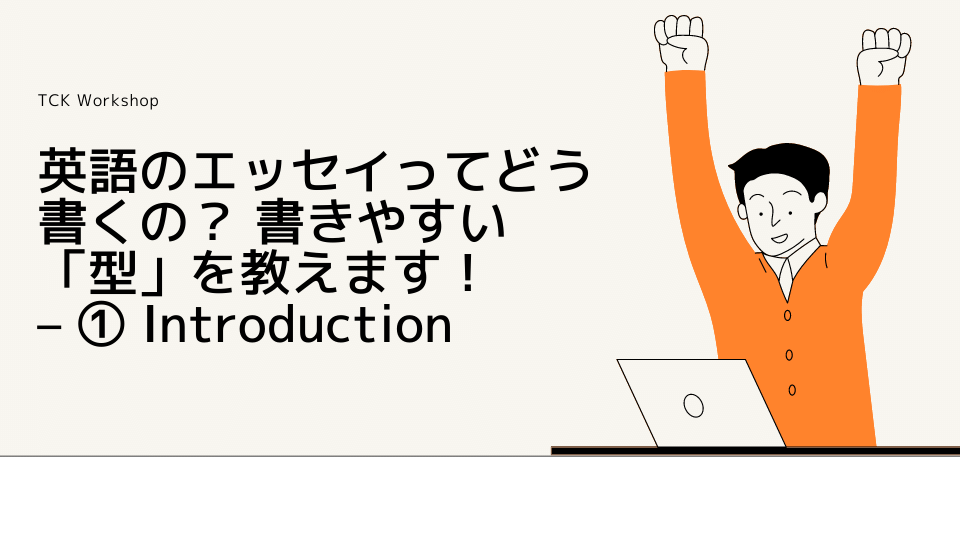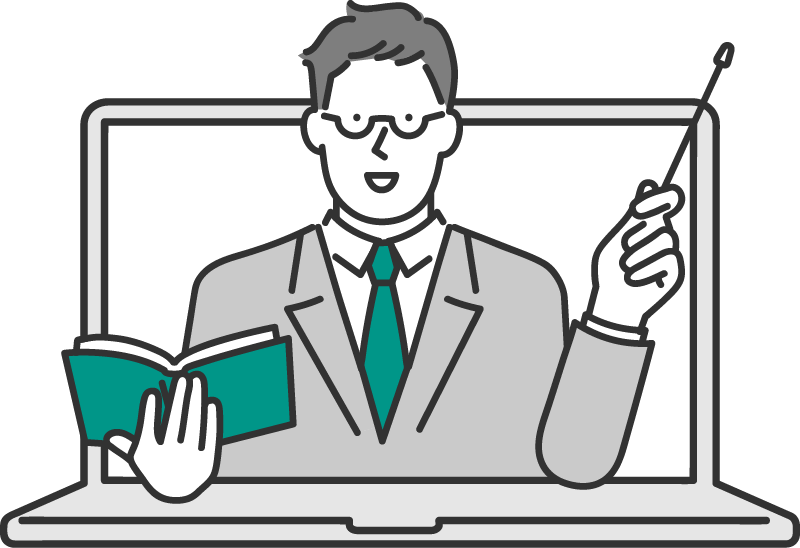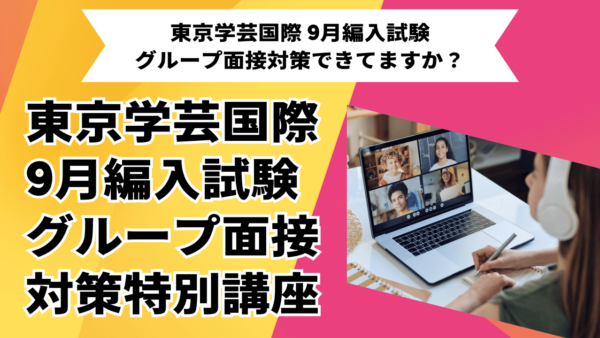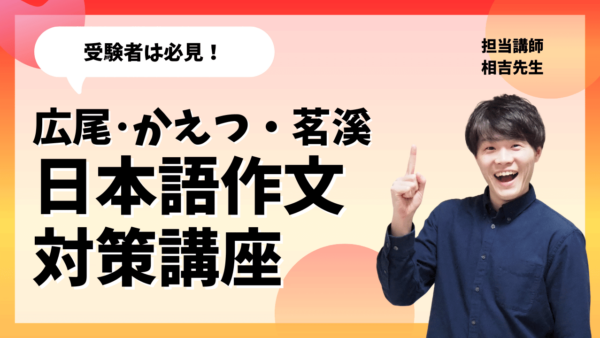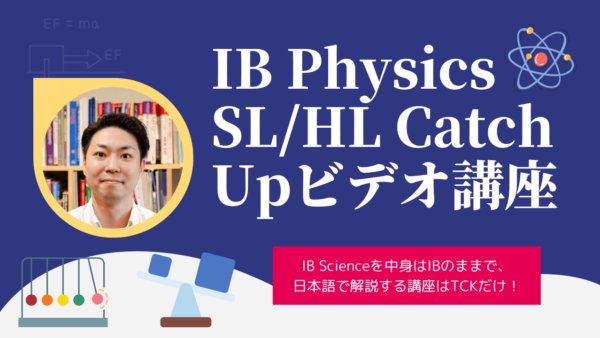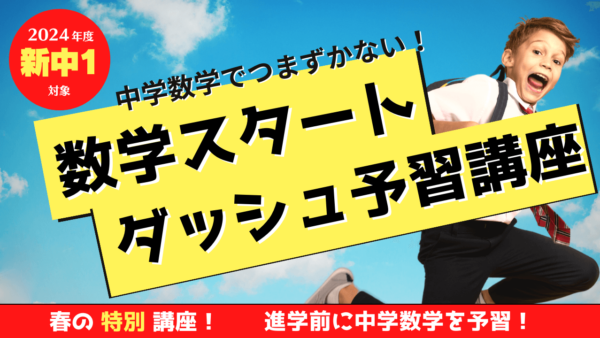現地校やインターナショナルスクールでは学んだことを文章にまとめるエッセイ(ライティング)課題が多く出されますが、「何をどうやって書けばいいのだろう…」と思っている方も多いと思います。
エッセイは、何を基準に採点されるのか、どのようなものが評価されやすいかを知らずに書き続けるとなかなか上達することができません。
そこで、今回は「エッセイの書き方を知りたい!」、「エッセイの苦手を克服したい!」という方に向けて以下の3点をご紹介します!
- エッセイの型
- エッセイの内容の決め方
- 避けるべきエッセイの書き方
英語エッセイの型とは?
英語のエッセイがなかなか書けないとき、どのような内容で書くかに気を取られてしまうかもしれません。
しかし、それより先に考えておくべきことがあります。
それは「エッセイの型 ( = 文章の流れ)」です。
英語のエッセイがどのような構成になっているかを知っておくと、それに当てはめるようにエッセイが書けるようになり、より内容に集中することができるのです!
では、英語エッセイの基本的な流れを確認しましょう。
- Introduction (メインパートの導入)
Introductory statement
Background
Thesis statement - Body paragraph (主張の背景・根拠の説明)
Topic sentence
Supporting evidence
Linking sentence - Conclusion (エッセイのまとめ・結論)
Restatement
Brief summary
Final statement
Introduction / Body Paragraph / Conclusionはさらに細かく分かれています。
それぞれのところでどんなことを書けばいいのかも確認していきましょう。
Introductionの書き方とは?

Introductionはエッセイで書いていく内容を紹介するところです。
このパートは単純にエッセイトピックを紹介するだけでなく、「このエッセイにはどんなことが書いてあるのだろう」と読者の関心をひきつけることが重要です。
実は、Introductionはエッセイの中で最も書くのが難しいと考える人も多いです。
それはなぜかと言うと、エッセイ全体のトピックがどのようなものか、そして、そのトピックに対する自分の意見はどのようなものかを短くまとめなければいけないからです。
初めは難しいかもしれませんが、「トピックを紹介すること」、「読者の関心を引きつけること」を意識しながら、以下のIntroductionの要素を確認していきましょう。
| Introduction | Introductory statement Background Thesis statement |
Introductory statement
エッセイの最初、Introductory statementではそのトピックに関する興味を読者に持ってもらえるようなセンテンスを書きます。
これにはいくつか例があるので、「子どもにとって都市部は地方より危険である」という考えに反対するエッセイを書くつもりでそれらの例を見ていきましょう。
- 質問を投げかける
日本は安全な国であると言われているが、そもそも我々は何をもって「安全」とみなすのだろうか。
- 本などから言葉を引用する
アメリカ出身の随筆家ジェイムズは1965年に日本を訪れたときの経験をまとめた著書「Japan – The Country of Beauty」に日本の治安について以下のようなことを書いている…
この本は架空のものです。また、他人の著作を引用するときのルールは別途確認が必要です。 - 最近の話題を入れる
日本は長らく安全な国だと言われてきたが、最近は日本の治安悪化を心配する声が多く聞かれる。
このように、いきなり本題に入るのではなく、まずは読者に自分がこれから書いていくトピックに興味を持ってもらえるような文を入れましょう。
どれを使うかは今のエッセイスキルと相談しながら決めることになりますが、このなかで一番取り組みやすいのは「質問を投げかける」だと思いますので、これからトライするのもいいと思います!
Background
読者の関心を引けたら次はBackgroundです。
ここではトピックに関する一般的に知られている事実やデータを示します。
上の例でいうと、日本の治安に関するデータや考え方をさらに説明するとよいですね。
ここでそのような情報をしっかり示せていると、読者は出てくる話について少し詳しくなれるためエッセイの内容が理解しやすくなりますし、さらにエッセイの内容に興味を持ちやすくなります。
また、ここでは全体の流れとして広い視点からより自分の主張に関係する点にフォーカスするような話の展開を心がけましょう。
例えば、最初に日本全体の治安など大きな視点でエッセイを始めていたら、「子ども」、「都市部の安全 vs 地方の安全」というキーワードに気をつけ、だんだん焦点をしぼっていくようなイメージを持つとよいです。
これが次のThesis statementにつながります。
Thesis statement
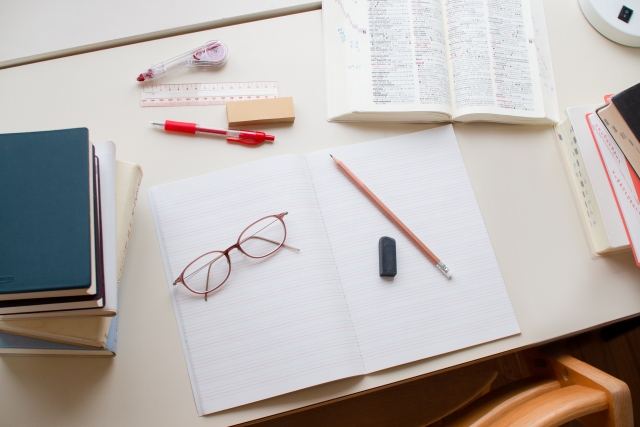
トピックに関するBackgroundを説明できたら、次はIntroductionのなかで最も重要、そして、エッセイ全体でも特に重要なThesis statementが来ます。
これはエッセイの主張を短くまとめるもので、エッセイ全体にどのようなことが書かれているかを表さなければいけません。
そして、基本的にはThesis statementは一文で書きます。
このようにエッセイの難しさのひとつは伝えたいことを短くまとめることです。
そして、もうひとつ大事なことがあります。
それはThesis statementではあいまいな立場は避けることです。
賛成なのか反対なのかわからないようなThesis statementを書くと、そのあとのエッセイでの議論の方向性が定まらなくなってしまいます。
例えば、
- 子どもにとって都市部はある人が見ると安全で、他の見方をすると危険である。
というより
- 都市部が地方より子どもにとって危険であるとは言えない。
というような言い切った形で書くようにしてみましょう。
このように自分の立場をはっきりさせた上で次のBody paragraphに移りましょう!
- Introductory statement – 読者の関心を引くようなセンテンス
- Background – トピックに関する事実やデータの説明
- Thesis statement – エッセイ全体の主張
Introductionでは自分の伝えたいことを短くまとめるスキルも重要!
IntroductionではThesis statementなど、短くまとめるスキルが必要です。
ただ、短くすればいいというわけではなく、入れるべき内容をしっかり入れたうえで短くすることが重要です。
このようなスキルは最初から身につけるのは不可能です。それくらい難しいのがIntroductionなのです。
なので、実は結構多くの人がエッセイを書く順番としてIntroductionを最後に書いています。
それはなぜかというと、最後まで書いてエッセイの全ての内容がしっかり把握できてていると、そのなかでも特に重要な点を抜き出し、話の流れが把握でき、短くまとめやすいからです。
もし、初めからIntroductionを書くのが難しければ、最後に書くというこの方法を試してみてください!
とはいうものの、やはり初めはどのようにIntroductionをまとめればいいのか自分で考えるのは大変ですね…
自分が書いた文に大切な情報が欠けていないか、十分に短くまとめられた文が欠けているか、といったことはエッセイがどのように評価されているかしっかり理解している人にチェックしてもらいながら練習するのが効率的です。
弊社ではエッセイライティングの経験が豊富な講師が文を短くまとめるコツや情報を効率的にまとめる書き方を指導することが可能です!
Introductionの書き方 まとめ
いかがでしたか?
Introductionでは単純にエッセイで書いていく内容を紹介するだけなく、読者の興味をひいたり、自分のメインの主張を短く述べたりとたくさんのことをしなければなりません。
しかし、いったんそれらのスキルを習得するとそのあとのエッセイが読みやすくなりますし、同じスキルを何度も使うことができます。
特に短くまとめるということが最初は難しいと思いますが、自分のエッセイをチェックしてもらいながら少しずつ能力を伸ばしていきましょう。
Introductionのあとはエッセイの主張のメインパートとも言えるBodyの部分がきます。
こちらに関する記事もぜひご覧ください!