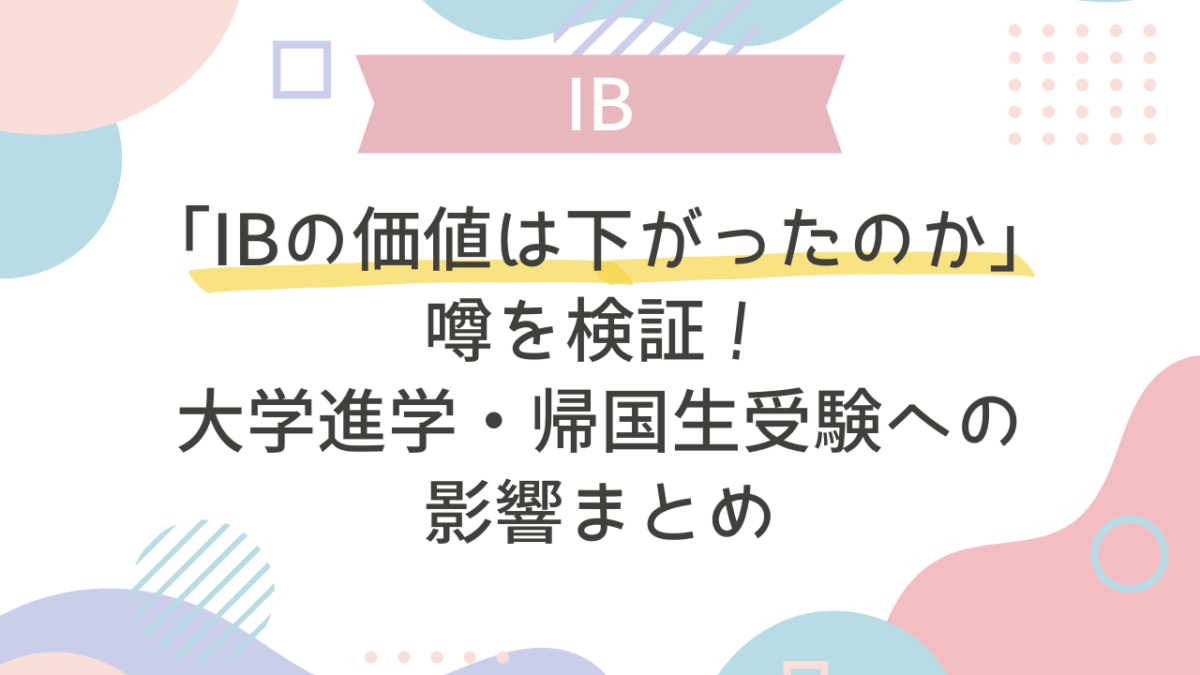はじめに
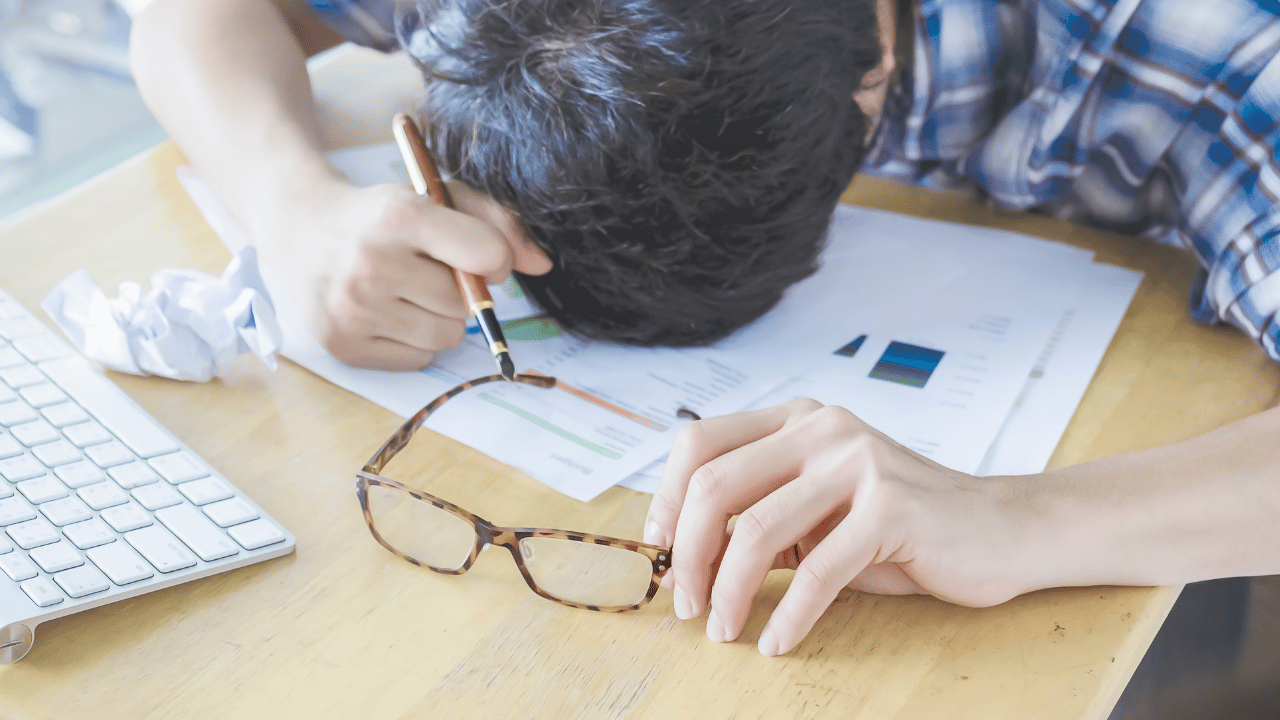
近年、「ロシアでIBが禁止された」というニュースや噂が保護者や生徒の間で広まり、不安を感じている方が少なくありません。特に帰国子女受験や海外大学進学を検討している家庭では、「このままIBを選んで良いのだろうか」という疑問が強まっています。
しかし結論から言えば、IB(国際バカロレア)の国際的な認知度や大学での評価は依然として堅固であり、日本国内でも導入数は増加傾向にあります。本記事では、TCK Workshop講師のウェビナーで話題となったロシアのIB禁止のニュースを出発点に、IBの価値を一次情報から検証し、帰国生や海外大進学を目指す方にとっての実務的な影響と今後の戦略を整理していきます。
ロシアで起きた「IB禁止」の背景とは
2025年8月、ロシア政府はロシア内でのIB教育を停止するよう発表しました。これにより、国内でIBプログラムを実施していた約30校は契約を維持できず、事実上IB教育を提供できない状況に追い込まれました。この判断の背景には、IBが欧米的価値観に基づく教育であると見なされた点があり、国家のイデオロギーと合致しないと判断されたことが要因とされています。
国際バカロレア機構(IBO)は直ちにIBのカリキュラムが思想に偏りはないと声明を発表し、自らは政治的な組織ではなく、160を超える国や地域で教育フレームワークを柔軟に提供していると強調しました。
世界規模で見たときのIBの現状

国際的な視点で見れば、IBの価値が低下しているという証拠はありません。国際バカロレア機構の最新統計によると、2024年時点で世界5,900校以上がIBプログラムを提供し、合計で8,000を超えるプログラムが稼働しています。導入国・地域は160を超え、むしろ拡大基調が続いている状況です。
日本国内でも、文部科学省とIBOの協力により「200プログラム達成」という節目を越え、2024年末には250を超えるプログラム(PYP、MYP、DP、CPを含む)が展開されています。とくに日本語と英語を併用できる「デュアルランゲージDP」が広がりつつあり、帰国生や国内在住の生徒にとって選択肢が豊かになっています。
つまり、ロシアのケースを一般化して「IBの価値は下がっている」と断定するのは誤解であり、実際には世界的にも日本国内でも導入数が増え続けているのが現実です。
大学でのIBの評価はどう変化しているのか
海外大学に進学する場合、IBは依然として主要な入学資格の一つとして高く評価されています。アメリカやイギリスをはじめとする多くの大学では、IBスコアを入学審査に利用しており、一定のスコアを満たすことで入学条件が緩和される場合や、大学入学後に単位として認定される場合もあります。
大学によっては、特定の学部に出願するために必要なHL(Higher Level)科目が指定されており、理系志望なら数学AA HLや理科HLが必須、文系志望ならエッセイ科目のHLが求められるなどの条件があります。また、Extended EssayやTOK(知の理論)の成果を出願書類と組み合わせることで、学びの一貫性を効果的にアピールできる点もIBの強みです。
結論として、IBは世界中の大学で制度的に認知され続けており、その教育的価値が低下しているという事実は見当たりません。
帰国生・海外大志望者への実務的な影響

ロシアに在住している場合、IBを履修し続けることは難しくなるため、国内カリキュラムやアメリカ式、APやA-levelといった他の国際資格への移行が必要になります。その際には、出願予定の大学がどの資格を認めているかを必ず確認することが重要です。
一方で、日本在住や日本への帰国を予定している家庭にとっては、国内で選べるIB校が増えているため、むしろ利便性が高まっています。特にDPを提供している学校では、日本語DPや英語DPの選択肢、Extended EssayやInternal Assessmentの指導体制などを学校説明会で確認すると良いでしょう。
海外大学進学を目指す場合には、IBスコアに加えて英語力証明(TOEFLやIELTS)、さらにはSATや英検などのスコアが出願条件として必要になる場合があります。つまり、IBだけで出願条件を満たすケースはむしろ少なく、IBは総合的な出願準備の中核に位置づけられるものの一つであると理解すべきです。
Solution|IB学習を不安から「強み」へ変えるためにできること
公式情報を一次確認する姿勢を持つ
SNSや噂に左右されるのではなく、志望大学の公式サイトやIBOの認知データベースを確認する習慣を持つことが最も大切です。大学によってはHL科目や総合点に明確な基準を設けているため、必ず出願予定の学部・学科単位で要件を確認しましょう。
HLとSLの選択を戦略的に行う
学部で必要とされる知識領域をHLに設定し、Extended Essayを将来進学したい分野と接続させることで、学習の一貫性を示すことができます。日本語DPか英語DPかを選ぶ際には、現在の得意科目や将来必要となる学術言語を考慮して決定すると良いでしょう。
外部試験との並走計画を立てる
IBだけで進学条件を満たすのは難しいため、TOEFLやSATなどの試験との並行学習が欠かせません。特にIBのIAやTOK、EEの提出が重なる時期と試験勉強が競合しないように計画を立てることが重要です。
出願書類と学習成果を一貫させる
Personal Statementや志望理由書は、IBで取り組んだExtended EssayやCAS活動と関連づけることで説得力を増します。これにより、大学に対して「自分の学びを一貫したテーマで深化させてきた」という印象を与えることができます。
国内の学校選びを現実的に設計する
国内のIB校に進学するか、一般受験校と併願するかは家庭ごとに異なります。重要なのは、学習言語、費用、地域などの条件を整理したうえで、複数の選択肢を持つことです。特に帰国生にとっては、IB校と一般校を併願する戦略がリスクヘッジとして有効です。
誤解と事実を整理する
「ロシアで禁止されたから、このままIBを選んで良いのだろうか」という悩みは誤解であり、世界全体では導入数が増加しています。
また「IBさえあれば海外大学に行ける」というのも誤りで、外部試験や書類審査との総合評価が求められます。さらに「日本ではIBはまだマイナー」という認識も過去のものとなり、国内の導入数は着実に増えています。
まとめ
IBの価値が下がったという噂がありますが、実際には世界規模でも日本国内でも導入は拡大しており、大学進学における評価も堅固に維持されています。受験生と保護者に必要なのは、不確かな噂に振り回されることではなく、志望大学の要件を正しく把握し、IB学習を外部試験や出願準備と一体的に設計することです。
TCK Workshopからのご案内
TCK Workshopでは、帰国子女や海外大学進学を目指す生徒に向けて、IB学習と受験対策を「要件から逆算する」形でサポートしています。IAやTOK、EEの指導から、英検やTOEFL、SATなどの外部試験対策、さらには志望理由書や面接準備までを一貫してカバーします。
まずは無料教育相談で、お子様の状況や志望校に最適化した学習プランを一緒に設計していきましょう!