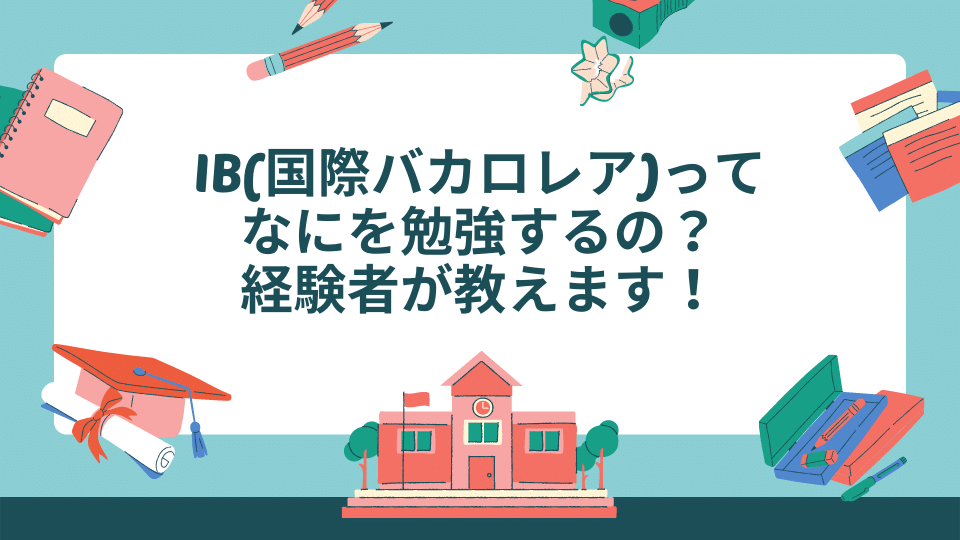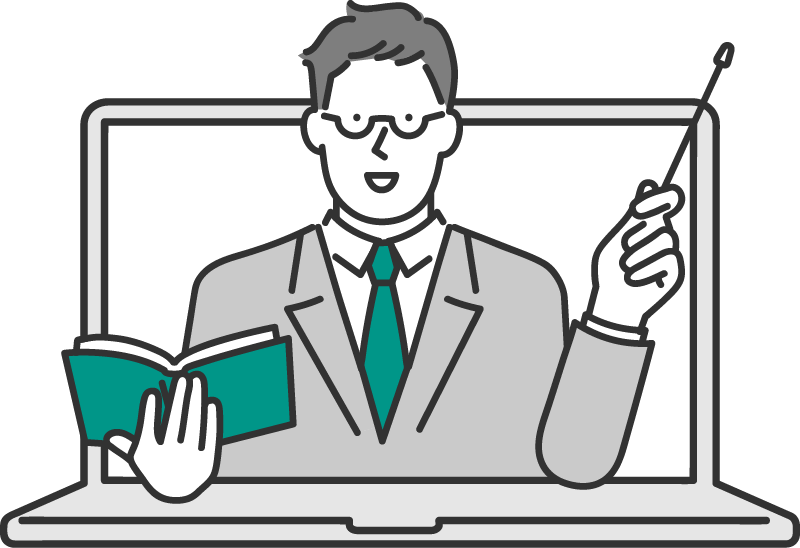高等学校の教育プログラム、国際バカロレアことInternational Baccalaureate(通称IB)。最近では、海外の高校だけでなく、日本国内でこのカリキュラムを提供している学校も増えてきています。
大学の入試でも、IBの成績表を持っているなら提出してください、と指示してくる学校も増える中、やはりまだ「IBって聞いたことはあるけど、具体的に何をするカリキュラムなのか分からない……」と思う方は多いと思います。今回は「これからIBに挑戦したい人」「少しだけIBに興味ある人」に向けて、
- そもそもIBってどんなプログラム?
- どういった科目を学べるの?IBを選択するメリット・デメリットは?
- IBでよく聞く「EE、ToK、CAS」って何?
という以上の3点についてご紹介していきたいと思います!
そもそもIBとは?
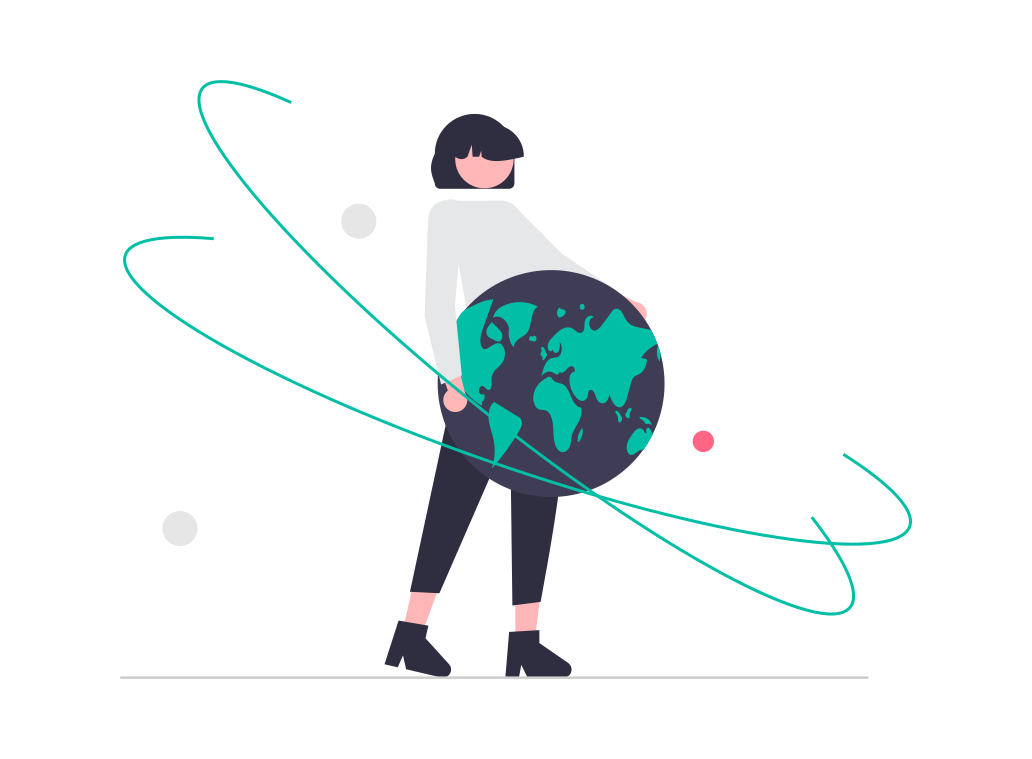
IB(国際バカロレア)は「全人教育」をモットーに掲げた「世界のどこにいても通用する大学入試資格」を提供するカリキュラムです。IBには、
- 小学校に相当する初等教育(PYP)
- 中等教育相当のミッドイヤープログラム(MYP)
- 高校2年次から学ぶディプロマ資格(DP)プログラム
の3種類がありますが、このDPの最後の年に受ける共通試験が最終的なIBの資格となり、多くの大学の入学試験で提出できるスコアになります。
そのため、単にIBというと「DP」を指す場合が多く、国内外の学校でも「DP」カリキュラムだけを専門に提供しているという学校も多くあります。
以下、こちらの記事では主にこの「IBディプロマ(DP)」について説明していきたいと思います。
IB教育が目指す人物像とは?
IBでは、生徒を取り巻く環境(国・地域・学校形態など)を問わず、充実した学びを享受することができるという点に重きをおいたカリキュラムを組んでいます。その中で特に重要視しているのが、IB教育が目指す人材のプロファイル【IB Learner Profile】の養成です。
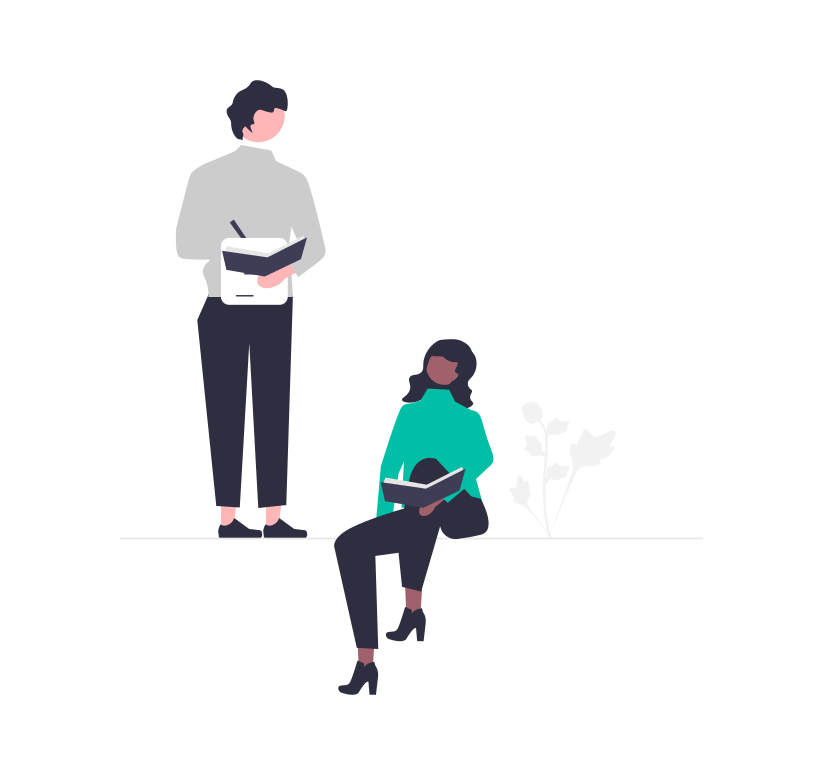
IBは提供するプログラムの中で、Inquirers、Knowledgeable、Thinkers、Communicators、Principled、Open-minded、Caring、Risk-takers、Balanced、Reflectiveという、10個の特徴、性格、考え方などを育てることを目標としています。
探究心がある、広い視野・心を持って物事を捉えることができる、学んだことをきちんと振り返って考えることができる、しっかりとコミュニケーションができる……などなど、大人になってもずっと役に立つスキルが多いのが特徴です。
これらの目標を満たすため、IBでは、A-levelなどの他の国際的な大学入学資格と異なり、CASやEE、ToKなど独自の課題や科目を生徒に課しており、2年間のプログラム内でこれらのタスクを熟さなければ、主要科目の点数にかかわらずディプロマを取得することはできません。
CASやEE、ToKについては、後ほど詳しく解説させていただきます!
IBディプロマの成績構成
IBディプロマでは、2年間かけて6つの教科を学びます。
成績は各教科7点満点で、最終的にはEEやToKの成績によるボーナスポイントが最大3点もらえますので、合計45点満点のスコアが算出されます。IBDPを持っている場合、この45点満点のスコアが大学入試の結果を左右する重要な数字となっています。
IBの公式情報によりますと、2021年のIB取得者の平均点は32.39点、7点満点の各教科の全教科平均点数は5.19点となっているそうです。
Ivy Leagueなどの最難関大学を受験する目安がおおよそ満点~42点、難関大学であれば40点以上~30点台後半で射程圏内と言われています。
とはいえ、ハイレベルなカリキュラムで知られるIBにて好成績を収めるのは簡単なことではありません。IBを始めてみたはいいけれど学校の先生と相性が悪い、授業だけではついていけないなど様々なケースがありますし、IBを始める前に予め準備をしておきたいという方もいらっしゃるのではないかと思います。弊社TCK Workshopでは、指導経験豊富な講師陣が、皆さまのIB対策から大学選びまでしっかりとサポートさせていただきます。
「IBについて詳しく知りたい」「IBコースに行こうか悩んでいるけど自分の成績・英語力でついていけるか不安……」など、まずは無料学習相談から、是非お気軽にお問い合わせください!
- IBには、初等教育相当のPYPから中学校相当のMYP、高等教育に当たるDPの3種類がある
- 探究心や広い視野を持つ人物育成のため、様々な課外活動(CAS)や特殊な科目(ToK)、リサーチ課題(EE)を課している
- 6教科×7点+EE/ToKによるボーナスポイント3点の45点満点
- 2021年度の平均点は45点満点中32.39点。難関大学を志望するなら40点以上の取得を目指したい
IBの科目について

さて、IBでは6つの科目を選択して履修しますが、基本的には、IBが用意している6つのグループの中からそれぞれ1つずつ選ばなくてはなりません。6つの科目グループは以下の通りです。
| Studies in language and literature | Language A科目(第1言語) |
| Language acquisition | Language B科目(第2言語) |
| Individuals and societies | 経済、地理、歴史、心理学、文化人類学など |
| Sciences | 生物、物理、化学、スポーツ健康科学など |
| Mathematics | 難易度別に数学の授業が3つほどあります |
| The arts | ダンス、音楽、演劇、美術など |
科目選択は各グループから1科目が基本となりますが、例外的に、Group 6の「The Arts」のみ、希望する生徒はこれを選択せず、6教科目として任意の別グループからもう1科目を選択することが可能です。
例えば、理系や理工系の学部へ進学を希望しているという場合、大学の入試要項に「Scienceグループから2科目選択していること」などの制約がつけられていることがあります。こういった場合、the Artを取らずに、「PhysicsとChemistry」あるいは「BioとChemistry」など、好きなScience科目を2つ選んで受講しましょう。
IBの特徴として、教師や教える環境が整っていないと選択科目を提供できない、という点もあるので、実際に受けることのできるIB科目については、進学予定・進学希望の学校に直接問い合わせてみることをオススメします。
学校によっては公式HPなどに履修可能な科目がのっている場合もありますので、チェックしてみましょう!
IBでは、これらの6科目のうち3科目をHigher Level(HL)で、残りのもう3科目をStandard Level(SL)で履修します。名前の通り、同じ科目でもHLの方が全体的にレベルが高く、履修範囲も広くなります。
科目によって例外はありますが、基本的にはほとんどの科目でHL、SLが用意されていますので、自分の得意な科目や興味のある科目をHLで選択するというケースがほとんどです。志望する学部によっては、大学側で「この科目をHLで履修していることが出願必須要件」という場合もありますので、進路の目途が立っている場合は、履修前にしっかりと確認しておきましょう。
HLは1教科240時間以上、SLは1教科150時間以上の授業を受けることが前提となっています。
- 第1言語、第2言語、社会、理科、数学、芸術の6グループから各1~2科目選択し、合計6科目を履修
- Group 6のThe Artをとらずに他Groupの教科を2つ選択することも可能
- 志望する大学や学部によっては履修が必須となる科目もあるので注意
- Higher Level (HL)とStandard Level (SL)を3つずつ履修。レベルによって難易度や授業時間数が異なる
以下、各Groupの特徴や履修上の注意点などについてお話します!
Group 1:Studies in language and literature
こちらはIBで「Language A」と呼ばれる、第1言語を勉強するための科目となります。
多くの生徒が自分の母国語を選択しますが、英語の得意な非英語母語話者でLanguage Aとして英語を選択するケースもあります。

ネイティブの中でネイティブレベルの授業・試験を受けることになりますのでかなりハードルの高い選択ではありますが、大学によってはIBDPにてLanguage AでEnglishを選択し一定以上の成績を修めた場合TOEFLやIELTSなどの語学試験が免除されるというケースもあるので、英語に自信があるという方は、是非English Aの選択も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
母国語を履修するためのグループではありますが、日本語などあまり履修する生徒数の多くない言語の場合、海外、特にヨーロッパ圏のインター校・現地校ですと「Japanese A」という科目が用意されていない場合があります。
そういった場合でも、Japanese Aを選択することは可能ですが、その場合は「Japanese A Self-taught」という扱いになり、特に教師がいない中、ひとりで勉強し試験を受ける、ということになります。
基本的には一般的な「Japanese A」と変わりませんが、Self-taughtの場合はHLの履修が不可となっており、SLでの履修ということになり、プレゼンテーション課題や口述試験などについては「対人ではなくボイスレコーダーに向かって発表を行う」という形になります。
Group 2:Language acquisition

こちらも言語系の科目ではありますが、第1言語を勉強するGroup 1に対してこちらは第2言語を勉強する「Language B」の科目となっています。日本人のIB生ですと、英語(English B)を選択することが多いのではないかと思います。
学校によっては英語母語話者など向けに「French B」や「German B」などの科目もありますが、「B」とついている科目はあくまで「中学校などで基本的な語彙・文法を勉強したことのある人向け」のカリキュラムとなっていますので、今までに勉強したことがない言語を選択することはできません。
学校によっては、「ab initio」といって、習ったことのない言語をイチから学ぶ科目を用意していることもあります。
フランス語、スペイン語、中国語などを用意している学校が多いようで、インター校などですと、その言語を母語とする友人などに教えてもらうこともでき、楽しいかもしれませんね!
「English Aを履修しているけどフランス語やドイツ語などの多言語は知らない……」という方にもおすすめです。ただし、ab initioはSL限定の科目となっていますので、その点は注意が必要です。
Group 3:Individuals and societies
Group 3は日本でいう「社会」にあたる教科になります。
- History
- Geography
- Economics
などがメジャーな科目で、学校によってはPsychologyやEnviromental System (E-system)、World Religionなど多様な科目が提供されています。
試験は一問一答式というよりも大きな設問に対してエッセイを書き上げていくような記述式の科目が多く、英語の苦手なノンネイティヴにとってはハードルの高い教科でもあります。コンセプトだけでなく用例などもしっかりと暗記し、各教科の答え方の「型」をしっかりと掴んでおくことがポイントです。
Group 4:Sciences
Gropup 4は読んで字の如く理科系科目のグループになります。
- Physics
- Chemistry
- Biology

などが基本的な科目ですが、学校によってはDesign Technology、Computer Sceienceなどを履修することもできます。
Group 3で述べた「Enviromental System」は少し特殊な科目で、Group 4の教科として選択することも可能です。理系科目が苦手な学生さんが、Group 4 subjectとしてこちらのE-systemを履修する場合が多い印象ですが、計算が少ない分、コンセプトや用語の暗記はむしろ多めの科目となっていますので、英語が苦手という方は要注意です!
Group 5:Mathematics
Group 5は数学のグループです。数学は、
- Analysis and Approaches (AA)
- Application and Interpretation (AI)
の2種類に分かれており、それぞれにHLとSLのクラスがあるので合計4種類の中から自分に合ったレベル・内容のものを選択するという形になります。
AAはいわゆる純粋数学に近いもので、CalculusやStatistics、Probability & Distributionなどをバランスよく勉強します。
それに対して、AIはより実生活に即した数学を扱う側面が強く、Calculusの比重が大幅に減り、その代わりにStatisticsを深く勉強します。
一般的にAAよりもAIの方が難易度が低いと言われていますが、AIはCalculusなどのレベルはそう高くない一方でStatisticsなどの単元でしっかりと電卓の使い方を覚え、様々なコンセプトを本質的に理解しておく必要がある科目です。現実に在りそうなシチュエーションの文章題をしっかりと読み解く力も求められますので、英語がハードルになってしまう場合もあるかもしれません。
周囲の情報に惑わされず、しっかりと自分でシラバスをチェックし、自分に合った科目を選択しましょう!
Group 6:Arts
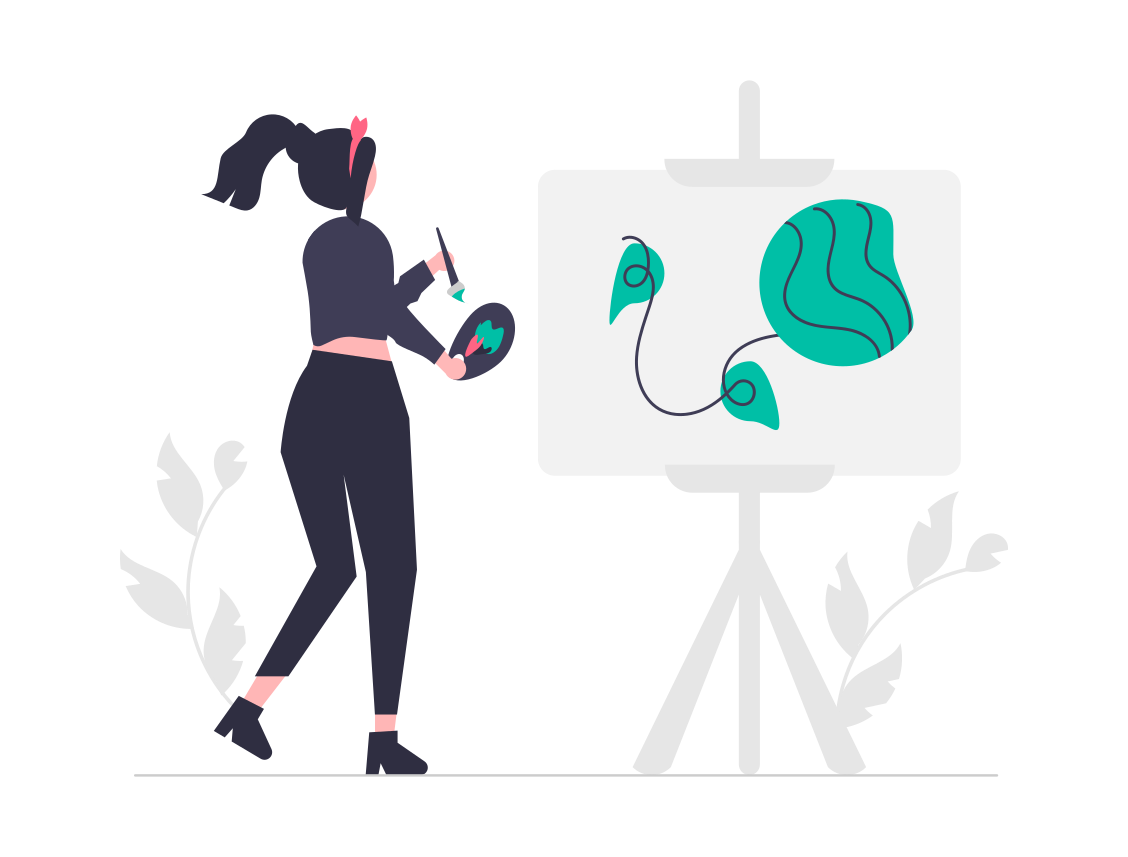
Group 6は芸術科目のグループで、Visual ArtやMusicといったスタンダードな科目から、TheaterやFilmといった日本の学校ではあまり馴染みのない科目まで様々です。学校によって提供していない科目もありますが、Visual ArtやMusicなどは多くの学校で開講している印象です。
また、前述の通り、IBDPの学生はGroup 6科目を選択せず、代わりに任意の他グループの科目をひとつ選択することもできます。
例えば、Language BにくわえてLanguage ab initioを学習したい、あるいはPhysicsとChemistryなどScience科目を2つ勉強したいという場合には、Group 6を選択せずに好きなグループから追加で1科目履修することが可能です。
- Group 1 (母国語):日本語は、Self-taughtと呼ばれる自習科目(SL限定)になることも
- Group 2 (第2言語以降):第2言語の他、初学者向けの「ab initio」(SL限定)の履修が可能
- Group 3 (社会):記述式問題が多いので英語が苦手な人は要注意
- Group 4 (理科):Environmental SystemはGroup 3としてもGroup 4としても選択可能
- Group 5 (数学):純粋数学に近いAnalysis and Approachesと応用数学に近いApplication and Interpretationの2種類から選択
- Group 6 (芸術):Group 6科目の代わりに、他Groupからもう1教科選択することも可能
IBの各科目についての簡単な解説は以上になりますが、6つの分野から、バランスよく様々な科目を選ぶことができるようになっているのがご覧いただけたのではないかと思います。
科目の選択肢が多いので、生徒一人ひとりが、本当に興味を持てる教科を選びやすく、モチベーションを保ちながらしっかりと学力を伸ばすことができるのではないかと思います。
たとえ苦労をする科目があっても、やりたい勉強ができていたり、モチベーションを高く保てる科目があると、それだけでも頑張ろう!という気持ちになれることもあるのではないかと思います。
私も、生物や数学がとても苦手だったのですが、芸術科目で選んでいた演劇や、英文学・日本文学の授業がとにかく楽しかったので、苦手科目も頑張って全体の成績の足を引っ張らないように……!と取り組むことができました!
EE、TOK、CASについて
IBの教育の大きな特徴の一つとして、EE、ToK、CASが挙げられます。これらの科目・活動は、通常の選択科目以外に、全IB生が必修として取り組まなければならないものとなっています。
これらの活動を通じて、ただ科目の勉強をこなすだけではなく、頭をやわらかくしながら、さまざまなテーマについて考え、論じていく力をつけていきます。
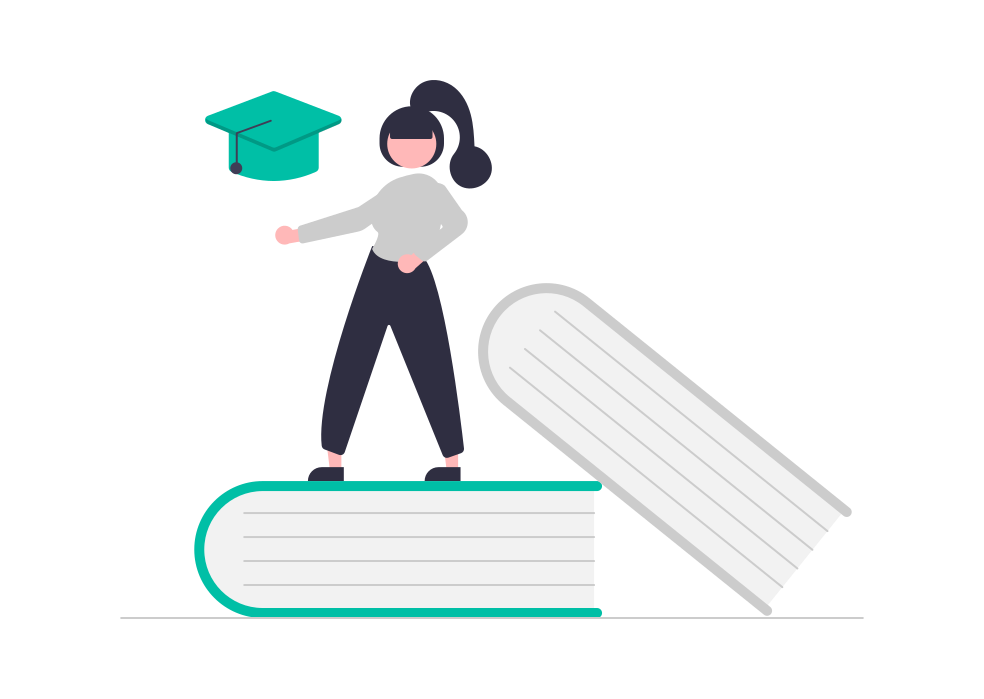
| Extended Essay | 一人で書き上げる、英語で4,000 words程度のリサーチレポートです。 いわゆる卒業論文に近いものとなっており、選択している科目の中から1科目選んでレポートを作成します。 テーマ決めから自分で研究を計画し、ひとつの論文として仕上げていきます。A~Eまでの評定がつきます。 |
| Theory of Knowledge | 「知るということはどういうことなのか」をテーマに考える授業です。 学内で行うプレゼンテーションと、1,600 wordsのレポートを元に、A~Eまでの間で評価されます。 |
| Creativity、Action、Service | 創造力などを育てるCreativity、新しいことに挑戦するActivity、そしてボランティア活動など人と交流しコミュニティーのために何かをするService。 一定時間以上(最低週3時間が目安)、これらの活動をバランスよく行い、各活動に合わせてレポートを書きます。 |
EEとToKについては、課題を元にA~Eの間で評価がつき、その組み合わせによってボーナスポイント最大3点が成績に加算されますので、各教科の成績と同じく最終的に大学に提出するスコアに関わってくる大切な得点源となっています。
双方ともA、あるいはどちらかがAかつもう一方がBで3点、双方ともB、あるいはAとC、BとCの組み合わせで2点、というように、EEとToKの評定によってボーナスポイントの点数も変わります。
IBで少しでも高い点数を取得したいということであれば、これらの課題も、主要教科でないからといって手を抜かずしっかりと取り組む必要があるでしょう。
IBDPの取得に必要な点数
IBを履修したからといって、すべての学生がIBディプロマを取得できるというわけではありません。IBDPを修了したと認められるためには、各教科やEE・ToKで一定の成績を修める必要があります。
6科目の成績42点とボーナスポイントの3点を合わせた45点満点中、ディプロマを取得するためには、最低でも24点以上の点数を取得していることが求められます。その他にも、
- EEとToKの評定が両方ともE
- CASへの取り組みが、IBの規定する分量以下
- 7点満点で1点の教科がひとつでもある
- 7点満点で3点以下の科目が4つ以上ある
など、ディプロマ取得が認められないケースはいくつかあります。
特にHLレベルの教科で2以下の評定がついてしまうとDP修了が認められない場合が増えてしまうので、科目の選択には充分注意し、苦手科目では授業においていかれないよう、日頃からしっかりと復習に取り組むことが大切です!
まとめ
- 第1言語、第2言語、社会、理科、数学、芸術の6分野から各1~2教科を選んで履修
- EE(卒論)やToK、CASなどIB独自の課題や課外活動を行う
- 6教科7点満点+EE・ToKによるボーナスポイント3点の合計45点満点で成績がつく
- IBDPを取得するには最低点などの条件をクリアする必要がある
IBは6つの選択科目とEE、TOK、CASの活動を通して、幅広い学びと経験を積むことができます。
IBのLearner Profileを見ても、ただ勉強するだけでなく、それをどうやって解釈したり、人に伝えたりすることができるか?というスキルを育てることができることが分かります。
しかし、IBDPは同時に難易度の高いカリキュラムでもあり、これだけではDP取得に関する不安を拭いきれない、実際の体験談をもっと詳しく聞いてみたい、という方も多いのではないかと思います。
TCK Workshopでは、IB対策も含めたオンライン個別指導を行なっており、日本語・英語でのサポートが可能な講師が多く在籍しています。IBを実際に経験してきた講師に、体験談を聞いたり、科目選びのアドバイスを受けることも可能です!弊社のプロ講師陣と一緒に、IB対策をしてみませんか?
まずは無料学習相談、無料体験学習から、是非お気軽にお問い合わせください!