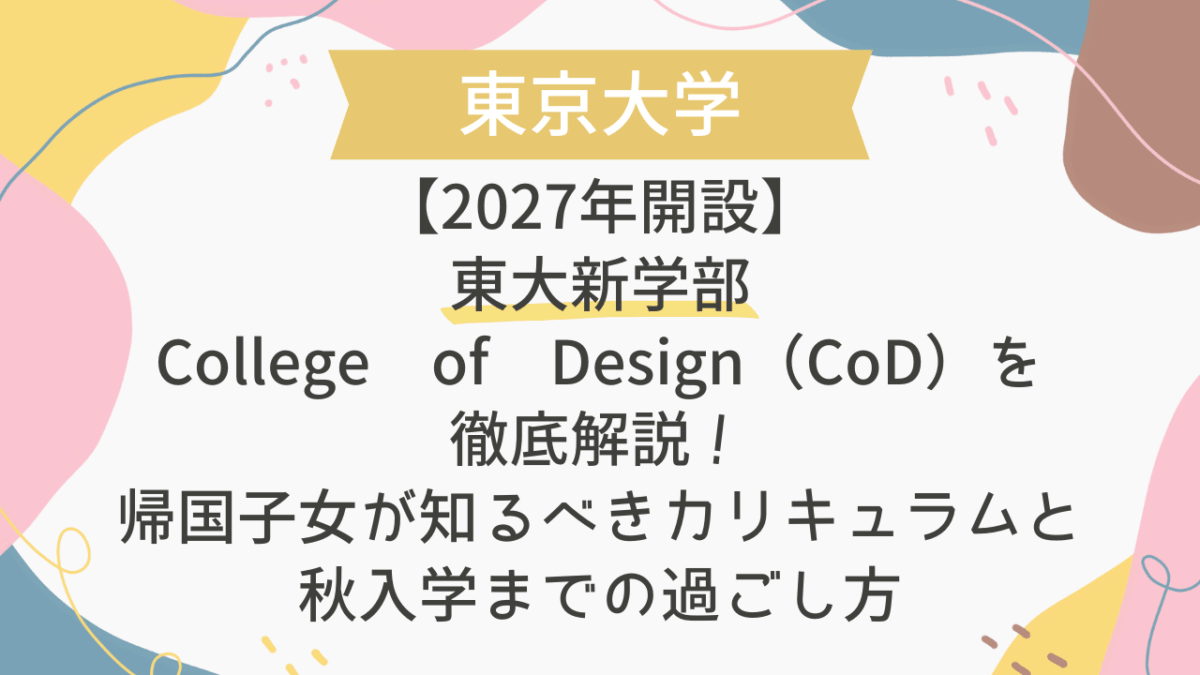2027年秋、東京大学が69年ぶりとなる新学部「College of Design(カレッジ・オブ・デザイン、通称CoD)」を開設するというニュースは、海外で学ぶご家庭や帰国子女にとって、これまでの大学受験の常識を覆す大きな衝撃でした。「東大で、英語だけで学位が取れる」「文系・理系の枠を超えたデザインを学ぶ」という構想は、日本の教育が「正解のある問いを解く」スタイルから脱却する転換点とも言えるでしょう。
しかし、前例のない学部だからこそ、このような疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

デザイン学部ということは、美大のように絵を描くスキルが必要なのか?

秋入学までの半年間(ギャップターム)はどう過ごせば評価されるのか?
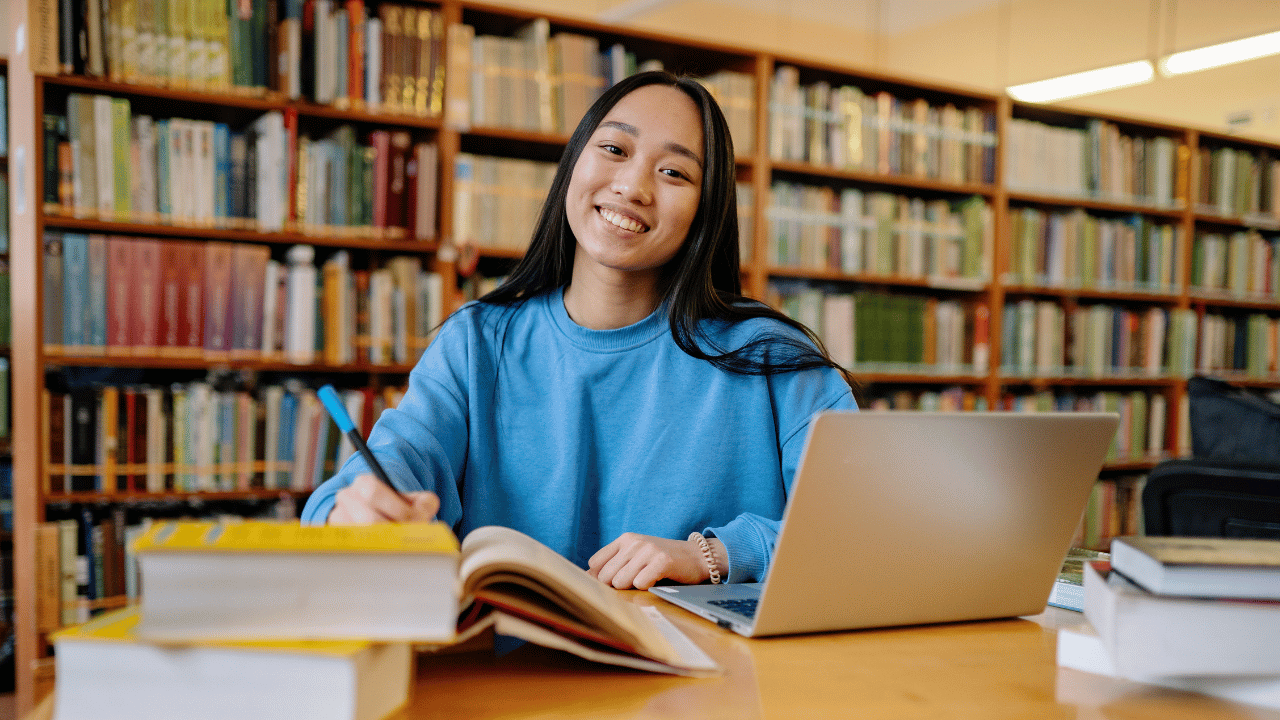
英語ができるだけで合格できるのか、それともSATやIBのスコアも重視されるのか?
本記事では、歴代総長たちが積み上げてきた改革の歴史からCoDの真の狙いを読み解き、帰国生受験のプロフェッショナルであるTCK Workshopの視点から、今から準備すべき具体的な合格戦略を徹底解説します。表面的な情報だけでなく、合格の鍵を握る「8つのデザイン手法」にも踏み込んで解説します。

TCK Workshop代表取締役、特別講師。ニューヨーク、サンフランシスコに滞在したのち帰国生の名門校である東京学芸大学附属高校に入学。早稲田大学の創造理工学部を卒業。TCK WorkshopではIB math、SAT、A-levels Physicsなど海外カリキュラムの理数科目の指導を中心に指導を担当。
東大が定義する新しい「デザイン」:歴代総長の悲願

CoDが目指すのは「工学の最先端研究を社会と結びつける」ことですが、どうしても「ものづくり」のイメージから離れられないという指摘も学内にはあります。だからこそ、受験生は「単にモノを作る」だけでなく、「そのモノが社会制度や人々の行動をどう変えるか」という法学的・社会学的な視点まで持っていることをアピールできれば、頭一つ抜け出せるでしょう。
まず誤解を解いておきたいのは、CoDは単に製品の見た目を良くする「意匠としてのデザイン」を学ぶ場所ではないということです。藤井輝夫総長が掲げる「デザイン」とは、複雑化する地球規模の課題を解決するための「社会システムの設計」です。
小宮山・濱田元総長からの系譜
この新学部は、突然生まれたものではありません。歴代総長の改革の集大成です。 小宮山宏元総長は、細分化されすぎた学問を繋ぎ合わせる「知の構造化」を提唱しました。CoDが目指す、既存の10学部(法、医、工、文など)の知を統合するカリキュラムは、まさにこの理念の具現化です。 濱田純一元総長も、 「よりグローバルに、よりタフに」を掲げ、秋入学の導入や英語コース(PEAK)の開設に尽力しました。2026年をもって募集停止となるPEAKは、発展的にCoDへと統合されます。
東大CoD vs 既存学部 vs PEAKの比較
| 項目 | College of Design (CoD) | 教養学部英語コース (PEAK) | 一般学部 (前期課程) |
| 使用言語 | すべて英語 | すべて英語 | 基本的に日本語 |
| 入学時期 | 秋入学 (9月/10月) | 秋入学 (9月/10月) | 春入学 (4月) |
| 学びのスタイル | スタジオ型 (実践・対話重視) | 講義・ゼミ形式 | 講義・実験形式 |
| 募集停止 | なし (新設) | 2026年で募集停止 (CoDへ統合) | 変更なし |
| 文理区分 | 文理融合 | 「国際日本研究」または「国際環境学」 | 文科一〜三類、理科一〜三類 |
| 求める学生像 | 社会システムを変革する「設計者」 | グローバルな教養人 | 高度な専門知識を持つ研究者・実務家 |
つまりCoDは、東大が長年模索してきた「国際化」と「知の統合」の最終回答であり、そこで求められる学生像は「クリエイター」というよりも、異なる分野の知恵を繋ぎ合わせて未来を構築できる「アーキテクト(設計者)」に近いのです。
英語で学ぶ「スタジオ型」教育とカリキュラムの全貌
CoDの授業スタイルは、日本の一般的な大学講義とは全く異なります。教室で静かにノートを取るのではなく、「スタジオ」と呼ばれるオープンスペースが学びの拠点となります。
スタジオを中心とした実践的学習 CoDが予定している情報基盤センター別館には、約400平方メートルもの広大な学生室が設けられる見込みです。
スタジオの特徴
・学生一人ひとりに作業スペース(ホームベース)が与えられる
・チームでプロジェクトに取り組む ・教員や仲間と常に対話し、フィードバックを受けながらアイデアを形にする
これは、英ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ(RCA)出身のマイルス・ペニントン学部長予定者が持ち込む、欧米のデザインスクールや建築学科に近いスタイルです。かつてマルクスが大英博物館の図書館にこもって資本論を構想したような「静的な知」ではなく、スタジオでの対話と実践から生まれる「動的な知」が重視されます。
4年間のカリキュラム構成
1年次
IF(Interdisciplinary Foundations) 必修科目として、既存の学部からの知見を概観します。ここで専門分野の基礎体力をつけます。
2・3年次
IP(Interdisciplinary Perspectives) 約100科目もの分野横断的な授業から選択します。ここではCoD学生だけでなく、他学部からの「アフィリエイト学生」も参加し、多様なバックグラウンドを持つ学生同士が議論します。
4年次
学外体験(Off Campus Experience) インターンシップやフィールドワーク、交換留学などが必修化されます。留学生は日本企業へ、日本人学生は国際企業へといったクロスカルチャーな経験が推奨されています。
帰国子女が直面する「秋入学」と「ギャップターム」の現実
CoDは9月または10月の「秋入学」を採用します。これにより、海外の学事暦で動いているIB生や現地校生にとってはスムーズに入学できるメリットがありますが、3月に日本の高校を卒業する生徒にとっては、約半年の「ギャップターム」が発生します。
ギャップタームは「諸刃の剣」
この半年間は、ボランティアやインターンシップなど、普段できない体験に充てる貴重な時間です。かつて東大が実施した「FLY Program」のような体験活動が推奨されるでしょう。 しかし、濱田元総長時代から懸念されているのが「体験格差」です。裕福な家庭が提供できる高額なプログラムと、そうでない場合で経験の差が開く可能性があります。大学側もサポートを検討していますが、受験生としては「自分なりのテーマを持って、主体的に半年をデザインする計画」を入試段階で持っておく必要があります。
まずは「無料学習相談」で現在地を確認しましょう

CoDの教員陣は、RCA出身者や実務経験者が中心です。彼らが求めているのは「テストの点数が高い優等生」だけではありません。「既存の学校教育に収まりきらなかった、とがった才能」や「社会に対する強烈な違和感を持っている生徒」です。TCK Workshopでは、生徒が隠し持っている「ユニークな視点」を引き出し、それを東大が求める文脈(コンテキスト)に合わせて翻訳するお手伝いをします。
東大College of Design(CoD)は、これからの時代に必要な力を養うための、非常に魅力的かつ挑戦的な選択肢ですが、東大CoDは新しい学部であるため、ネット上にもまだ十分な情報がありません。だからこそ、帰国生受験のプロと一緒に戦略を立てることが重要です。
入試情報は今後さらに具体化していきますが、求められる本質は「英語力」×「思考力」×「志」です。 「IBの科目選択、これでCoDに通用するか不安」 「SATのスコアが伸び悩んでいて、英語力証明に自信がない」 「エッセイで書けるような強烈な原体験がない」このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひTCK Workshopの無料学習相談をご利用ください。
無料相談でわかること:
- お子様の現在の英語力・学力で、CoD合格まであとどれくらいの距離があるか
- IB/SATなどの科目選択が、CoDの入試に有利に働いているか
- 今から半年間(または1年間)、具体的に週何時間の学習が必要か
「まだ志望校が決まりきっていない」という段階でも構いません。選択肢の一つとしてCoDを検討するための材料を提供いたします。