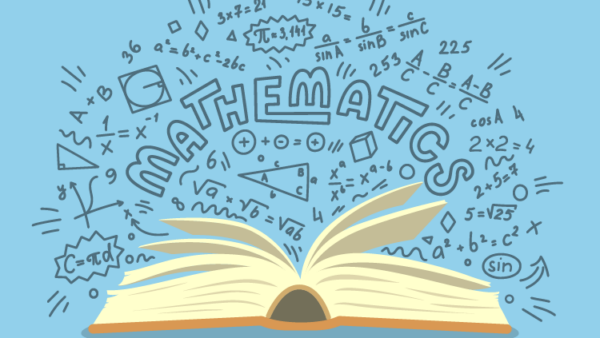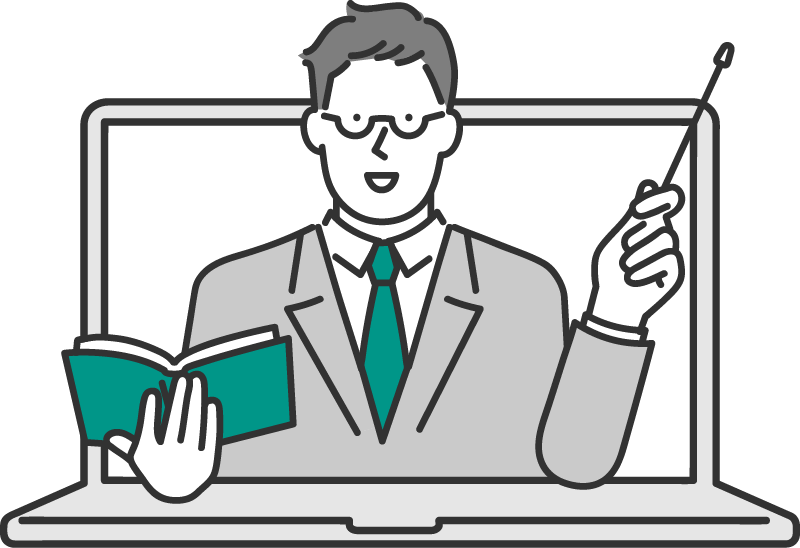いよいよこの秋からIB Mathematicsのカリキュラムの移行が始まります。国際バカロレア協会の公表によると、より実生活に基づいた内容、現実世界への応用を意識したカリキュラムとなっています。以前のカリキュラムと比べて、どのように変わるのか、解説していきます!
変更前のMathとのつながり
国際バカロレア協会が公表した具体的な変更点を見ていきましょう。
Mathematics: Analysis and approaches course will be offered at both SL and HL. It is designed for students who enjoy developing their mathematics to become fluent in the construction of mathematical arguments and develop strong skills in mathematical thinking. They will explore real and abstract applications, sometimes with technology, and will enjoy the thrill of mathematical problem solving and generalization.
Mathematics: Applications and interpretation course will be offered at both SL and HL for students who are interested in developing their mathematics for describing our world, modelling and solving practical problems using the power of technology. Students who take Mathematics: Applications and interpretation will be those who enjoy mathematics best when seen in a practical context.
国際バカロレア協会公式HPより
今までGroup5のMathematicsは以下の通りに分けられていました。
- Mathematical Studies SL/HL
- Mathematics SL/HL
- Further Mathematics HL
2019年よりDPを履修する生徒達(2021年卒業見込み)は下の4つのいずれかを選択することになりました。
- Math Analysis and Approaches (SL)
- Math Analysis and Approaches (HL)
- Math Application and Interpretation (SL)
- Math Application and Interpretation (HL)
従来のMath Studies, SLとHLとのリンクは以下の通りというのが初期段階での発表で、今まで通りの学習内容の棲み分けに大きな変更はありません。
| 新Math | 旧Math |
|---|---|
| Math Analysis and Approaches (SL) | Mathematic SL + α |
| Math Analysis and Approaches (HL) | Mathematics HL |
| Math Application and Interpretation (SL) | Math Studies + α |
| Math Application and Interpretation (HL) | Mathematical Studies SL × Mathematics SL |
IB Mathのカリキュラムの変更点
生徒としては
「で、一体何が変わるの?難しくなるの??簡単になるの??学習範囲は変わるの??」ここら辺が気になりますよね。教科書が公表され販売も開始されたので、実際に中身はどうなっているのか、この連載を通してAppication and Interpretation SL/HLとAnalysis and Approaces SL/HLに分けて記載していこうと思います。
まずは、変更事項が最も多かったApplication and InterpretationのHLを見ていきましょう。恐らく、AI HLの受講者は従来で言うMath SLの受講予定者と同じ層となります。
Application and Interpretation HLの変更点
具体的な学習内容ですが、従来のHLの4つのOptional topicsであった「Statistics and Probaiblity」「Sets, Relations and Groups」「Calculus」「Discrete Mathematics」の中からそれぞれ一部がCore Topicsに放り込まれています。
*少々乱暴な言い方をするとSets, Relations and Groupsは無いに等しいです。
Statisticsの分量がだいぶ増え、HL Optionレベルの内容なので、それなりに難易度は高いです。やはり、時代はStatistics推しのようです。
Calculusからは「Differential Equation(微分方程式)」が入ってきます。こちらも同じくOptionでやっていたレベルの問題が入ってくるため難易度が高いものを扱います。
これまでMath SLに無かったものが入ってきますが、ご安心を。内容は浅いです。
「Series Convergence(級数の収束)」や「Power Series/Taylor and Maclaurin Series(関数の多項式近似展開)」など、より難解なトピックスは全てAA HLに突っ込まれています。
Matrix(行列)はSLでは扱っていなかったので新出単元になりますね(IGCSE AddMathなどを履修していた場合はそうではありません)。従来は行列の計算方法のみといったとても簡単な内容でしたが、こちらではもう1,2歩先の内容まで深堀りしています。行列を使った連立方程式から関数の回転、固有値ベクトルまでを扱うので(←これから習うことなので、何のこと言っているかわかからなくても大丈夫です)、こちらは要注意。
Discrete MathematicsからはGraph Theoryが入ってきます。Discrete Mathematicsを履修している生徒は稀なので、恐らく多くの学生も(先生も)要注意です。
全体として、Topicsの量やコンテンツが増えているように見えますが、その反面一つ一つの深さはそこまで深くないと考えられます。
これが生徒にとって吉と出るか凶と出るか。授業を通して数学って凄いな!面白いな!と思う生徒が増えれば良いですね。
私個人としての見解として、今回の変更点で意識しておくべきことは下記の通りです。
- 従来のMath HL optional Topicsがそれぞれ一部入ってきてCoreと合体した
- 全体的に学習す単元が、広く浅くなった
- Statisticsの内容がボリュームとして多め
- 難易度に大きなシフトはない
- paper3は、speeadsheetやgraphing softwareを利用したテストになる
- 文章題中心の問題が増える
- 本質的な理解が求められる(指導者側も)
- IAは書きやすくなる?ネタが豊富に教科書に放り込まれているため
Application and Interpretation SLの変更点
全体的な方向性としては、公表された情報や他サイトでも散見される通り、現実世界での応用を意識した内容へのシフトとなっています。
ですが、やはり学習する本人達からすれば「で?何が変わるの?今まで学校でやっていた数学は意味なかったの??何か準備しなくて大丈夫なんですか??」ということが気になりますよね。
International Baccalauriateによると2018年は下のような履修者数となっているようです。
| Subject | Candidates |
|---|---|
| Further Mathematics HL | 267 |
| Math Studies SL | 36,253 |
| Mathematics HL | 14,841 |
| Mathematics SL | 48,534 |
最も履修者の多いMathematics SLでしたが、新しいカリキュラムとなりどのように分布が変わるかというと、Mathematics SLとMath Studies SLの履修予定であった生徒らがAA SLまたはAI HLを履修することになるということでしょう。
AI SLですが、4つの新Mathの中では、もっともイージーなものになります。ただし、やはりそもそも数字が苦手だったり、数学的思考が弱いとむしろ難しく難解になってしまうかもしれません。
数学的な処理や計算能力よりは、コンセプトの理解を重視する内容となっているので、例えば英語力が低いとそれだけでも勉強が辛くなってしまうかもしれません。周り(友達)が簡単と言っている、という理由だけで選ぶのは辞めましょう。
やはり時代は「Statistics and Probaility」
全体としては、Statisticsの学習内容が大幅に増え、他の部分の細かい要素が削り落とされたといった印象です。正直、学習量としては従来より少なくなり楽になったと個人的には思います。
大きく分ければトピックスは
- Number and Algebra
- Functions
- Geometry and Trigonometry
- Statistics and Probaility
- Calculus
- Exploration
で変化はありません。AI HLの変更と同様にStatistics and Probailityが大きな割合を占めるようになりました。その中でも、χ2-testは新しい。これまではBiology HLで勉強する内容でしたが、統計を学ぶ一環として数学の授業でちゃんと学ぼう、ということでしょう。
また、Voronoi Diagram(ボロノイ図)は新参です。HLでも新しくカバーする内容となっています。ITや様々なネットワークや自然の中の幾何学への応用を意識した内容となっていそうですね。
Trigonometryが激痩せ
その他、これまでの学習内容とはほぼ大きな変化はありません。これまでTrigonometryが4チャプターも使いでカリキュラムが組まれていましたが、こちらが大幅に短くなっています。
別々のチャプターに少しずつ散りばめられており、Trigonometryについて深く学ぶというよりは、Trigonometryを使った「何か」について学ぶという内容にシフトした具合です。圧倒的に計算練習量は少なくなります。
Scienceを意識したMathematics
チャプター1にはMeasurementについて。こちらもChemistryやPhysicsで必ず勉強するSignificant Figures(有効数字)について触れたり、三角比を利用した数学的な測量方法について学びます。今後もScienceとMathの教科としての垣根はどんどん低くなるんだろうな、と改めて実感。
最もスタンダードな現代の数学セットっていう感じですね。代数、幾何、微積、確率と統計が非常にコンパクトに納まっていますので、数学が苦手な子達には優しい内容となっています。