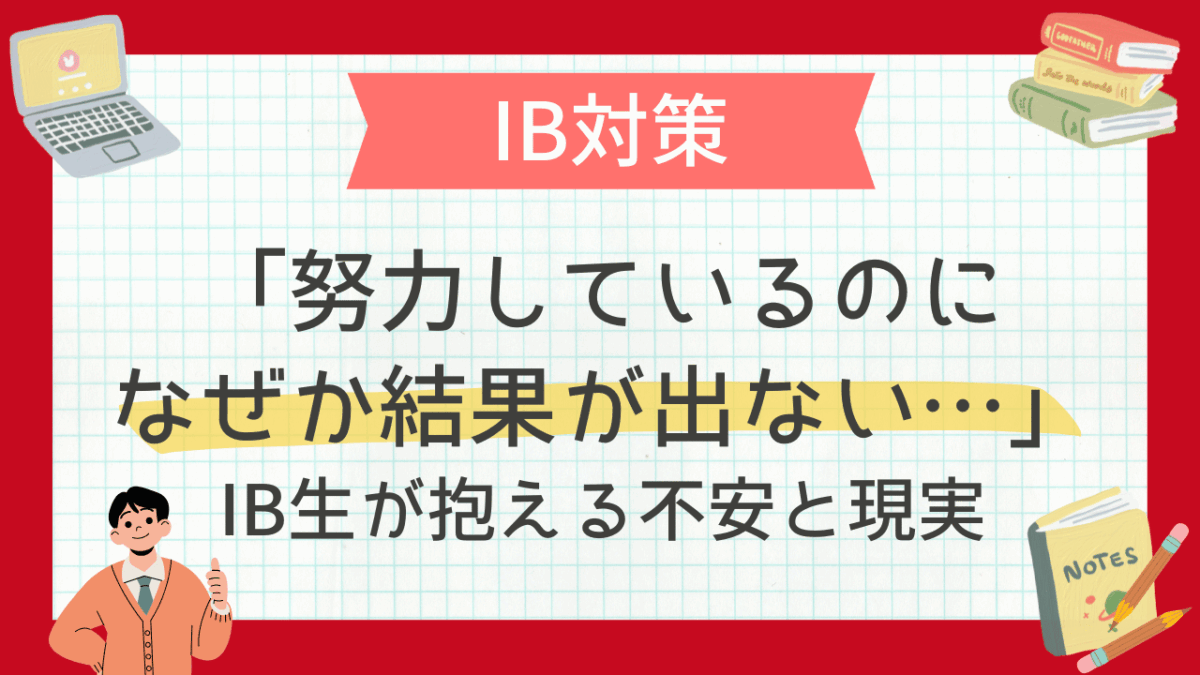「うちの子、毎日しっかり勉強しているはずなのに、模試の結果が伸び悩んでいます」
TCK Workshopに寄せられる保護者様の声には、共通する“もどかしさ”が含まれています。
批判的思考や探究心、協働性などを育み、グローバルな視野を持った人材を育成することを目的としたIB(国際バカロレア)は、単なる知識量ではなく、思考力、表現力、論理構成など総合的な力が問われるため、「暗記が得意な子」や「真面目に取り組む子」が必ずしも高得点を取れるとは限りません。ただ、意外な落とし穴として、「アウトプットが上手」「いかにもIB learnerっぽい子」「批判的思考力が強い子」だからといって高得点が取れるとも限らない。
…結局テストで点数が取れる子でないと、最終スコアは取れないんです。最終成績の80%は最終試験の結果で決まります。IBの理念や思想に魅了されて「こんな学びを経験させたい!」というピュアな気持ちだけで行くと、案外怪我をする、と言う現実があります。
「日本の教育は詰め込み型で…」と口にする保護者が多いですが、これを「詰め込む(知識のインプット)は価値が無い」ような解釈をする人すらいる。教科書を読んだり、暗記したり、資料動画を視聴したり、そういったことを意図的に避けたりする生徒すらいる。
こういう生徒はどうなるか?むしろIBで強調されるアウトプットがスカスカになるんです。インプットサボりのアウトプットなんて大したものにならないのです。体裁だけが良い(プレゼンテーションだけが上手)で中身スカスカで入って来ない。というのが典型です。
少し具体的ま話をすると、英語のエッセイ。文法や語彙がしっかりしていても、分析の深さや論理展開に乏しければ、点数は伸び悩みます。その他科目の記述問題。例えば、Economics、Business、Biology、Chemistryなどで現象や理論の説明をすることが多くあります。ここで的を得た答えができない場合の多くは書くだけの知識の定着が無いことが多いわけです。
特に12年生にとっては、Final Examまでの残された時間との闘いでもあり、「このままで間に合うのか」という焦りが募ります。そんな時、どこに改善の糸口があるのかを見極めるのは非常に難しいものです。
「何を直せばいいのかわからない」そんな親子が選んだ再出発の道
11年生の春からTCK Workshopに通い始めたKさんは、理系科目に強く、特にMath AA HLではIAで高評価を得ていました。それにもかかわらず、模試では5点止まり。お母様も「予習復習もしているし、提出物もきちんと出しているのに、なぜ伸びないのかが分からない」と戸惑いを隠せませんでした。
カウンセリングを通して見えてきたのは、Kさんが「答えは出せるけれど、なぜそうなるのかを説明する力」に欠けていたことです。IAでは十分な準備時間があるため表現力を補えますが、試験本番では限られた時間で構造的に論述する必要があります。
そこでTCK Workshopでは、記述演習と「説明するトレーニング」に特化した指導を行いました。たとえば数式の選択理由を言葉で述べる練習や、英語のエッセイにおける「意図の可視化」など、得点に直結する表現力を徹底的に強化。結果、12年生のFinal ExamではMathもEnglishも6点を超え、第一志望の大学に合格しました。
IBでつまずく3つの落とし穴と、逆転のための戦略とは
原因1:英語力のハンデ
日本一条校でDL (Dual Language)DPを履修する生徒を除けば、ほとんどの生徒がすべての科目を英語で履修をするDPを履修していると思います。この場合どうしても必要なのはそもそもの英語力です。ただここでの英語力とは、Academic ReadingとWritingです。最悪Speakingは上手でなくても勉強習慣があり勉強が得意な子であればちゃんと成績が取れるのです。一番苦労するパターンが、英語は喋れる(日常会話)けど、教科書(学術的な英語)が読めない、ちゃんとしたエッセイが書けない、生徒達です。要するに、IBは高校2,3年生相応の“学力”も査定されてしまうので、勉強ができないと得点は取れません。人柄、パッション、マインドだけではどうにもならないんです。(他のカリキュラムでも当然そうですが)
英語力にハンデがある場合は、日本語で理解を補填したりなどなす術は沢山あります。大学出願の頃には目標とするTOEFLやIELTSの点数があることでしょうから、もちろん英語は日常的に学習することが大切ですが、英語ができる=成績が取れる、ではないことをしっかりと受け入れましょう。英語ができる=勉強の効率が上がる、ことは間違いないです。
また英語を学びたいためにIBにチャレンジするという生徒も見かけますが…これは甚だしくIBスクールの目的とずれているので考え方を改めるべきだと思います。英語を学ぶためのプログラムではありません。語学学校に行った方がよっぽど英語は出来るようになります。
インターナショナルスクールで学ぶIBであれば、英語力は切っても切り離せないほど大事なツールです。英語の学習は終わりが無い反面、今からでもすぐに対策を始めることができるものです。まず何から始めよう…となった場合は迷わずまずは英語を1,2レベル上げるということから始めてみてはいかがでしょうか。
原因2:理解の浅さを“やっている感”でごまかしている
多くのIB生がはまりがちなのが、「読まない」「書かない」という2つの悪習慣です。読むことでのインプットを嫌がり、動画を視聴するだけで済ませる。そして、実際に問題が目の前にあるのに、解かない。書かずに喋る、もしくは「解き方は頭の中では解っているから、もう大丈夫」となる。これでちゃんと成績が取れる人は所謂センス化け物の天才型です。あなたはそうなんですか?相当少数派だと思います。
当たりまえですが上のような生徒はテストになったら全然点数が取れないんです。
スタンフォード大学の教育研究によると、「概念理解をともなう学習」は、知識の保持期間や応用力において暗記型の学習より3倍高い効果をもたらすとされています。まず公式や現象の背景理解を重視し、「知識の意味づけ」を行うことで、記憶の定着と応用力を同時に鍛えることが重要であり、これを達成するには教科書や先生から理論をしっかりと学ぶ必要があります。ちゃんと読み、ちゃんと聞き、ちゃんと書き、定着を促す“努力”をしない限りは概念理解にはなかなか至らないのです。
IGCSEレベルであればやっている感でも難なくクリアしてきた子達でも、DPレベルになると通用しなくなるといことも陥りがちな落とし穴です。中学校までの勉強方法が通用しなくなる、一人ではどうにも理解が難しい、なんてことが起こり始めるのもDPからです。
要は、ちゃんと腰を上げて勉強をしないといけなくなるのが最後の2年間です。
原因3:テスト勉強のやり方をしらない。エッセイや記述で“減点されない書き方”を知らない
IBの採点は主観的評価を避けるため、明確なルーブリックに基づいて行われます。ですから、減点される理由の多くは、「採点基準に沿っていない記述」や「論点のずれた解答」にあります。
特にEnglish AやTheory of Knowledge、Extended Essayでは、「自分の意見」を書いているのに、「評価されない」ことが頻発します。これは“書いているつもり”と“評価される内容”のズレが原因です。
TCK Workshopでは、実際の採点基準を用いて記述指導を行い、「どのように書けば点になるのか」を明示的に伝えています。生徒には必ずルーブリックと照らし合わせながら添削を行い、自分の弱点を自覚して修正できるようサポートしています。
またテストで必要な力とは、「知っていることを短時間で論理的に構造化して伝える力」です。重要なのは、「決められた時間内に」というルールです。IB Learner profileには、ThinkersだとかCommunicatorsだとかKnowledgeableだとか書いてありますが、この3つが素晴らしく長けている場合は、基本的にどんな問題も解く素質があるわけです。が、10分で解けるか?というと、これは全く別のスポーツになるわけです。テストのルール(時間、採点基準)、テストの構成(問いの数と問いの種類)について知らないまま、学校のテストを受けて「頑張っているのにテストで点数が取れないんです…」という生徒があまりにも多い。ということは、学校でこの点について恐らく触れていない。(なぜなら、上記の“スポーツ”の戦い方はIB learner profileではないから)
どうやって点数を取るのかは学校では教わらないんです。(教える必要がない。という理想があるから)*一部の点数にこだわっている学校では、この点の指導も積極的に行っている様子。
オンライン個別レッスンでは、生徒に対して「知識を本番でどう使うか」をトレーニングします。そもそもの知識が無いなら、どの知識をインプットしなければならないか、を教えます。こうすることで、知識とスキルの転移がスムーズになり、試験での再現性が高まります。
IB専門指導だからできる「点を取る力」の育て方
TCK WorkshopのIB対策指導は、単なる家庭教師や個別指導とは一線を画します。IBを専門とする指導陣が、各科目の特徴をふまえた学習設計と指導を行い、「何を」「どの順番で」「どのように学ぶか」を徹底的にマネジメントします。
たとえば、文系科目ではエッセイ構成を骨格から見直し、「結論→根拠→証拠→反論→再主張」のフレームを反復練習します。理系科目では、グラフ解釈やデータ処理の演習を通して、「現象から公式を導き出すプロセス」の訓練を行います。
また、学習の記録とフィードバックを全てデータで管理し、生徒・保護者に可視化して提供するシステムも好評です。「今、何をやっているのか」「どの力が伸びているのか」が見える化されることで、生徒の自信とやる気にもつながります。
実際、12年生のRさんはEnglish Aのエッセイで常に4点前後だったところ、8週間の指導で6点まで到達。お母様からは「内容だけでなく書き方の訓練がこんなに重要だとは思いませんでした」とのお声をいただきました。
「うちの子にも当てはまる」そう感じたら今が動くタイミングです
この記事が特に役立つのは、以下のようなご家庭です。
- IBの各科目で「IAではうまくいったのに試験では結果が出ない」とお悩みの方
- 「努力しているのに成績が伸びない」と感じている生徒
- 11年生や10年生で、「これからどう学べばいいかわからない」と不安を感じている方
「このままでもなんとかなるだろう」と思っていても、IBは本番直前の追い上げが効きにくい試験です。だからこそ、今、動くことが取れる最短の近道になります。
無料相談・体験授業・特別講座。あなたに合った方法で第一歩を
TCK Workshopでは、IB生と保護者様のための無料教育相談を実施しています。現在の状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、最適な学習戦略をご提案いたします。IBに精通した講師陣が、お子様の今の位置とゴールを明確にし、やるべきことを整理します。
また、「まずは授業を体験したい」という方のために、体験授業も随時受付中です。実際の授業の雰囲気や講師との相性を確認いただいたうえで、ご検討いただけます。
悩みを抱えたまま過ごすより、まずは一歩。無料相談・体験授業・特別講座、あなたに合った方法で、一緒にIBの壁を越えていきましょう。