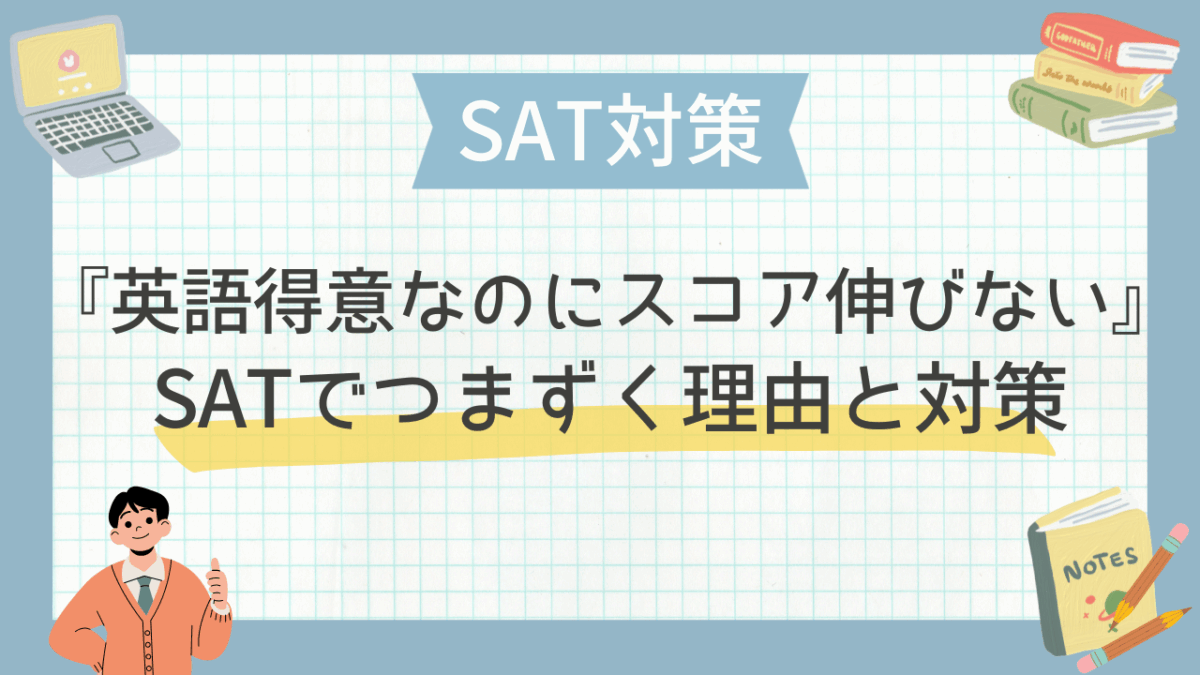帰国子女が初めて直面するSATの壁

「SATって一体何?」
そうつぶやくお子さまの顔を見て、保護者の方は不安が膨らみます。海外現地校では“成績”で語る英語でしたが、大学入試の“試験英語”はまた別物。リーディングの長文問題、数学の数的推理、英作文…これまでの学びの延長では対応しきれません。しかも、2024年以降に始まったデジタル形式では、一度に全部解くことができず、モジュールごとの“順応力”や“適応力”も求められます。
さらに、海外在住やインター校でも採点基準や訓練方法が異なるため、「家でやってる英語とSATの英語は違う」と感じるご家庭も多いでしょう。加えて、帰国後に日本型受験が控えているご家庭にとっては「SATに時間を割くべきか」「国内入試とのバランス」が頭を悩ませます。こうした不安・葛藤が重なり、「SATの準備が不十分」「何から手をつけていいかわからない」状態が続き、結果として模試でも実力を出し切れず伸び悩んでしまうケースが少なくありません。
「せっかく海外で育んだ英語力を活かしたい」「将来の選択肢を広げたい」その一心でSATに挑む帰国子女の多くが、こうした“見えない壁”にぶつかり、望んでいた自分とは異なるスコアに心が折れそうになっています。
【私たちも同じ道を歩んだ】先輩帰国子女の戸惑いストーリー

「英語は得意なはずなのに、なぜSATのリーディングが思うようにいかないんだろう?」
多くの帰国子女が最初に直面するのが、この”得意分野での予想外のつまずき”です。現地校やインターナショナルスクールでは流暢に英語を使いこなしていたのに、SAT形式の長文問題や複雑な文法問題になると、なぜか手が止まってしまう経験は珍しくありません。
特に多いのが「時間配分の感覚が掴めない」という悩みです。普段の授業では時間制限なく丁寧に文章を読めていたのに、SATでは限られた時間内で正確に解答する必要があり、焦りから普段なら理解できる文章も頭に入らなくなってしまいます。
数学分野でも同様の現象が起こります。海外で学んだ数学の知識は十分あるのに、独特な出題形式や英語での数学用語に慣れておらず、「知っているはずの問題が解けない」というもどかしさを感じる生徒が多くいます。また、電卓の使用ルールやデジタル形式の操作に慣れるまで時間がかかり、本来の実力を発揮できないケースも頻繁に見られます。
さらに、帰国後の生活環境の変化や日本の学校制度への適応と並行してSAT対策を進めなければならず、「どこから手をつけていいかわからない」「勉強時間は確保しているのにスコアが思うように伸びない」という声も多く聞かれます。これらは決して個人の能力不足ではなく、SAT特有の形式に慣れていないことが主な原因なのです。
あなたの弱点を劇的に改善するための3大ステップ
以下の3つの柱で、帰国子女のSAT対策を根本から強化します。各ステップには、College Board公式や大学研究報告に基づいた裏付けと具体的手法を取り入れています。
- デジタル形式特有の時間感覚とペース配分を身につける
多くの帰国子女が最初にぶつかる壁が、2024年3月に導入されたDigital SATの特別な形式です。これまでの紙の試験とは違い、読解と数学が各2つのセクションに分かれていて、全体で2時間14分という短い時間での勝負となります。
特に注意したいのが、この「適応型」と呼ばれる仕組みです。最初のセクションでどれだけ正解できたかによって、次のセクションの難しさが変わります。つまり、序盤でつまずくと、後半で挽回するのがとても難しくなってしまうのです。
まず大切なのは、Bluebook公式アプリでの練習に慣れることです。紙の試験とは違い、パソコンの画面で長時間集中したり、スクロールしながら文章を読んだり、画面上でメモを取ったりと、新しいスキルが必要になります。また、最初のセクションで確実に点数を取ることが全体のスコアに大きく影響するため、序盤の問題への集中力と時間配分の練習が欠かせません。
- 読解と文法を組み合わせた総合的な英語力を伸ばす
SATの読解・文法セクションは、普通の英文読解だけでは突破できません。文学・歴史・社会科学・自然科学の4つの分野から出される短い文章(150-750語)に対して、文法・単語・文章の組み立て方・証拠の分析を総合的に判断する力が求められます。
帰国子女が特に苦戦するのが、「文脈から単語の意味を推測する問題」です。日常会話や現地校の授業では問題なく理解できる単語も、SAT形式では「この文章では、この単語はどんな意味で使われている?」という形で出題され、一つの単語が持つ複数の意味を使い分ける必要があります。
また、文法問題でも、英語が母国語の人でも見落としがちな「無駄な表現の削除」や「代名詞が何を指すかの明確さ」「コンマやピリオドの正しい使い方」など、きちんとした文章を書く時に大切な技術的な部分が重視されます。これらは普段の英語使用では意識しない部分なので、帰国子女にとって見落としやすい分野です。
- 数学分野の解き方のパターンと優先順位の判断を身につける
SAT数学は、代数・高度な数学・問題解決とデータ分析・幾何学の4つの分野から構成されますが、帰国子女の多くが「知識はあるのに解けない」状況に陥ります。これは、海外の数学教育とSAT数学の出題の仕方の違いが原因です。
SAT数学では、単純な計算問題よりも、日常生活の状況を数式にして解く応用問題の比重が高くなっています。例えば、「携帯電話プランの最適化」「人口増加の予測」「投資の収益比較」など、数学の知識を現実の問題に応用する力が重視されます。
また、Bluebook搭載の関数電卓(Desmos Graphing Calculator)の上手な使い方も重要な要素です。手で計算すると時間のかかる複雑な計算や、グラフを使った視覚的な理解が必要な問題で、正しい電卓の使用により大幅な時間短縮ができます。ただし、電卓に頼りすぎると逆に時間がかかってしまうため、どの問題で電卓を使うべきかの判断力も同時に養う必要があります。
- やる気を維持し、個人に合った学習計画を立てる
多くの帰国子女が途中で挫折してしまう理由の一つが、「何をどれだけ勉強すればいいかわからない」という迷いです。英語力はあるのにスコアが伸びない状況が続くと、「このまま勉強を続けても意味があるのだろうか」と不安になり、やる気を失ってしまうケースが少なくありません。
大切なのは、現在の自分のレベルを正しく把握し、目標スコアまでの道筋を明確にすることです。どの分野が得意で、どの分野に時間をかけるべきなのか。毎週どれくらいの時間を確保し、どんな順番で学習を進めていけば効率的なのか。こうした個人に合わせた学習戦略があることで、「今日何をすればいいかわからない」という迷いがなくなり、着実にスコアアップへの道を歩むことができます。
また、帰国子女特有の事情(帰国後の環境適応、日本の学校との両立、将来の進路選択など)も考慮した現実的なスケジュール作りが重要です。無理のない計画だからこそ、継続して取り組むことができ、結果として確実な成果につながります。
帰国子女だからこそ活かせるSATでの強みを見つけよう
SATは確かに帰国子女にとって新しい挑戦ですが、これまで海外で培ってきた経験は決して無駄ではありません。むしろ、多様な文化に触れ、異なる環境で学んできた柔軟性や適応力は、SATの多分野にわたる問題に取り組む上で大きな武器となります。
大切なのは、「英語ができるのになぜ?」と自分を責めるのではなく、SAT特有の形式やルールを理解し、それに合わせた対策を着実に進めることです。デジタル形式への慣れ、文脈に応じた語彙の使い分け、応用問題での数学的思考力、そして個人に合った学習計画—これらのステップを一つずつクリアしていけば、必ずスコアアップにつながります。
TCK Workshopでは、同じ道を歩んできた帰国子女の先輩たちが、皆さんの不安や悩みに寄り添いながらサポートします。一人で抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。あなたの海外経験を活かしながら、理想の進路実現に向けて一緒に歩んでいきましょう。