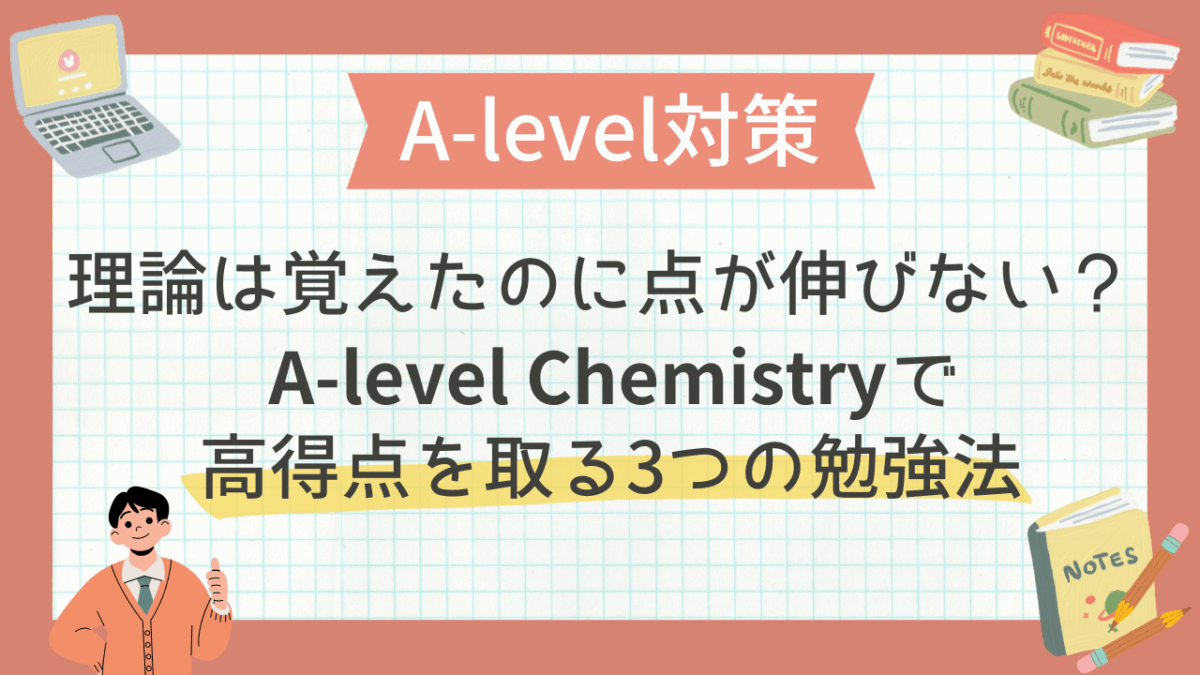「理解したはずなのに点が取れない…」理論重視の落とし穴
A-level Chemistryの学習で、多くの生徒がつまずくのが「理論と計算のバランス」です。

知識はあるのに、なぜか点数が取れない
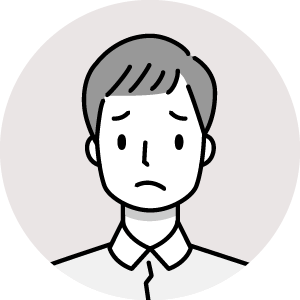
毎回ケアレスミスが減らない

計算問題になると時間が足りない
といった声をよく耳にします。特に海外の現地校やインターで学んでいる生徒にとって、化学は理論暗記と理解を重視する一方で、定期試験やA-level本番では計算の正確さやスピードも同じくらい求められます。知識を丸暗記して安心していたら、本番で歯が立たなかった…という事態も少なくありません。
さらに、A-level ChemistryはGCSEに比べて格段に抽象度が増し、理解すべき概念の数も増えます。「有機化学は反応の流れが覚えきれない」「化学平衡の問題でどこで間違えたのか分からない」など、正解にたどり着けない理由が複雑に絡み合っているのも特徴です。特に計算問題では、ミスを一つすると答え全体が大きくずれてしまい、理論が分かっていても点につながらないというジレンマが生まれます。
A-level Chemistryでは、知識の量だけでなく、それを計算・実践にどう活かすかという視点が問われるのです。
「うちの子もそうでした」暗記中心から抜け出せなかった日々
TCK Workshopに寄せられた相談の中で、特に印象的だったのが、イギリス現地校から帰国し、A-level Chemistryを日本で継続して学んでいた高校2年生・Rくんの事例です。Rくんは有機化学や無機の知識は人一倍あり、過去問も毎週こなしていましたが、模試では毎回同じような点数にとどまり、「なぜ伸びないのか分からない」と自信を失いかけていました。
実は彼の学習は「知識の暗記」に偏っており、反応機構や電子の動きは覚えていても、応用的な問題や実験設計問題には対応できていなかったのです。計算問題も「出たとこ勝負」で、式の意味を深く理解せず、流れを暗記して解いている状態でした。ご家庭でも「こんなに頑張っているのに、なぜ結果がついてこないのか」と悩み、学習の方向性そのものを見直す必要がありました。
TCK Workshopでは彼の弱点を徹底的に分析し、「なぜこの反応が起こるのか」「なぜこの式が成り立つのか」を根本から考える力を育てる指導に切り替えました。その結果、3ヶ月後には過去問の正答率が安定し、有機合成やエネルギー変化の問題でも自信を持って解けるように変化。現在は志望大学の条件に届く見込みが出てきています。
理論と計算のギャップを埋める3つの学習戦略
- 知識を”使える形”で整理すること
A-level Chemistryでは、暗記した知識を単に再現するだけでは不十分です。University of Cambridgeの教育研究でも、“Conceptual Understanding”(概念の理解)が最も成績に影響することが示されています。たとえば化学平衡では、単にLe Chatelierの法則を暗記するのではなく、「なぜその反応が右に進むのか」「温度変化や圧力が何に影響を与えるか」を図や数式でイメージ化し、因果関係として理解することが大切です。
また、有機化学の反応機構も「何が出発物質か」「電子はどこに動くか」を矢印で示しながら解説することで、流れの意味が明確になり、初見の問題でも対応しやすくなります。単なる「情報の記憶」から、「情報の構造化」へと学びの質を高めることが得点力の第一歩です。
- 計算問題は「解法の引き出し」を持つこと
化学の計算問題では、モル濃度、ガスの体積、エネルギー変化、滴定など出題パターンが幅広く、全てを毎回ゼロから考えていては時間が足りません。University of Yorkの理科教育ガイドでは、計算問題に取り組む際は「類型別アプローチ(type-based approach)」が有効であるとされています。つまり、計算問題は必ず典型的なパターンがあり、その型ごとに「この問題ならこの式、この順番」という思考の引き出しを作っておくことが、ケアレスミスや焦りを防ぐ鍵です。
さらに、式をただ暗記するのではなく、「どの単位を変換するのか」「どこで四則計算が必要か」など、プロセスを可視化しながら練習することが重要です。TCK Workshopでは、講師とともにミスを生むポイントを一つ一つ分析し、何度もシミュレーションを繰り返して「計算の型」を身体にしみこませていきます。
- 実験・応用問題で思考力を鍛える
A-level Chemistryでは、知識と計算以外に、実験結果の考察や未知の反応を考える応用問題も多く含まれます。これらは「既知の知識をどう応用するか」「与えられた情報から仮説を立てられるか」が評価ポイントになります。
Imperial College Londonの教育ガイドラインでは、「Active Application of Knowledge(知識の積極的な応用)」が評価の中心にあると明記されており、単なる暗記型では太刀打ちできないことが分かります。たとえば、ある沈殿反応の観察結果から「どんなイオンが反応したのか」「なぜ色が変わったのか」を論理的に説明する必要があります。
このような問題に対応するには、実験問題に触れる回数を増やし、実験ノートやグラフの読み解きに慣れることが効果的です。TCK Workshopでは、過去問に出た実験考察問題をもとに「データをどう読むか」「仮説と一致しているか」などを講師と一緒に訓練することで、思考力を高めるトレーニングを行っています。
「計算が苦手」でも変われた!TCK式サポートの実力
TCK Workshopでは、A-level Chemistryに特化した個別指導を提供しています。特に多いのが、「有機や無機の理論は得意だけれど、計算になると途端に自信をなくす」というご相談。こうした生徒には、まずどの計算でつまずいているかを丁寧に分析し、「理解が浅い箇所」「ミスが出やすいパターン」「時間配分の癖」などを洗い出します。
たとえば、前述のRくんは、毎回モル計算で計算式を途中で見失ってしまう癖がありました。TCKの講師はその原因を「単位換算への理解不足」と特定し、単位変換表の活用や、式を言語化して解説するステップを導入。これにより、問題文の意味を正しく捉え、自信を持って手を動かせるようになりました。
TCK WorkshopにはA-level Chemistryに精通したプロフェッショナル講師が在籍しています。過去問の傾向分析や、各シラバス(AQA, Edexcel, OCRなど)ごとの出題形式にも対応しており、授業では実際の試験を想定した演習とフィードバックを繰り返します。授業の録画も可能なので、復習も万全。
以下のような方はTCK WORKSHOPでの対策がおすすめ
- A-level Chemistryに取り組む中で「理論の知識はあるのに点数が安定しない」「計算問題になると焦ってしまう」「応用問題が手につかない」
- 海外のインターや現地校に通っており、日本でのサポートが受けづらい
- 現在の学校で十分な化学の指導が受けられていない
- 過去問演習をしても成果が見えないと感じている
まずは一歩、無料で試してみませんか?
A-level Chemistryは、単なる暗記科目ではありません。「考える力」「応用する力」「論理を構築する力」も求められる高度な科目です。だからこそ、一人で悩まず、専門家のサポートを受けることで、学びが格段に加速します。
TCK Workshopでは、A-level各教科の専門講師が、シラバス別・スキル別に最適なカリキュラムを提供し、理論も計算も得点につなげる指導を行います。初回は体験授業から始められますので、まずはどのような学び方が合っているのかを確認する絶好の機会です。
また、個別のご相談にも無料で対応しております。「何から始めていいか分からない」「今のやり方で合っているのか不安」など、どんなお悩みでも専門スタッフが丁寧にお答えします。
このまま自己流で悩み続けるよりも、まずは小さな一歩を踏み出してみませんか?体験授業や無料相談を通じて、お子様に最適な化学の学習法を一緒に見つけていきましょう。