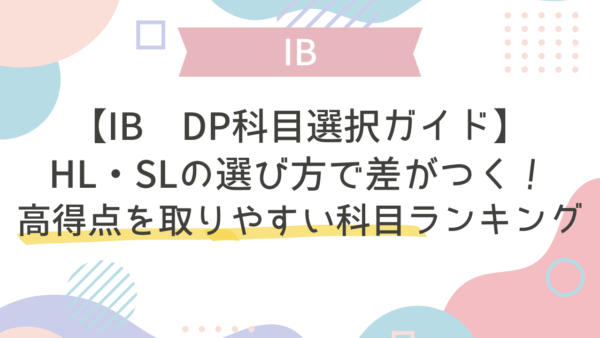はじめに

IB DPで高得点を狙ううえで、科目選択はもっとも重要な第一歩です。どの科目をHLにするか、どこをSLに回すかという判断は、志望する学部や大学だけでなく、最終的なスコアにも直結します。
特に、統計的に「7を取りやすい科目」と「難易度が高くリスクのある科目」ははっきりと分かれています。本記事では、IB公式統計と実際の学習現場の知見を踏まえながら、科目選びのポイントと高得点戦略を解説します。
IB DPの科目選択の基本
IB DPでは、6つの科目とコア要素(TOK・EE・CAS)を履修することが必須とされています。各生徒はGroup1から5までをそれぞれ1科目ずつ選び、Group6についてはアート科目を履修するか、あるいは他のグループの科目で代替することが可能です。
科目はハイヤーレベル(HL)とスタンダードレベル(SL)に分かれており、HLは240時間、SLは150時間の学習時間を前提としています。また、多くの大学や学部では出願条件として「特定科目をHLで履修していること」を求めているため、進路から逆算してHL科目を選ぶことが重要です。
さらに、理系志望の生徒の場合、Group6をアート科目ではなく「ダブルサイエンス」、すなわち化学と物理といった二つの理科科目に置き換える選択が王道とされています。
高得点を取りやすい科目とその特徴
Individuals & Societies(グループ3)
経済学(Economics HL)は、統計的に7の取得率が約15%と高く、安定した得点源になりやすい科目です。教える先生が多く、チューターもつけやすいという点で勉強がしやすい科目と言えます。論理的な文章構成とデータ解釈が得意な生徒には特に向いています。
一方、歴史(History HL)は受験者数が多いにもかかわらず7の取得率が3%未満と低く、英文読解や論述の要求レベルが非常に高いのが特徴です。
心理学(Psychology HL)は人気がある一方で、暗記量と批判的思考力の両方を求められるため、7に到達する生徒は限られています。
Sciences(グループ4)
理系科目では物理(Physics HL)がもっとも7を取りやすい科目とされ、取得率は約20%にのぼります。数学が得意であれば物理の問題形式とも相性が良く、演習の積み重ねで成果を出しやすいでしょう。
化学(Chemistry HL)は物理よりやや取得率が低いですが、概念理解と計算力の両方を養うバランス型の科目です。
生物(Biology HL)は受講者数が多いにもかかわらず、7を取る割合が7%程度と低く、暗記中心の学習では対応できない点に注意が必要です。
しかし、第一は大学で何を学びたいかで科目選択をするべきと言えます。大学出願の際に必要になる科目をしっかりと事前に調べた上での科目選択をしましょう。
Mathematics
数学はAA(Analysis & Approaches)とAI(Applications & Interpretation)の2系統に分かれます。理工系や経済系を志望する場合はAAが主流であり、とくにAA HLは7の取得率が15%弱と比較的高めです。データ分析や応用を重視する場合はAIを選ぶケースもありますが、大学の出願条件に合わせて慎重に判断する必要があります。
失敗しやすい選択パターン
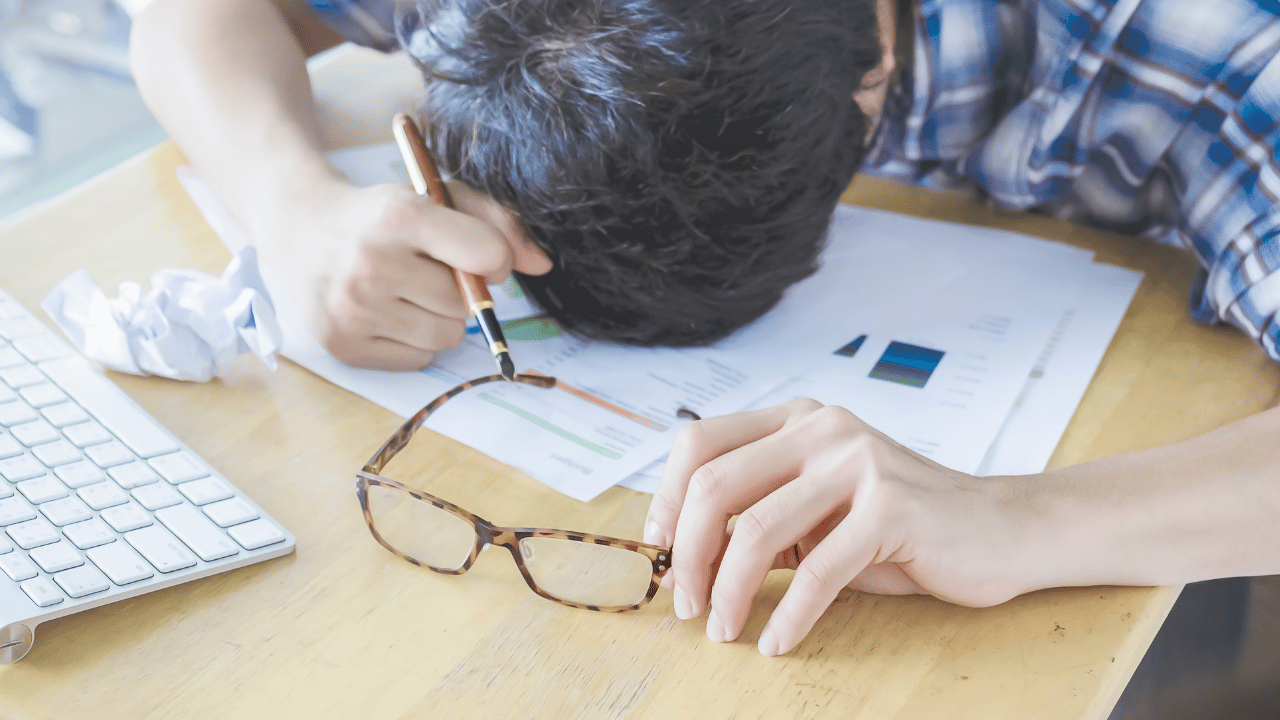
科目選択では、「好きだから」「得意だから」といった理由だけでHLを選んでしまうと、想定以上の負担になりやすいです。たとえば歴史HLを「英語が得意だから大丈夫」と安易に選ぶと、史料読解や論述の負荷が想像以上に重く、結果としてスコアが伸び悩むことがあります。
また、志望学部に必要なHL科目を見落とすと、大学出願時に要件を満たせず、出願そのものが制限されてしまいます。
さらに、IA(Internal Assessment)の準備にかかる時間を軽視すると、授業・試験対策と並行できずにスコアを落とす原因となります。
高得点を実現するための戦略

- まず最初に、志望進路に必要なHL科目を明確にしましょう。たとえば工学系ならPhysics HLとMath AA HLが安全な組み合わせとなります。
- 次に、統計的に7の取得率が高い科目を「得点源」として配置するのが効果的です。文系であればEconomics HL、理系であればPhysics HLを軸に置くことで、スコアを安定させることができます。
また、IAは早期にテーマを決めて準備を進めることが不可欠です。特に理系科目のIAでは実験の設計からデータ処理、考察までに時間がかかるため、学期序盤から逆算して取り組む必要があります。文系科目ではエッセイ構成を定型化し、データや事例を効果的に挿入する練習を重ねることで、得点を確実に伸ばせます。
さらに、TOKやEEといったコア科目との連動も意識しましょう。たとえばEEで経済学を選ぶ場合、データ分析スキルや因果関係の議論がTOKの論文でも役立ちます。
このように、学習を科目横断的に結び付けることで、合計点を底上げできます。
モデルプラン(志望分野別)
- 理工系志望の生徒には、Physics HL・Math AA HL・Chemistry HLの組み合わせが最も堅実です。
- 経済・経営系を目指す場合はEconomics HLを中心に、Math AAをHLまたはSLで選び、さらにGeographyやBusinessを加えると良いでしょう。
- 生命科学や医学部志望ならChemistry HLとBiology HLを軸に、Math AAを組み合わせることで大学出願要件を満たしやすくなります。
まとめ
IB DPの科目選択は「志望進路」「統計データに基づく得点の取りやすさ」「IAやコア科目との連動」を三本柱として考えるのが鉄則です。
経済学や物理のように統計的に7を取りやすい科目を得点源に据え、負担の大きい科目はSLでバランスを取ることが賢明です。学校の開講状況や指導環境によっても差が出るため、外部の指導や補習を組み合わせながら、自分に最適なプランを構築しましょう。
TCK Workshopのサポートについて
IB DPの科目選択や学習戦略は、進路や得意不得意によって大きく変わります。そのため、早い段階から専門的なアドバイスを受けることが成功の近道です。TCK Workshopでは、帰国生・海外在住生に特化した個別指導を行っており、IB科目別の対策からIAやEEの指導、さらには英検・TOEFL・SATなどの資格試験対策まで一貫してサポートしています。
「自分に合った科目選択が分からない」「高得点を狙いたいけれど勉強の方向性に不安がある」という方は、まず無料の教育相談をご活用ください。
専門カウンセラーが一人ひとりの状況に合わせたプランを提案し、安心してIB DPに取り組める環境を整えます!
関連記事
- IB Economics対策|エッセイとデータ解釈で差をつける【帰国子女向け】
- IB Physicsで6 or 7を取る子の秘密:公式理解と実験対応を両立させた勉強法とは
- IB Math AAとAI、違いがわかる!知っておきたい5つのチェックポイント
- IB Biologyで成績が伸びない3つの理由とその突破法とは?
- IB Internal Assessment(IA)で差をつける!科目別テーマ選定のポイントと事例