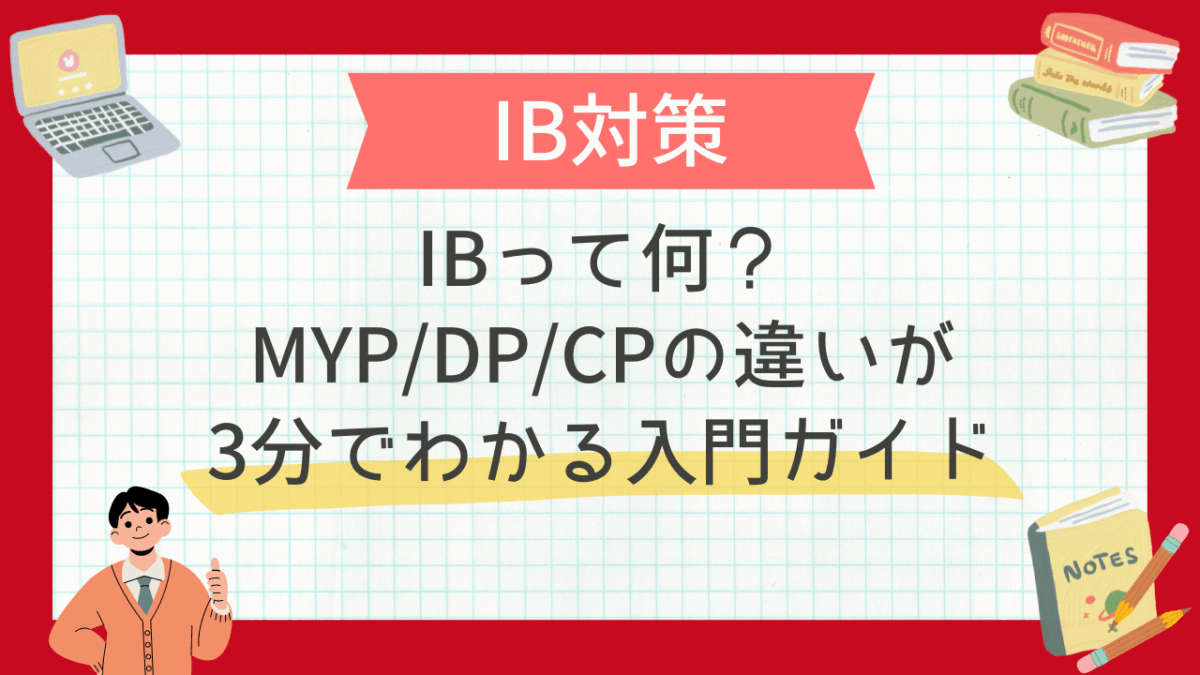最初に戸惑う3つのギモン:IBってなに?何が違うの?どう備える?

「国際バカロレア(IB)って、最近よく聞くけど結局どんな仕組み?」

「MYP?DP?CP?いろいろあって混乱する…」
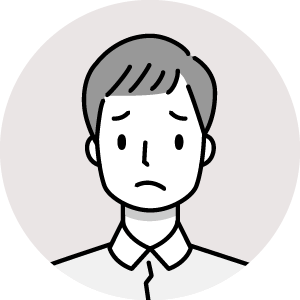
「インター校を検討しているけれど、英語力が足りるのか不安」
――こうした声は、これからIB教育に関わろうとする保護者様から本当によく聞かれます。
特に日本にお住まいで、これから海外やインターナショナルスクールに進学予定のお子様をお持ちのご家庭では、IBという言葉は知っていても、その中身については曖昧なままのことが多いです。学校説明会では用語が多くて話についていけなかった、という声も珍しくありません。
また、IBの学びは「英語が話せる=大丈夫」ではなく、「探究力」「論理的思考力」「自律性」など、独特のアカデミックスキルが求められます。これらは従来の日本の教育や補習校の学習とは大きく異なる部分であり、特に日本語環境で育ったお子様にとっては、最初の1年が壁になることも。
「うちの子、本当についていけるのかしら?」という不安は、IBの本質を知れば知るほど大きくなっていくものです。だからこそ、学ぶ前に「MYP/DP/CP」の違いや全体像、そして準備の方向性を明確に理解しておくことが非常に重要なのです。
IBとは何か?MYP・DP・CPの違いを完全解説
IBとは——グローバルスタンダードの教育理念
IB(International Baccalaureate)はスイスの非営利教育機関が開発・運営する教育プログラムで、「知識・思考・国際理解・自律的学習者の育成」を目的に設計されています。対象年齢に応じて4つのプログラム(PYP, MYP, DP, CP)に分かれ、日本では主に中高生対象のMYP・DP・CPが注目されています。
MYP(Middle Years Programme)——学びの“骨格”をつくる5年間
MYPは11歳〜16歳(日本の中1〜高1相当)を対象とし、学問的知識とスキルを統合するカリキュラムです。特徴的な3つの要素を詳しくご紹介します:
- 教科横断型の学習(Interdisciplinary Learning): MYPでは複数教科を横断する学びが奨励されています。例えば、「水資源の持続可能性」というテーマを通じて、理科では水の循環を学び、地理では国別の使用状況を比較し、英語ではその内容を論述するエッセイを作成する——このように、教科をまたいで1つのテーマに取り組むことで、知識を現実世界と結びつける力を養います。
- Criterion A〜Dに基づくルーブリック評価: 各教科には4つの評価基準(Criterion A:知識と理解、B:探究と分析、C:コミュニケーション、D:思考力の応用)が設定されており、点数ではなく記述式ルーブリックによって成績がつけられます。つまり「何ができて、何が課題か」を明確にする“育成型評価”が中心。これにより、単なる結果よりも学びの過程が重視されます。
- グローバルコンテキストとATL(Approaches to Learning): MYPの単元は必ず「Global Context(グローバルな視点)」のいずれかに紐づいており、たとえば「公平性と発展」や「時間・場所・空間」などを切り口に思考を深めます。またATLでは、調査力・自己管理力・協働力・批判的思考力など“学び方を学ぶスキル”を体系的に育成。これらは将来DPで求められるエッセイ・プレゼン・プロジェクトを支える土台となります。
DP(Diploma Programme)——IBの集大成となる2年間
DPは16歳〜19歳(高2〜高3相当)を対象とする大学進学直結型プログラムです。6教科(Language and Literature, Language Acquisition, Individuals & Societies, Sciences, Mathematics, The Arts)と、以下のコア3要素で構成されます:
- TOK(Theory of Knowledge):知識とは何かを問い続けるメタ認知科目
- EE(Extended Essay):4000字の学術論文を通してリサーチ力と論証力を鍛える
- CAS(Creativity, Activity, Service):課外活動を通じた人間的成長
DPとMYPの最大の違いは、評価がより厳格で国際的な大学出願に直接関わる点にあります。MYPでは「プロセスの中で育つ姿勢」が重視されていたのに対し、DPでは「成果としての思考・分析・表現力」が本格的に求められます。
また、DPでは学習内容そのものも高度化し、エッセイは常に論拠を必要とし、複数の視点から物事を分析する力が前提とされます。TOKでは哲学的な思考とディスカッションが要求され、EEではテーマ選定・リサーチ・論証・引用までを一人で完遂する力が求められます。
必要とされるスキルには、学術的な英文読解力、クリティカル・シンキング、論理構成力、タイムマネジメント、そして何より「自分で考え、学ぶ主体性」が挙げられます。
そのため、DPは単に「成績優秀な生徒」向けではなく、「問い続ける姿勢」を持つ学習者にこそ向いているプログラムだと言えるでしょう。
最終的には各教科7点+コア3点の計45点で評価され、世界中の大学がこの資格を認定。IB Diploma取得はグローバル大学進学のパスポートとも言える資格です。
CP(Career-related Programme)——職業志向のIBモデル
CPは16歳〜19歳対象で、DPよりも実践的かつキャリア寄りに設計されたプログラムです。特定分野(例:ビジネス、観光、アート、ICTなど)に特化した職業教育と、DP科目の一部+IB独自のキャリア科目(Personal and Professional Skillsなど)を組み合わせた構造となっています。専門大学やポリテクニック志望者に最適なルートで、実務的な学びを深めたい生徒向きです。
違いの整理:MYP・DP・CPは何がどう違う?
| プログラム | 対象年齢 | 主な目的 | 評価方法 | 進路への影響 |
| MYP | 11〜16歳 | 学び方と探究姿勢の育成 | ルーブリック(A〜D) | DPに進む基礎力構築 |
| DP | 16〜19歳 | 大学進学準備・思考力の集大成 | 最終試験+内申(7×6+コア3) | 海外/国内大学出願資格 |
| CP | 16〜19歳 | 職業志向・実践的スキルの習得 | 専門科目+DP+キャリア科目 | 専門大学・キャリア系進学 |
「何から手をつけていいか分からなかった」IBに戸惑う家庭のリアル
実際にTCK Workshopへご相談いただいたN様(中1・男子)は、海外赴任を機に日本の中学からインターナショナルスクールへ転校されました。学校はMYPカリキュラムを導入していましたが、当初は「何を、どのように、どこまでやればいいのか全く見当がつかない」とお母様は語ります。
「教科書がなく、毎回プロジェクトやプレゼン、エッセイばかりで…日本の勉強とは全然違う」「ルーブリックやクライテリアって何?と思うことばかり」――授業はすべて英語、評価方法も新しく、親としても不安が尽きなかったそうです。
また別の事例では、高1でDPに入ったお子様が「英語は日常会話なら問題なかったが、学術的な文章を書く力がまったく足りずに苦労した」と話していました。CASやEE(Extended Essay)、TOK(Theory of Knowledge)など、日本の教育では馴染みのない要素にも戸惑う声は多くあります。
こうした混乱や悩みは、実はIBを始める前に「構造」や「目的」「評価方法」を知っておくことで大きく軽減できます。そして何より、正しい準備とサポートによって、IBの魅力を最大限に活かせるようになるのです。
まずは無料相談で、お子様に合ったIB対策を見つけてみませんか?
IBは学びのあり方そのものが大きく異なる教育プログラムです。そのため、「いまの学習スタイルで本当に通用するのか」「うちの子にMYPやDPは向いているのか」と不安を抱えるのは当然のことです。
TCK WORKSHOPでは、IBに精通した専門スタッフが一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを提供する「無料学習相談」を実施しています。学年や通学予定校、現在の英語力に応じた準備の進め方など、具体的なご相談が可能です。
IB特有の学びへの備えは、早ければ早いほど効果的です。MYPやDPの導入前に、一歩先の視点で準備を始めてみませんか?