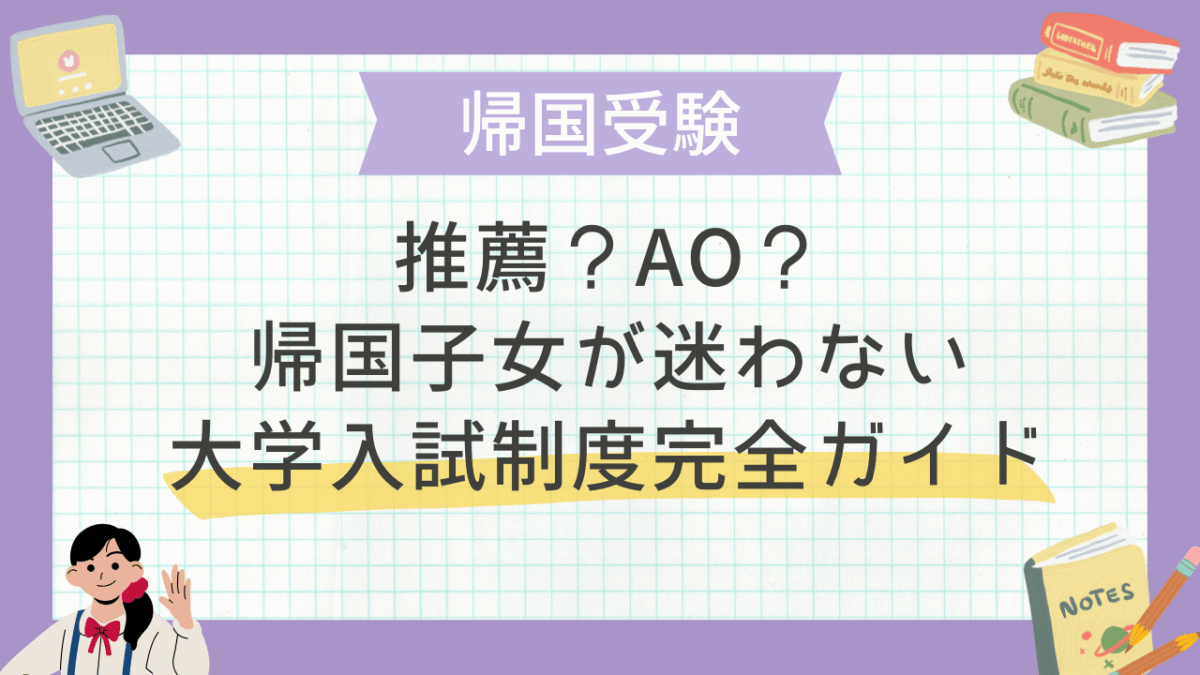「どの制度がうちに合う?」あふれる情報にとまどうあなたへ
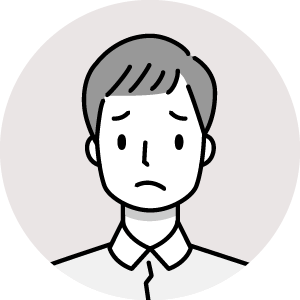
「何をいつまでに準備すればいいの?」
日本の大学入試では、帰国子女枠・学校推薦型選抜・総合型選抜(AO)など、海外在学経験を評価する制度が年々多様化しています。「一般入試より楽」と思って詳細を見れば、英語資格や書類、面接のハードルに唖然。例えばICUの総合型選抜〈帰国生〉はIELTS/TOEFLで英語力を証明しつつ、日本語の面接で批判的思考を測る二段構えです。また慶應SFCのAOはSAT・IB・ACTから1種類を選び、スコア提出と長文エッセイが必須となります。大学ごとに期限も評価基準も異なるため「何をいつまでに準備すればいいの?」と途方に暮れるご家庭が少なくありません。さらに2025年度以降は、慶應文学部・商学部などが帰国生募集を停止し、選択肢が狭まる一方で倍率は上昇傾向にあります。こうした制度変更は毎年のように起こるため、「最新情報を追えず、準備が後手に回る」という声が多数寄せられています。
「自分ごと化」できた瞬間に動き出す
Yさん(香港在住・高3)は、TOEFL iBT102点とGPA3.9を持ちながら、志望理由書の構成に悩みAOを敬遠していました。TCK Workshopの無料相談で、ICU〈帰国生総合型〉では学科試験がなく書類と面接が重視される点を再確認し、TOEFLを活かしつつ日本語自己PRを磨く作戦に変更。専属講師とのオンライン指導で、エッセイを3週間で4稿ブラッシュアップし、面接リハーサルを計5回実施。結果、10月出願から12月合格まで2カ月で勝負を決めました。
一方、Mさん(米国在住・高2)は早稲田SILS志望。AOと帰国枠の両方を視野にSATと英語エッセイを準備するも方向性が定まらず、親子ともに疲弊。講師の提案で「帰国枠(Type-A)」一本に絞り、SAT1300目標を維持しつつ志望理由書を夏休みに完成。9月締切に余裕を持って提出し、1月の合格通知を受け取りました。
どちらのケースも「制度を正しく理解し、不要な準備を捨てた」ことで家族のストレスが激減したと語っています。
大学が何を見ているか——3つの鍵で制度を攻略
1. 評価軸を“入試タイプ×大学”でマトリクス化
推薦・AO・帰国枠は大きく「学力型」「総合評価型」「語学特化型」の3種に分けられます。学力型(慶應経済タイプBなど)はSAT/IB/評定平均がコア評価。総合評価型(慶應SFC AO、ICU帰国総合型)はエッセイと面接が主、学力は基礎点扱い。語学特化型(早大SILS AO)はTOEFL/IELTSが足切り。志望校を縦軸、評価軸を横軸にしたシートを作ると「英語力は足りているが学力が不足」「書類が強みになる」など優先課題が一目瞭然になります。
2. 書類は“体験→学び→志望動機”の三層構造で書く
慶應AOやICUでは、海外経験が単なるエピソード披露に留まると評価が伸びません。エッセイでは「(体験)国籍を越えたチームで地域課題を解決→(学び)多文化協働の難しさを認識→(志望動機)国際関係学で制度設計を学びたい」の三層で論旨を展開することで、面接質問にも一貫性が生まれます。TCKでは“WHY-CHANGE-HOW”フレームワークを用い、2時間で骨子→24時間以内に講師が添削→48時間以内にリライト指示を返すサイクルで、平均3稿で完成ラインへ到達します。
個別最適化×丁寧なPDCA——TCK Workshopの推薦・AO対策
TCK Workshopでは、まず専任カウンセラーが志望校リストと評価軸を整理し、「何を削るか」から逆算したロードマップを提示。エッセイ指導ではネイティブ&日本語バイリンガル講師が共著体制を採用し、語学と構成を同時に磨きます。面接対策は出願校の過去傾向を分析した質問集を使用し、1回30分の短期集中リハを最大5回までセット。2025年度入試では、推薦・AO利用の85家庭のうち78%が第一志望合格、うちICU帰国総合型は合格率92%(全国平均34%)を記録。保護者アンケートでは「書類と面接を同じ講師が見る一貫性」「返却スピードの速さ」が満足度90%以上でした。
一歩踏み出すなら今—無料相談と体験授業で大学受験のロードマップを
まずは無料教育相談で出願カレンダーと現状スコアを棚卸しし、「何を出すか/何を捨てるか」を明確にしましょう。方向性が決まったら、体験授業でエッセイ添削や面接リハの手法を体感し、講師との相性を確認できます。
今日、公式サイトのフォームから無料相談を予約することで、進路選択の迷いが未来志向の行動へ変わるはずです。