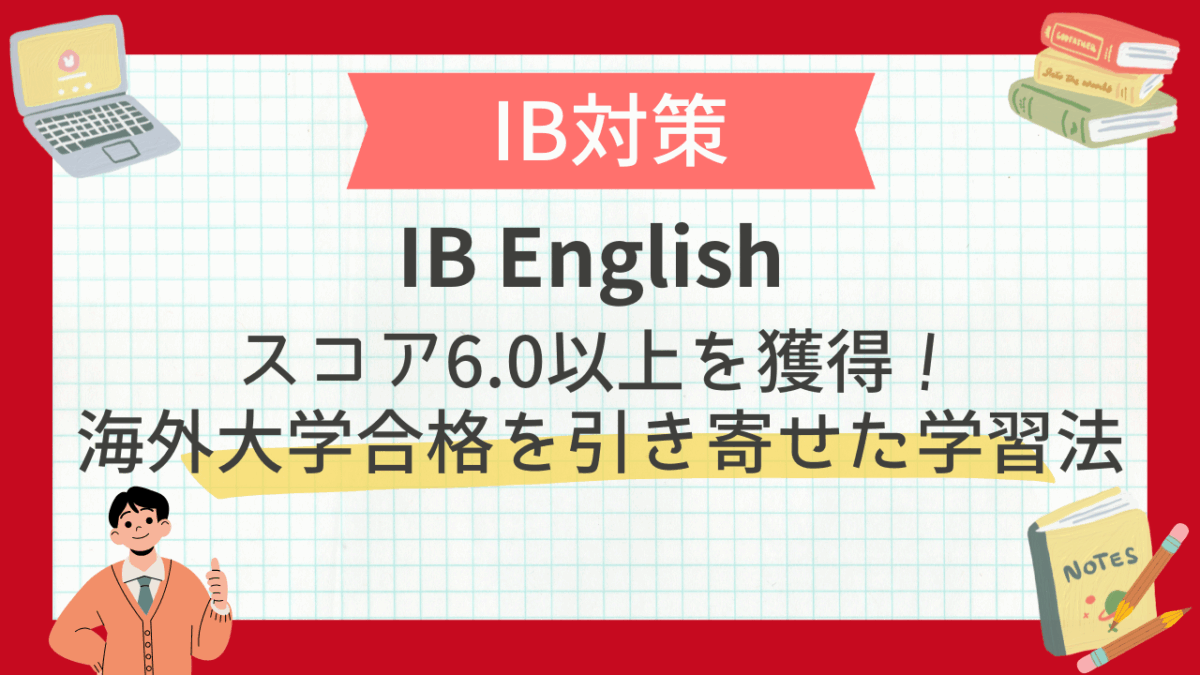「これで安心」海外大学合格へIBスコアが伸び悩む原因とは?
帰国生受験を控える小中高生と保護者の皆様にとって、IB(国際バカロレア)のスコアは将来の進路を左右する重大な要素です。

IAで高評価だったのに試験本番で得点が伸びない…
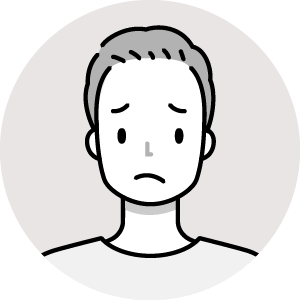
英語が得意なはずなのにHL英語のペーパー1や2でスコアが振るわない
といった声を耳にすることが増えています。特に、IBは知識の深さだけでなく英語で論理的に表現する力が問われるため、「海外現地校では順調だったのに、日本帰国後に急に壁にぶつかった」というお子様も少なくありません。その背景には、科目によって求められる思考方法の違い、評価基準の理解不足、そして時間配分の難しさなど複数の課題が存在します。
さらに、「海外大学に向けてIBスコアを安定的に取れているか不安」「志望校の基準にあと0.5点足りない」といったご家庭も多く、試験直前になるほど学習計画が空回りし、試験本番で本来の力が発揮できないケースも見られます。これらの悩みは他人事ではなく、「まさにわが子の現状だ」と感じられている方も多いのではないでしょうか。
「あの時、もうダメかと思った」先輩生徒のリアルストーリー
例えば、帰国子女の生徒Aさん(高校2年・海外現地校歴5年)は、IAで高評価を得ながらも、SL English Paper 2では常に5点前後の安定しない結果に悩んでいました。保護者様も「授業には追いついているのに、エッセイは書けているのに、なぜスコアに結びつかないんだろう…」と授業ごとに不安な表情だったそうです。Aさんは特に、IBの評価基準である“Criterion C: Organisation and Language”の観点がつかめず、論旨の流れや英語表現で点を落としていました。
同時期、志望する海外大学ではIBスコアが少なくとも5.5以上求められていましたが、彼女は5.0前後で停滞。模試は合格ラインに届かず、親御様も「海外大学は無理かもしれない」と落胆していたといいます。しかし、Aさんは学習法を見直し、最終的には6.0以上を獲得し、志望大学に見事合格を果たしました。その変化には、ご家族全体で「正しく対策したい」という共通の思いがあったのも大きな推進力になっていたようです。
「なぜ?」から「どうする?」へ導く!IBスコアが伸びる3大戦略
- 評価基準とのギャップを埋める「基準対応型フィードバック」
IB英語では、単に英語が話せたり書けたりするだけでは高得点が取れません。評価は、IBの国際基準「IB Marking Criteria(IBの採点基準)」に沿って行われており、「文章の構成は明確か」「語彙の使い方は豊かか」「文法の正確さはどうか」など、細かい項目でスコアがつけられます。特にエッセイで評価されるCriterion C(文章表現)では、自然なつなぎ言葉(トランジション)、的確な単語選び、ミスのない文法などが大きなカギになります。
つまり、「とりあえず書いてみた」や「テンプレートを使った」だけでは、点数が伸びにくいのがIB英語の特徴です。
TCK Workshopでは、IB公式の評価ポイントに沿って、生徒が書いたエッセイを講師が丁寧に添削します。例えば、「主題の導入が不明確」「アイディアのつながりがぎこちない」「接続語が単調」といった細かい点を、Criterion別に具体的にフィードバックします。何を直せばスコアが上がるのかが目に見えるので、生徒自身が改善点を理解しやすく、自分の力で書き直せるようになります。
実際に指導を受けたAさんも、「どうして自分の書き方がIB基準に合っていなかったのか」が明確になり、自信を持って修正に取り組めるようになりました。
- 論理構成力を鍛える「逆算型ライティング演習」
IB英語では、英語力だけでなく「論理的に文章を構成する力」も非常に重視されます。どんなに英語が上手でも、主張と根拠が整理されていなかったり、段落のつながりが弱かったりすると、高評価にはつながりません。
この「論理構成力」を鍛えるには、自分の文章を後から振り返って分析する“逆算型”の練習が効果的です。アメリカのハーバード大学の研究でも、自分の文章を「構成図」に分解して見直すことで、論理の流れや構造が明確になり、文章力が上がると報告されています。
TCK Workshopでは、この逆算型の学習法を取り入れ、IBで高得点を取った模範エッセイを「なぜこの順番で段落が書かれているのか」「どのように意見をつなげているのか」といった観点から一緒に分析していきます。また、自分のエッセイについても「主張は明確か」「例は適切か」「結論につながっているか」などを講師と一緒にチェックしていきます。
Aさんはこのプロセスを通じて、自分の書いた内容を客観的に見直せるようになり、文章の流れがより論理的に整うようになりました。結果として、構成ミスが減り、IBの評価基準に合ったエッセイが書けるようになったのです。
- 多読×要約×表現転換で「英語表現力」を根底強化
IB英語では、「読んで理解する力」だけでなく、「自分の言葉で要約する力」や「表現を言い換える力(パラフレーズ力)」も問われます。これは、ただ単語を覚えるだけでは身につきません。
アメリカ・ペンシルベニア大学の研究では、たくさんの英文を読みながら、内容を自分の言葉でまとめる練習を続けると、語彙力と文法理解が飛躍的に伸びるとされています。
TCK Workshopでは、IBレベルに合った英語記事や過去問題の資料を使い、「指定文字数でまとめる→自分の言葉で書き直す」という訓練を行います。これにより、「読んだ内容を要約する力」や「自分の表現で言い換える力」が自然と身についていきます。
このトレーニングを続けたAさんは、語彙の定着が進み、複雑な文構造もスムーズに使いこなせるようになり、リーディングとライティングのスコアが0.5〜1.0ポイントも上がるという成果を出しました。
「本気で合格したい人にこそ」TCK WorkshopのIB対策が選ばれる理由
TCK WorkshopのIB対策プログラムは、単なる「たくさん解く」学習ではなく、生徒一人ひとりに寄り添った個別最適化が特徴です。多くの講師が帰国子女または海外経験者で、英語ネイティブレベルの言語運用力を備えております。
まず無料相談で現状分析を行い、その後、評価基準と受験目的に合わせた学習プランが立案されます。Aさんの場合、まず模範答案から逆算する逆構成の演習を重視したカリキュラムが構築され、週1回の模範答案解説、週2回のパラフレーズ演習、月1回の模擬試験+振り返りセッションが続きました。
その結果、開始から4ヵ月でIB HL Englishのペーパーが平均5.0→6.0に向上し、最終的には6.5を獲得し志望大学に合格されました。
「こんな方にこそ力になれます」対象者の具体像
特に、以下のような状況のお子様とそのご家庭には、TCK WorkshopのIB対策が非常に適していると考えられます。
- 英語の基礎力は充分にあるものの、Criterion別採点基準や思考構造への意識が乏しく、模擬試験でも「あと0.5~1点届かない」パターンに苦しんでいる方
- SLやHL問わずEssayやWritten responseなど英語で論理的に書く作業に自信がない方
- 海外現地校に通っていたものの、帰国して日本語教育とのギャップに戸惑っている方
このような方にとって、単なる塾ではなく、IB評価基準に精通した講師とともに「今の課題を明確にし、スコアに直結する対策」が取れる環境は、大きな安心と期待につながるでしょう。
「まずは一歩から」安心して始められるTCK WORKSHOPのサポート
まずは、無料教育相談へのお申込みをご検討ください。現状の課題を講師が丁寧にヒアリングし、必要な改善ポイントや学習スケジュールの方向性を示してくれます。「今のままでは試験本番でどこでつまずくか不安」と感じる方にとって、プロの目による分析は大きな指針となるでしょう。
次に、体験授業では実際にAさんと同じような逆構成演習やCriterion別フィードバックを受けていただけます。体験だからこそ、「自分に合うかどうか」「どの程度伸びそうか」を肌で感じる良い機会となります。
「このまま悩み続けるより、まずはプロの視点で課題を整理してほしい」「短期間で確実にスコアを伸ばしたい」とお考えの方には、無料相談・体験授業のいずれも有効です。まずは一歩、まずは相談から。安心と自信を手に、一緒に合格への道を歩み始めませんか。