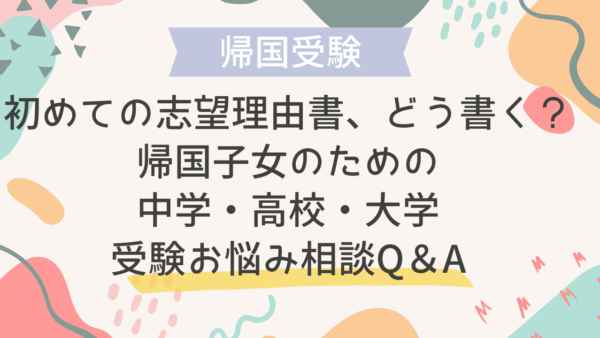帰国子女受験で増える「志望理由書」の重要性
帰国子女の中学・高校受験では、筆記試験に加えて志望理由書の提出を求められる学校が増えています。特にICU高校、学芸大附属国際、同志社国際などの人気校では、志望理由書が合否を大きく左右するケースも。
とはいえ、多くのご家庭で出る悩みは共通しています。

そもそも何を書けばいいの?
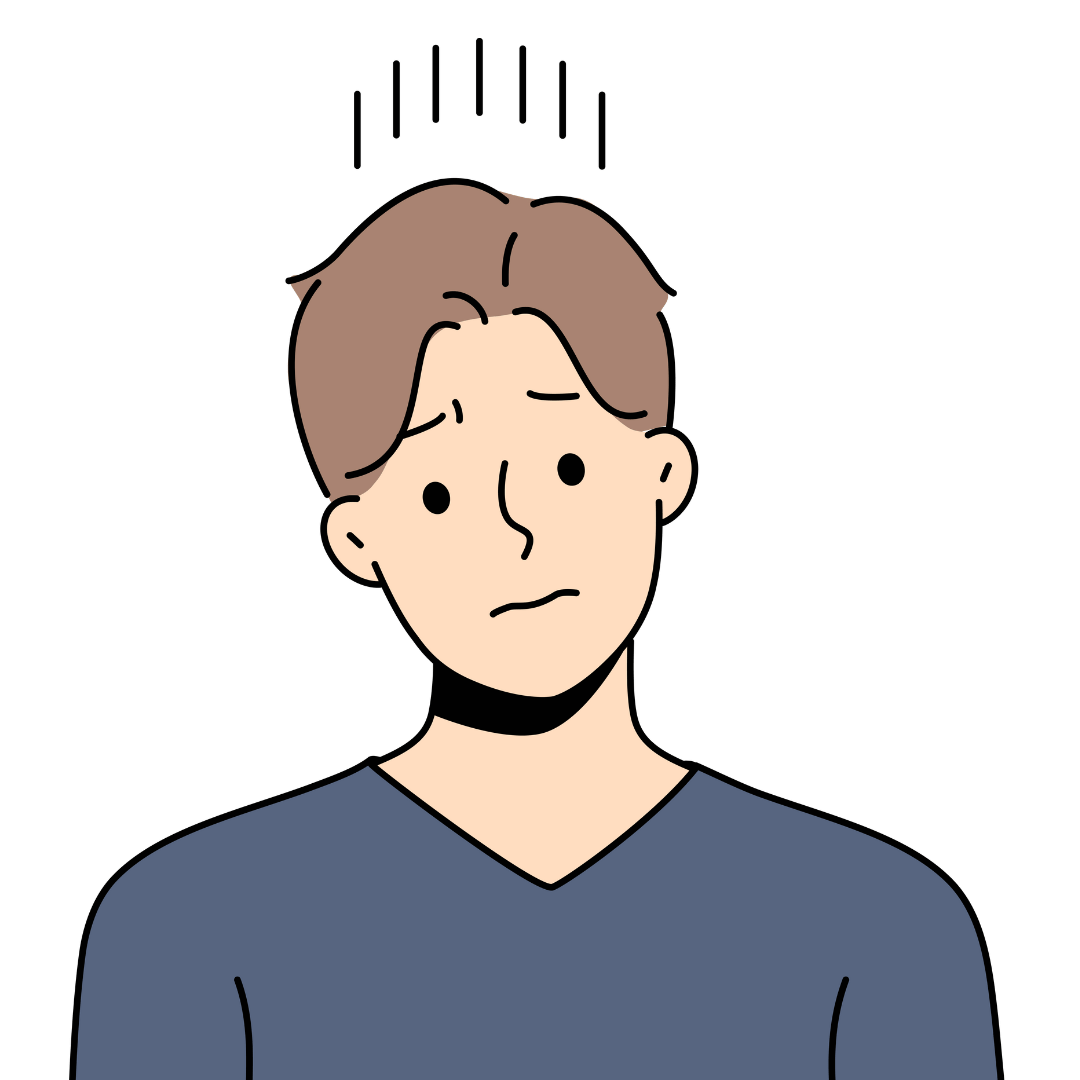
活動実績が少ないけど大丈夫?
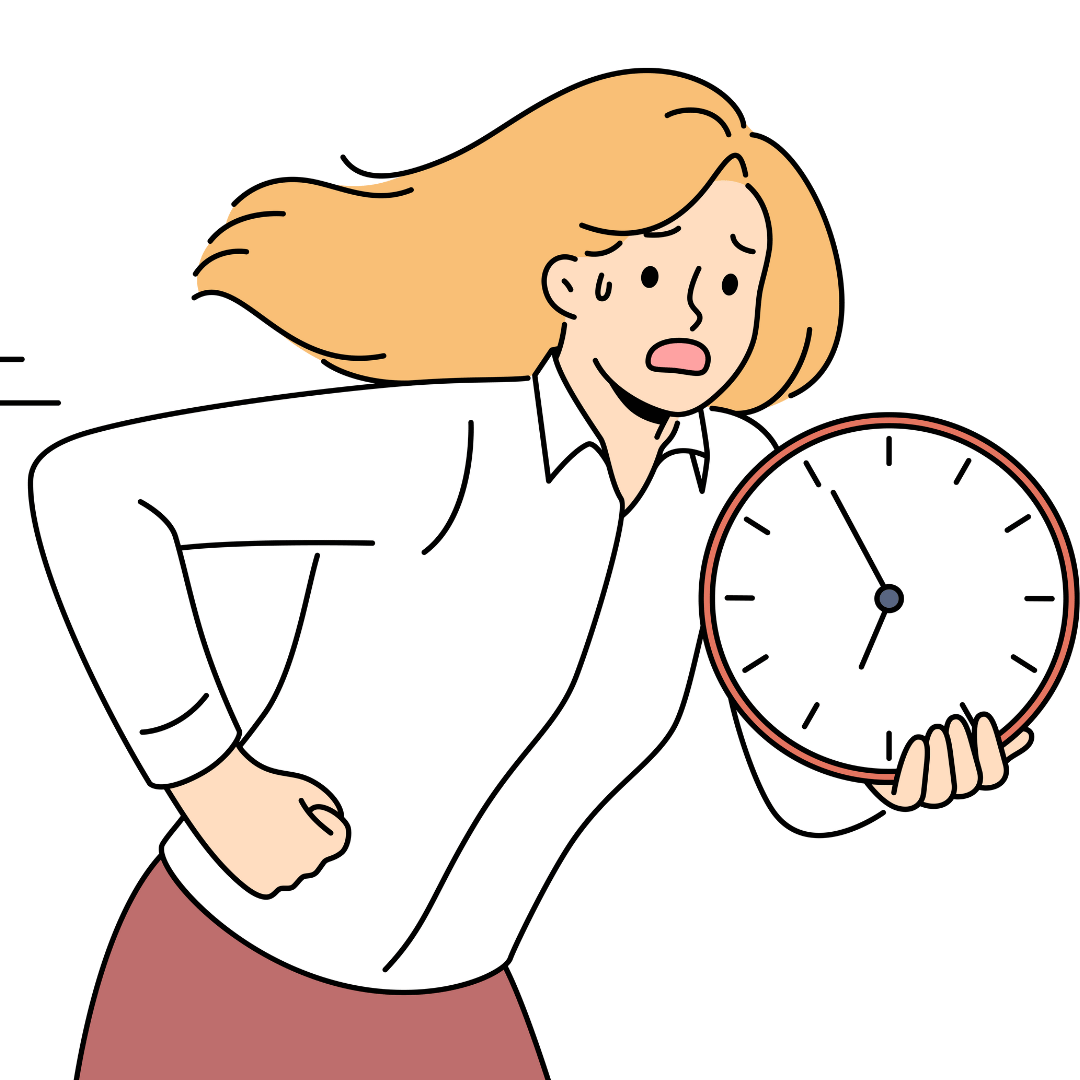
いつから準備すればいいの?
この記事では、TCK Workshopの受験指導の現場で実際によく寄せられるご相談をQandA形式で紹介しながら、帰国子女のための志望理由書の書き方を丁寧に解説していきます。
Q1:実績がないけど、何を書けばいい?
A:日常の経験や「続けてきたこと」を丁寧に掘り下げましょう。
帰国生は、日本のように資格や受賞歴が明文化されていない場合も多く、「アピールすることがない」と悩みがちです。しかし、学校側が見ているのは実績よりも人となり・継続力・興味関心です。
たとえば、以下のようなものも立派な題材になります:
- 数年間続けた習い事(ピアノ、バレエ、スポーツなど)
- 家族での取り組み(マラソン、読書、地域清掃など)
- 授業での特別クラス(上級クラス、プロジェクト型授業)
さらに、「なぜそれに打ち込んだのか」「そこから何を学んだのか」を言語化することで、他の受験生と差がつく志望理由書になります。
Q2:志望理由書って、いつから準備すればいいの?
A:遅くとも出願の3~4か月前。余裕があれば1年前から「材料集め」を。
実際の執筆に入るのは3~4か月前が一般的ですが、「ネタになる経験探し」や「自己分析」は早いほど有利です。特に以下のような準備を夏休み中から始めておくと、秋以降が楽になります:
- 学校の説明会・文化祭への参加
- 自分の経験を振り返るワーク(ブレストや日記など)
- 現時点で将来やりたいことについて明確に考える
👉 受験準備のスケジュールを具体的に把握したい方はこちら:帰国子女の中学受験スケジュール|いつ何をすべきか?
👉 同志社国際を志望している中学生の方はこちら:帰国子女枠で同志社国際を狙う中学生へ|合格に導く3つの秘訣とは?
Q3:学校のことはどうやって調べるの?HP以外に何がある?
A:現地訪問・SNS・在校生の発信など、リアルな情報がカギ。
学校のホームページは出願情報を得るうえで重要ですが、「その学校らしさ」をつかむには以下も活用しましょう:
- 文化祭や学校説明会(可能なら一時帰国時に)
- 在校生・卒業生のSNSやブログ(部活やイベントの様子)
- TCK Workshopの受講生の合格体験談
👉 志望校選びの視野を広げたい方はこちら:帰国子女に選ばれている大学は?国内大学TOP10を徹底比較!
Q4:志望理由書で差がつく書き方って?
A:自己PR+学校の特色+将来像=一貫したストーリーが重要です。
TCK Workshopの指導では、以下の構成で書くことを勧めています:
- 自分の経験・価値観の紹介(自己PR)
- 学校の魅力と、なぜそこを選んだか(共感)
- 入学後どう学び、将来にどうつなげたいか(展望)
この3つを矛盾なくつなぐことで、説得力のある「志望理由」になります。
👉 面接対策も含めて全体像を知っておきたい方はこちら:高校帰国子女受験|面接で何を聞かれるの?志望理由書は何を書けばいい?
👉 推薦・AO入試に向けて書類全体を見直したい方はこちら:帰国子女 大学受験|帰国子女が使える推薦・AO入試制度まとめ
Q5:親と子で意見が分かれたらどうする?
A:すり合わせは大事。でも最終判断は「本人の熱量」で。
志望理由書には「その学校に行きたい」という熱意がにじみ出る必要があります。親の意見を参考にしつつも、書くのは本人。そのため、以下のような対話が効果的です:
- 親:「こんな経験も書けるよね」
- 子:「でも自分はこの部分に一番力を入れたから、そこを強調したい」
👉 面接や志望理由書に向けて親子で話し合いたい方はこちら:帰国生の面接対策、何から始める?プロが教える効果的アプローチと注意点
志望理由書は「正解がない」からこそ、向き合う価値がある
志望理由書の作成は、受験のためだけでなく、
“自分の過去を振り返り、これからの進路を考える時間”
でもあります。
TCK Workshopでは、生徒自身の言葉を引き出すブレインストーミングや添削サポートを通じて、自分らしい志望理由書作りを徹底サポートしています。