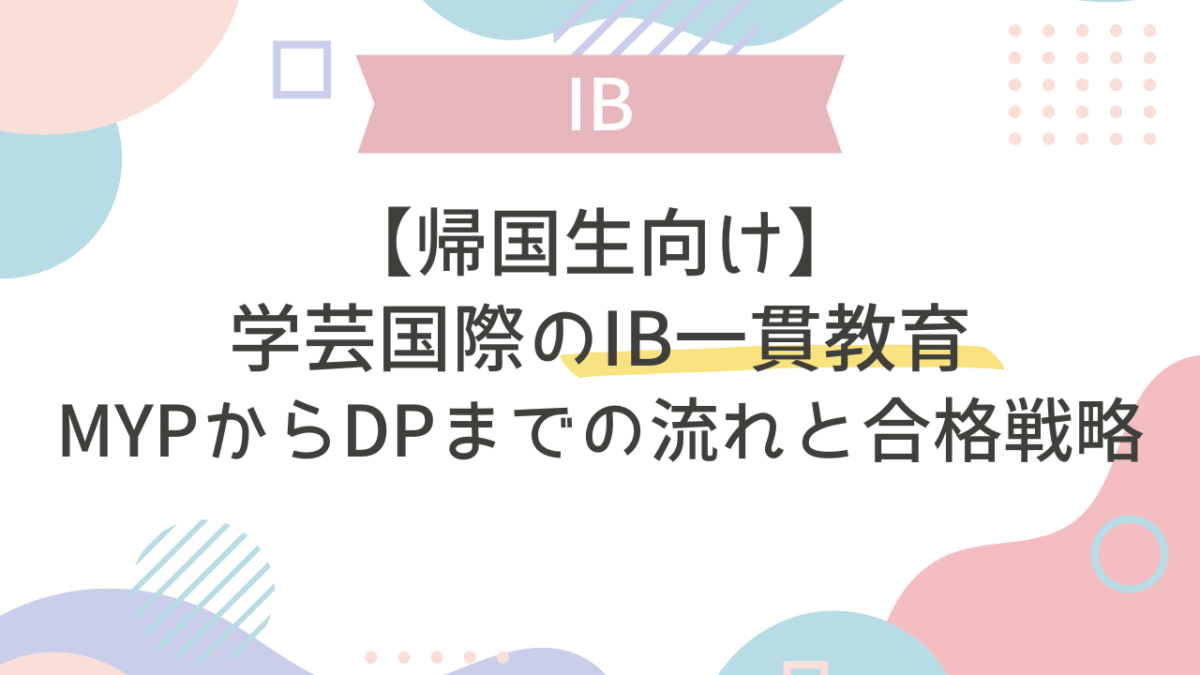はじめに
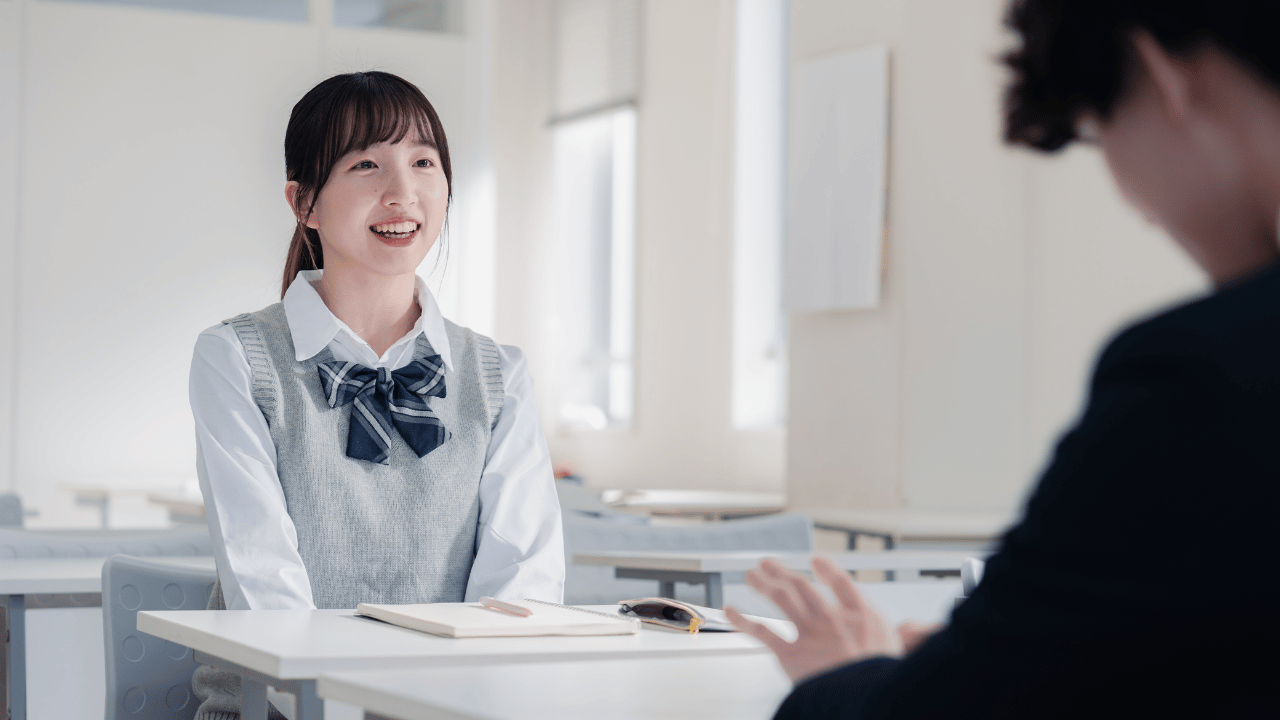
「日本でIBを一貫して学べる“国公立”の選択肢はあるのか?」——これは帰国直後のご家庭から特に多く寄せられる質問です。東京学芸大学附属国際中等教育学校(通称:学芸国際/TGUISS)は、その答えの一つとなる存在です。
同校では中学1年から高校3年に相当する6年間を通して、前期課程でMYP、後期課程でDPを学ぶことができ、国公立学校としては数少ないIB一貫校の一つです。授業は日本語中心で行われながら、必要に応じて英語やその他の言語が取り入れられ、帰国生へのJSLサポートも充実しています。
本記事では、MYPからDPまでの学びの流れ、入試制度の仕組み、進路実績、そして合格をつかむための戦略を詳しく解説していきます。
学芸国際の全体像:MYPとDPをつなぐ一貫教育
学芸国際の最大の特徴は、IB教育をMYPとDPで連続的に経験できる点です。
学習場でのギャップを埋められるMYP
中学1年から高校1年にあたる4年間では、MYPの枠組みの中で日本の学習指導要領に沿った科目を日本語で学びます。国語や社会、理科や数学、美術や音楽といった幅広い科目群を、探究的なアプローチと結びつけて学ぶことができます。この期間に日本語で学ぶことにより、帰国後に生じやすい学習上のギャップをスムーズに埋められるのが利点です。さらに、日本語が第二言語となる生徒に対しては、JSL(Japanese as a Second Language)の支援が提供されており、基礎的な日本語から教科日本語までを段階的に強化していく仕組みがあります。
専門的で国際的な学びに移行するDP
高校2年から始まるDPでは、より専門的で国際的な学びへと移行します。科目によって使用言語が異なるのが学芸国際の特徴であり、例えば歴史は日本語で、数学や一部の理科科目は英語で行われることがあります。生徒は英語と日本語を行き来しながら知識を積み重ね、最終的に世界標準の評価体系であるIBディプロマを取得することができます。
卒業後の進路
卒業生の進学先は国内外に広がっており、東京大学や一橋大学をはじめとする国内難関大学だけでなく、アメリカやイギリスなどの有名大学へも進学実績があります。国内と海外のどちらも選べる進路の幅広さは、学芸国際の大きな強みです。
入試制度:A方式とB方式の違いと準備のポイント
学芸国際の入試はA方式とB方式に分かれています。
帰国生に有利なA方式
A方式は帰国生にとって最も利用されやすい選択肢であり、外国語作文、基礎日本語作文、集団討論形式の面接、そして書類審査で評価されます。特に外国語作文は英語だけでなく、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、韓国語から選択可能であり、多言語に対応している点は国内でも珍しい特徴です。集団討論は日本語で行われ、自分の意見を論理的に伝える力と同時に、協調性や傾聴姿勢も評価対象になります。
配点:作文100(外国語85+基礎日本語15)+面接50+書類100=計250。
国内生が主に受験するB方式
一方、B方式は国内生が主に受験する方式で、実世界のさまざまな場面において、数理的思考を問う適性検査Ⅰと、社会問題を資料から読み取り自らの考えを表現する適性検査Ⅱを中心に実施されます。どちらの方式を選択するにしても、面接と書類審査は共通しており、総合的な人間性と学習姿勢が見られることを意識する必要があります。
適性検査Ⅰ:(理数的・科学的思考)50点+適性検査Ⅱ(社会課題の資料読み取りと表現)50点+面接50点+書類100点=計250。
学芸国際では毎年必ず4月と9月の年2回、入学試験と編入試験も実施しているため、タイミングに応じて入学のチャンスを得ることが可能です。
合格戦略:作文・面接・日本語強化をどう進めるか

合格を勝ち取るためには、それぞれの試験で求められる能力を的確に鍛える必要があります。
外国語作文では、言語的な正確さよりも、論理の一貫性や説得力ある構成が評価されるため、テーマを決めて短時間で文章を組み立てる練習を重ねることが大切です。基礎日本語作文は配点こそ15点と少なめですが、合否を左右する微差を生む可能性があります。限られた字数の中で明確に意見を述べる訓練を怠ってはいけません。さらに、日本語を母語としない帰国生の場合、日本語での面接や討論に備え、日常的に日本語での議論や要約を練習しておくとよいでしょう。
集団討論型の面接では、自分の意見を述べる力だけでなく、他者の意見を要約したり対話を通じて合意を形成する姿勢が求められます。議論の中で「まとめ役」や「バランスを取る役割」を果たせると、評価が高まりやすい傾向にあります。
B方式を選ぶ場合には、資料を短時間で分析し、自分の言葉で再構成する練習が不可欠です。過去のテーマを参考にしながら、因果関係を意識した整理と結論の提示を繰り返すことで力がついていきます。
入学後に求められる適応力と伸びしろ
合格はあくまでスタートラインであり、入学後はMYPからDPへの学びの移行に備える必要があります。
MYP段階では探究型学習を日本語で行い、日本語の学力基盤を整えることが第一歩となります。その後DPに進むと、英語で授業を受ける科目が増えるため、科目ごとに言語を切り替えて理解できるスキルが必要です。
また、Extended Essay(EE)、Theory of Knowledge(TOK)、Creativity, Activity, Service(CAS)といったDP特有の課題も待ち受けています。これらをこなすには、早い段階からテーマ選びや時間管理を意識して取り組む姿勢が欠かせません。こうした学びの積み重ねが、国内外の難関大学へと進学する大きな力になっているのです。
まとめと次のステップ

学芸国際を理解するための3つの要点(概要)
- IB一貫体制:2010年にMYP認定、2015年にDP認定。国公立としてMYPとDPの一貫実施を行う希少校。
- 授業と言語:前期課程(第1〜4学年=中1〜高1相当)でMYP×日本の学習指導要領の統合。多くの授業は日本語で実施しつつ、イマージョンや一部DP科目で英語等を活用。JSLサポートも整備。
- 入試の実情:A方式とB方式を実施しており、A方式の外国語作文は英・仏・独・西・中・韓/朝から選択。集団討論型の面接が特色。入学・編入試験は原則4月・9月の年2回実施。
学芸国際は、帰国生にとって「日本語と英語の両方で学びを深められる」数少ないIB一貫校です。MYPでは日本語中心の授業を通じて基盤を整え、DPでは国際的な評価に直結する学びへと進んでいきます。卒業後の進路も国内外のトップ大学へ広がっており、学びの成果を進学にしっかりとつなげられる環境が整っています。入試制度は多言語作文や集団討論といったユニークな要素を含み、準備には専門的なサポートが必要になることも少なくありません。
TCK Workshopのサポートで合格力を強化
TCK Workshopでは、学芸国際の入試に対応した作文指導、面接対策のプログラムを提供しています。帰国直後で日本語に不安を感じるご家庭や、学芸国際独自の試験形式悩む受験生にとって、専門的なサポートは合格への大きな後押しになります。
まずは無料相談や体験授業を通じて、お子様の現状に合った最適な学習プランを一緒に考えてみませんか。
関連記事
学芸国際やIB教育についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。