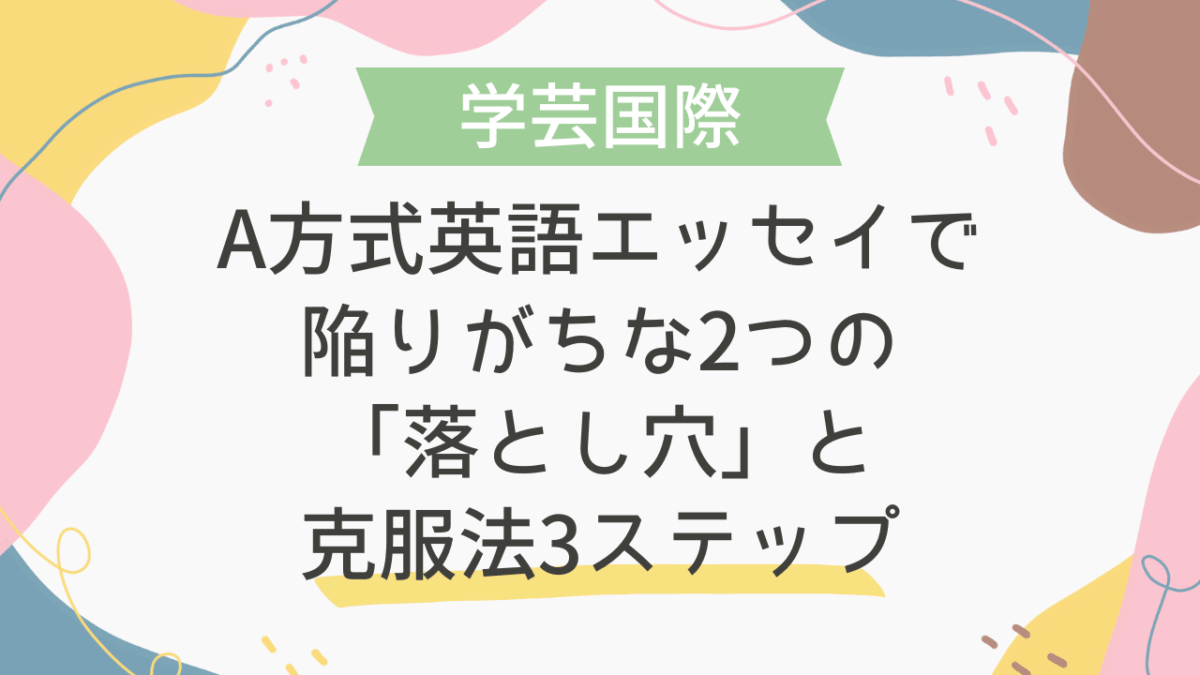配点が高い学芸国際A方式の英語エッセイ
海外での生活が長く、英語力に自信のある帰国子女にとって、東京学芸大学附属国際中等教育学校(学芸国際)は、その国際的な教育環境から志望度の高い学校の一つでしょう。しかし、学芸国際の入試、特にA方式で課される外国語作文(英語エッセイ)は、単なる英語力だけでなく、論理的な思考力と多角的な視点を問われるため、十分な準備が不可欠です。

英語は得意なのに、なぜかエッセイの点数が伸びない

社会的なテーマにどう論理的にアプローチすれば良いかわからない
このような悩みを抱える受験生は少なくありません。
この記事では、学芸国際の外国語作文で求められる本質的なスキルと、それを磨き上げるための具体的な対策法を、元学芸国際出身の講師の知見も交えて徹底的に解説します。単に「書き方」を知るだけでなく、「合格に必要な思考力」を身につけるための具体的なステップを理解し、自信を持って入試に臨むための道筋を見つけましょう。
英語力だけでは不十分?学芸国際の外国語作文で多くの帰国生が直面する壁

東京学芸大学附属国際中等教育学校の選抜検査(A方式および編入学)のうち、外国語作文(多くは英語エッセイを選択)は、合否を分ける重要なポイントとなります。
制限時間45分で「Persuasive Essay」を書き上げる
外国語作文は、制限時間45分で課題文を読み、それに対する意見をPersuasive Essay(説得的な論述文)として構成し、書き上げる形式が特徴です。これは、自分の意見を論理的かつ客観的に主張する力が求められるもので、短時間で高い論理性と構成力(推奨される5段落構成)を示す必要があります。
過去問テーマに見る「社会的な視野」の重要性
過去の出題テーマを見ると、「白川郷のリースの是非」「ドネーションの是非」「学校の特定授業の外部委託」など、汎用性があり多様な視点で考えられる社会的なテーマが多いことがわかります。これらのテーマは「YesかNoか」がはっきりしない、多面的な議論が可能なトピックです。表面的な理解ではなく、問題の深層や、異なる立場からの影響まで踏み込んで考察できるかが問われています。
帰国生が陥りやすい2つの「落とし穴」
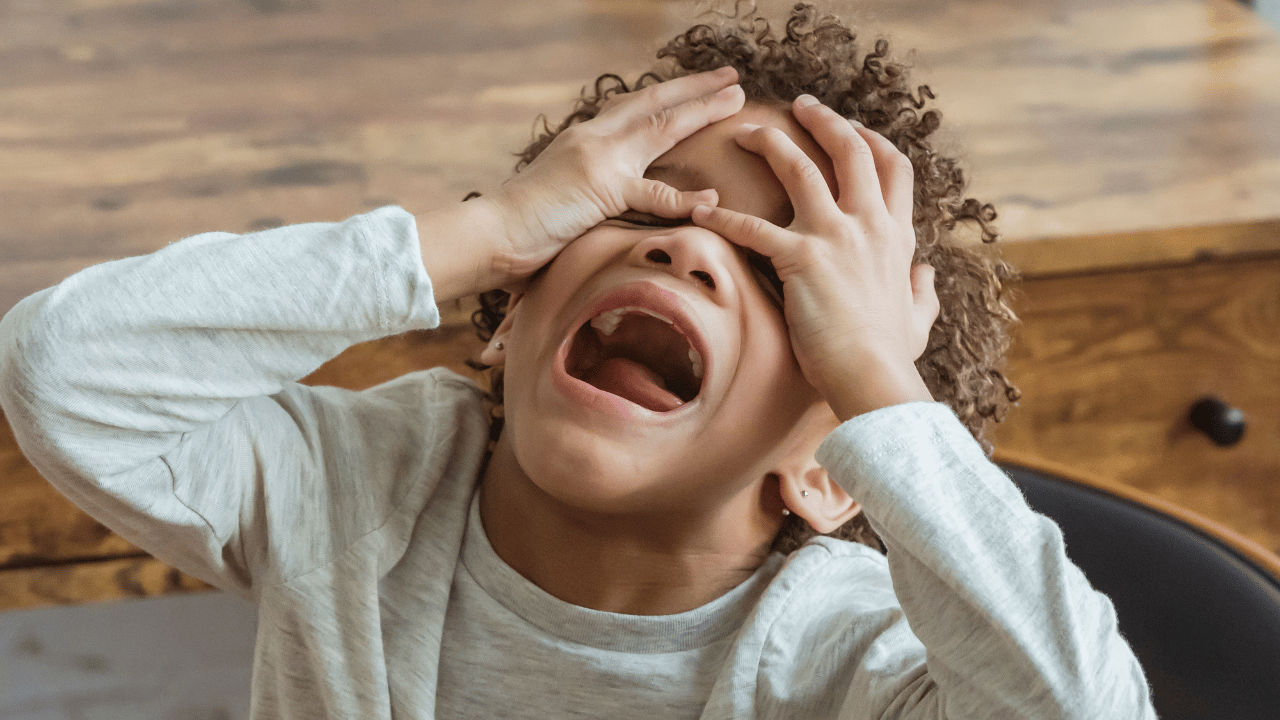
TCKの講師が指摘する特に帰国生が点数を落としがちなのは、以下の2点です。
立場が同じ視点からしか考えられていない
例えば「学校の授業の外部委託」というテーマに対し、生徒自身の視点のみで終わってしまい、教師、外部委託団体、親、社会全体といった多角的な視点からのメリット・デメリットを論じることができないケースです。
具体例が書けない
一般論や抽象的な主張を繰り返すだけで、主張を裏付ける具体的な事例や詳細な説明が欠けてしまうケースです。抽象的なアドバイスで止まってしまい、「具体的にどんなアドバイスで、どのように成長するのか」という詳細な描写(ズームイン)ができないと、説得力に欠けます。学芸国際の評価基準にも「具体と抽象のバランス」が重視されるという記載があります。
この二つの壁を乗り越えることこそが、学芸国際の英語エッセイで合格を勝ち取るための鍵となります。
合格を勝ち取る思考法:学芸国際A方式「英語エッセイ」対策を徹底解説
学芸国際の外国語作文で高得点を取るためには、単なる英作文の技術ではなく、論理的な思考プロセスと多角的な視点を構築する訓練が必要です。ここでは、エッセイの質を劇的に向上させるための具体的な戦略と実践ステップを解説します。
1. 複数の「立場」から問題を捉える「多角的な視点」の養成法
学芸国際の英語エッセイが最も重視するのは、多角的な視点(Multiple Perspectives)から問題を分析する能力です。
「賛成・反対」以外の「第三者の視点」を洗い出す
テーマが与えられたら、「賛成(Pro)」と「反対(Con)」に加えて第三者の視点を明確に定義し、それぞれの立場からの意見を論理的に展開します。
テーマが「ドネーションの是非」の場合のステークホルダーの例:
- 明確な対立する二者
- ドナー(寄付者): 心理的満足度、節税(→メリット)
- レシーバー(受領者): 必要な支援(→メリット)、自立の妨げ(→デメリット)
- 第三者の視点:
- 仲介・運営団体: 資源配分の効率化(→メリット)、運営コスト(→デメリット)。
- 経済・環境: 廃棄物削減(→メリット)、新品市場への影響(→デメリット)。
本論の3つのボディパラグラフを、それぞれ異なる立場からのメリット・デメリット、あるいは課題と解決策に割り当てることで、深みのある多角的な論述が可能となります。特に上級学年の入試では、この「視野の広さ」が強く評価されます。
日常的な「ニュースの登場人物」の立場深掘り訓練
この多角的な視点を磨くため、日頃からニュースを見る際、「その出来事に関わるすべての人」の立場を想像してみましょう。例えば、紛争のニュースを見た際には、当事国の市民、周辺国の市民、国際機関の職員、遠い国の子供たちなど、様々な立場からの「利益」と「不利益」を考える訓練をします。
2. 説得力を高める「具体的な事例」の書き方とズームインの技術
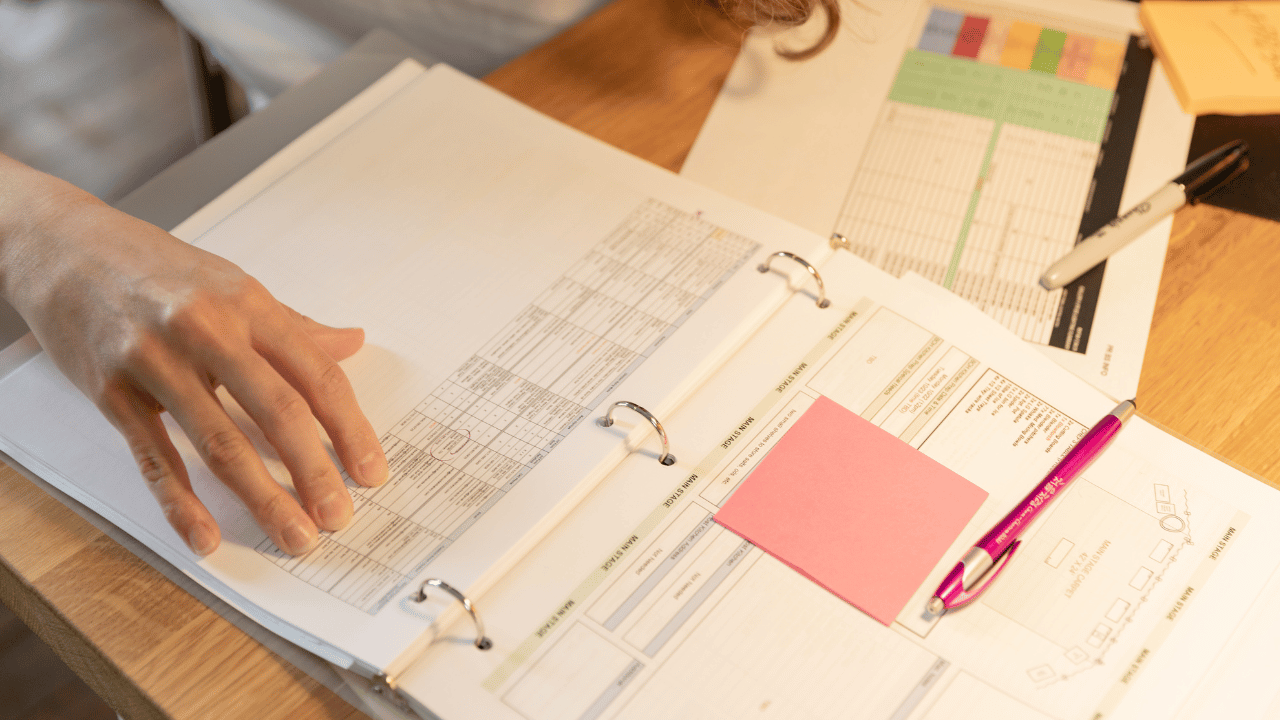
抽象的な議論を避けるためには、主張と具体例のバランスが欠かせません。学芸国際が求める「具体性」とは、主張と事例の間に論理的な橋渡しを行う「ズームイン」の技術です。
抽象的な主張から「具体化の連鎖」で掘り下げる
エッセイ作成時は、以下の「具体化の連鎖」を意識し、事例の質を高めましょう。
テーマが「クラブ活動の講師の外部委託」の場合の例:
- 主張(Topic Sentence):外部委託は、生徒のスポーツスキル向上に有効だ。
- 理由(Explanation):プロの先生から専門的なアドバイスがもらえるからだ。
- 具体的/OK例(Specific Example/Zoom-in):
- 単に「プロの先生のアドバイス」で終わらせず、「例えば、学校の先生が教える基本技術を超え、水泳クラブではバタフライや個人メドレーといった高度な泳ぎ方や、怪我の予防法など、専門家ならではの知識に触れることができる。これにより、生徒はより早期に専門分野での成長を達成しやすくなる」と掘り下げる。
3.「書き直し」で完璧なエッセイの型を覚える
受験対策の終盤は、「新しいエッセイを書く練習」と「既存のエッセイを書き直す練習」の二刀流で取り組みましょう。
- 新しいエッセイ(模擬試験):時間制限45分を厳守し、初見のテーマに実力で対応する。
- 書き直し(パーフェクト・エッセイ作成):時間制限を外し、辞書やインターネットをフル活用して「もし時間があればここまで書ける」という最高の論理性、語彙力、構成でエッセイを完成させる。
この「完璧を目指した書き直し」を行うことで、合格ラインのエッセイが持つべき論理の運び方や具体例の配置を脳に刻み込むことができます。自己の弱点を認識し、理想的な完成形を何度も経験することが、本番での応用力向上に最も寄与します。
TCK Workshopの「学芸国際対策講座」で合格を確実に

TCK Workshopでは、学芸国際の入試を知り尽くした講師陣(中には学芸国際の卒業生もいます!)が、帰国生一人ひとりの状況に合わせた個別指導を提供しています。
外国語作文、日本語作文、グループディスカッション対策、そして面接指導までを一貫してオンラインで指導。海外に住んでいて日本の受験情報が手に入りにくい生徒や、帰国後の限られた時間で効率的に対策を進めたい生徒にとって、最適なサポート体制です。
まとめ
東京学芸大学附属国際中等教育学校(学芸国際)の外国語作文(英語エッセイ)で合格を掴むための重要ポイントは以下の通りです。
- 試験の形式: 制限時間45分でPersuasive Essay(説得的な論述文)を構成する。
- 求められる力: 論理性、客観性、そして多様な視点から問題を分析する能力。
- 対策の鍵: 「生徒以外の立場」を含む多角的な視点で論を構成すること。主張と事例を繋ぐ「ズームイン」による具体性の徹底。
- 実践的な訓練: 時間を測る「新規エッセイ」と、完成度を追求する「書き直し」を並行して実施する。