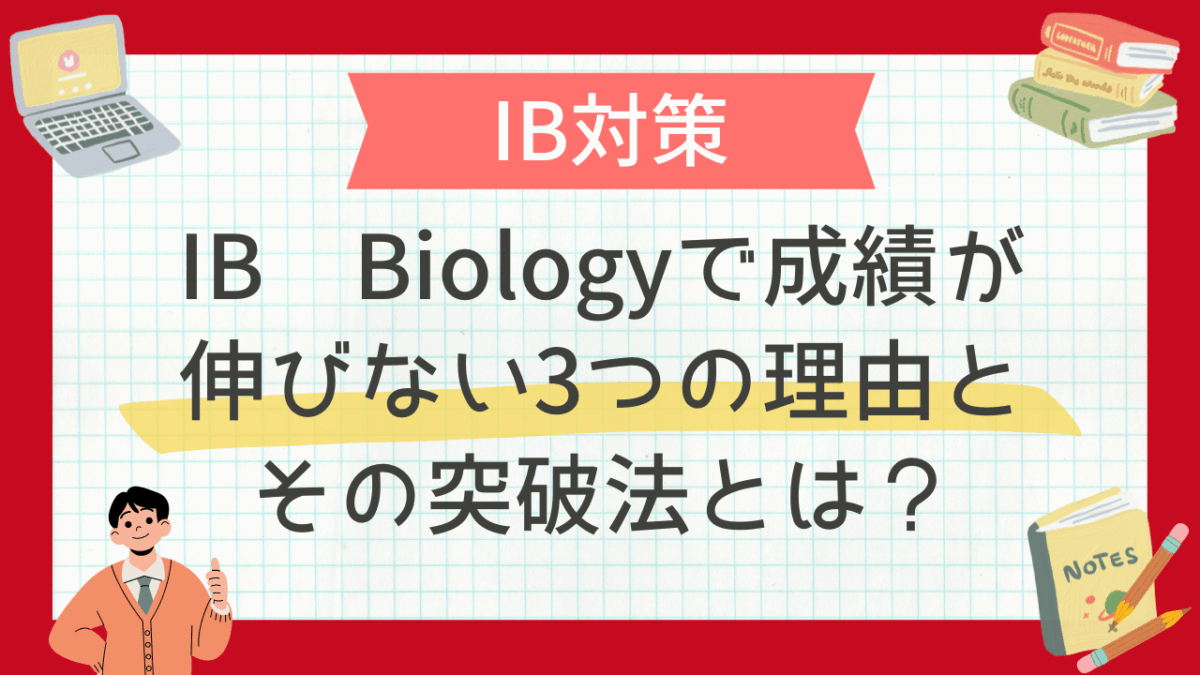「なぜ覚えたはずの用語が書けないのか?」IB Biologyに潜む“見えない壁”
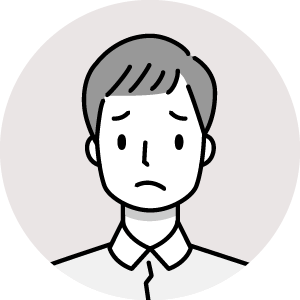
「授業で聞いたときは理解できたはずなのに、いざ記述問題になると全く書けない」

「専門用語を覚えてもすぐに忘れてしまう」
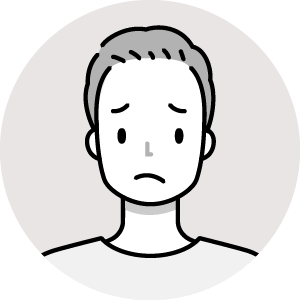
「IAの実験テーマが決まらず、締切が迫って焦っている」
IB Biologyを学習する中で、こうした声を頻繁に耳にします。
IB Biologyは、他の科目以上に“暗記+理解+論述”の3要素が複雑に絡み合っており、一筋縄ではいかない科目です。しかもHLでは細胞生物学や分子生物学、遺伝学など専門性の高い内容を英語で理解し、記述式でアウトプットする必要があります。SLであっても、用語の正確な定義と記述力は求められ、単なる丸暗記では太刀打ちできません。
さらに、Internal Assessment(IA)では実験設計・データ解析・論述が求められ、時間と労力がかかるうえに、テーマ選びの段階でつまずく生徒も少なくありません。こうした複合的な難しさが、IB Biologyにおける成績停滞の背景にあるのです。
「うちの子もそうでした」IB Biologyで苦戦した生徒のリアルな体験
TCK Workshopに相談いただくIB生徒の中には、もともと理科が得意だったにもかかわらず、IB Biologyで初めて「できない」「わからない」という壁に直面する生徒が少なくありません。
たとえば、マレーシアのインター校に通うKさん(Year 2・HL)は、授業の理解は問題ないものの、Paper 2の記述問題で点数が伸び悩んでいました。専門用語の定義は覚えているものの、設問に対する“論理的な組み立て方”が分からず、減点されていたのです。IAにおいても、「オリジナリティのあるテーマを選ばなければいけない」と思い込み、必要以上に悩んでしまい、提出直前まで不安を抱えていました。
彼女のお母様からは「こんなに真面目にやっているのに、なぜ結果が出ないのか分からない」「親が教えるには難しすぎる」とのお悩みもあり、専門的な伴走が必要だと感じてご相談いただきました。このように、努力が空回りしてしまうのは、IB Biologyという科目特有の“構造的な難しさ”があるからこそなのです。
記述・用語・実験…IB Biologyで結果を出すための3つの戦略
1. 用語は”定義”だけでなく”使用文脈”とセットで覚える
IB Biologyでは、単語帳的な丸暗記だけでは不十分です。実際に評価基準では、”use of appropriate terminology”(適切な専門用語の使用)が問われます。たとえば”osmosis”(浸透)であれば、”passive movement of water molecules across a partially permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration”という定義を暗記するだけでなく、それをどう文中で自然に使えるかが評価の分かれ目になります。
そのため、効果的な方法としては、過去問記述の模範解答における用語の使われ方をチェックし、それを自分の言葉で再構成してみることが推奨されます。University of CambridgeやOxfordのIB Biology Tutorも、記述と用語習得をセットにした学習が効果的と提唱しています。
2. 記述問題は”構造”と”プロセス”で組み立てる
Paper 2や3では、短文で済まない論述問題が出題されます。よくある失敗は、単語やフレーズを並べただけで、因果関係やプロセスが説明できていないケースです。
IBの公式ガイドラインでは、特にLevel 6〜7を目指す生徒に対して、**”構造化された解答“(structured responses)**が求められると明記されています。つまり、単に事実を羅列するのではなく、”なぜそれが起こるのか(mechanism)”、”どのように作用するのか(process)”を説明する必要があるのです。
たとえば、免疫応答に関する記述では、マクロファージ→ヘルパーT細胞→B細胞→抗体の産生…といった順序に沿った因果関係を明確にし、それぞれのステップにどんな化学物質や細胞が関与するかを整理して書く必要があります。TCK Workshopではこの構造化力を鍛えるために、過去問ベースの記述トレーニングを段階的に行っています。
3. IAでは”独自性”より”実現性”と”考察力”が評価される
IAに関しては、”他人と違うテーマでなければならない”という誤解を持つ生徒が多くいます。しかし、IB公式では、“テーマの独自性”は採点基準に含まれていません。
大切なのは、”明確なリサーチクエスチョン”と”実験の再現性・論理性”です。たとえば「光の強さと光合成速度の関係」といったシンプルなテーマでも、統制変数の設定やエラー分析、参考文献の使い方、考察での他者研究との比較がしっかりしていれば高評価が得られます。
「IAで高スコアを取る生徒は、内容の奇抜さではなく、実験計画の整合性とデータの読み取りに優れている」
University of QueenslandのIB Biology教官によると、上記の通りに述べています。TCK Workshopでは、生徒一人ひとりの関心に寄り添いながら、IAのテーマ選びからデータ処理、考察指導まで一貫して伴走しています。
個別最適化されたIB Biology指導で、記述力も実験も自信に変わる
TCK Workshopでは、IB Biologyに特化した個別指導を通じて、生徒一人ひとりの課題に応じた最適なサポートを提供しています。記述問題対策では、過去問を活用した添削指導とロジカルライティングのトレーニングを実施。特に、解答の構造化(Cause→Process→Outcome)を重視し、得点に直結する書き方を指導しています。
IA対策では、テーマ選定から実験計画の妥当性チェック、データ分析、考察の構成までトータルにサポート。実験キットが使えない海外在住生徒向けには、シミュレーション型データを用いたIA練習も提供しています。
特に印象的だったのは、ニューヨーク在住のMさん(Year 2 HL)が、IAの指導を受けた結果、当初は17点だったスコアが26点にまで伸び、最終的に7点満点を達成した事例です。彼女の保護者様からも「先生に出会っていなかったら、IAを諦めていたと思う」と嬉しいお言葉をいただきました。
「あと一歩」で伸び悩む生徒こそ、IB Biologyサポートが効果的
特に以下のような状況にある生徒・保護者様にとって、TCK WorkshopのIB Biologyサポートは大きな効果が期待できます。
- 「理解はできているはずなのに、記述になるとうまく書けない」
- 「IAの方向性が定まらず、時間だけが過ぎていく」
- 「過去問を解いても、なぜ点数が取れないのか分からない」
また、プレIB生で、これからIB Biologyを履修しようと考えている方にとっても、先取り学習で用語や記述の土台を築いておくことは大きな武器になります。
海外在住やインター校で、英語環境にあっても専門用語の扱いや記述構成は難易度が高いため、学校外での専門的な支援が鍵となります。特に医療系・生命科学系の進路を目指す生徒にとって、IB Biologyは基盤科目。今のつまずきを放置せず、早めの対策が将来への第一歩になります。
まずは「無料相談」から。学習の方向性を見つけませんか?
もしこの記事を読んで、「うちの子にも当てはまるかも」と感じた方は、まずはお気軽にTCK Workshopの無料教育相談をご利用ください。経験豊富なIB指導者が、お子様の現在地を一緒に分析し、最適な学習プランをご提案いたします。
また、「一度試してみてから判断したい」という方には、体験授業もおすすめです。記述添削やIAのテーマ相談など、ニーズに応じて内容をカスタマイズできます。
「このまま様子を見る」ではなく、「一歩踏み出す」ことで見えてくる景色があります。IB Biologyの学習に不安がある今だからこそ、まずは無料相談から始めてみませんか?