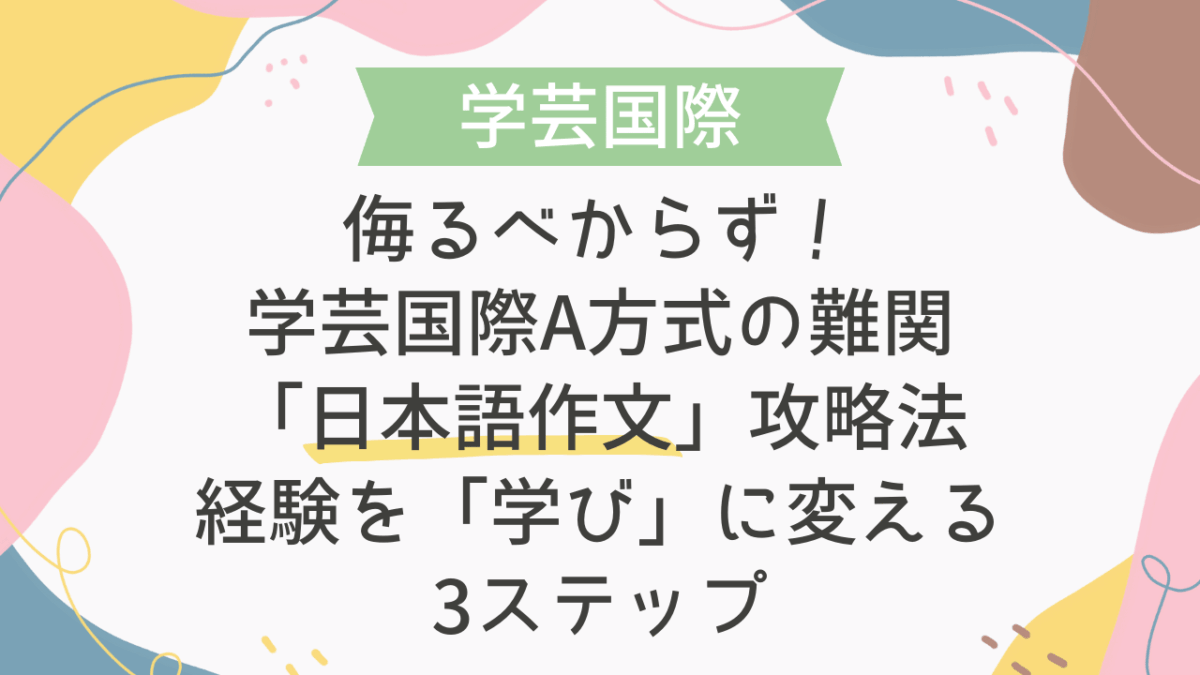帰国生がつまずく!学芸国際A方式の「日本語作文」で高得点を取る方法
東京学芸大学附属国際中等教育学校(学芸国際)のA方式入試において、基礎日本語作文(15点満点)は、外国語作文(85点満点)に比べて配点は小さいものの、合否を分ける重要な要素です。この作文で問われるのは、単なる日本語力ではなく、「自らの経験や知識に基づき、自分の考えを適切に表現する力」です(東京学芸大学附属国際中等教育学校の採点基準より)。
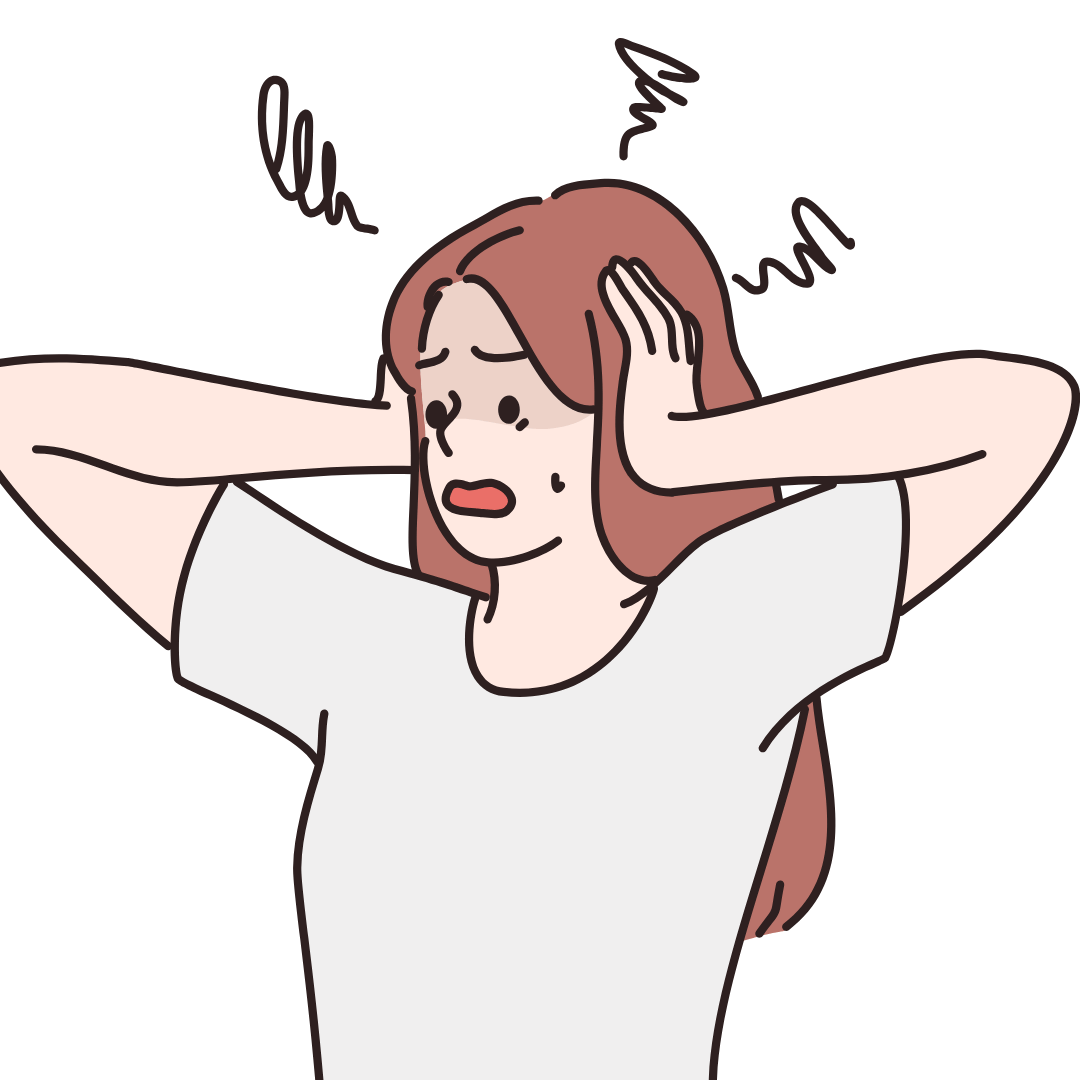
経験をどう書けばいいのかわからない
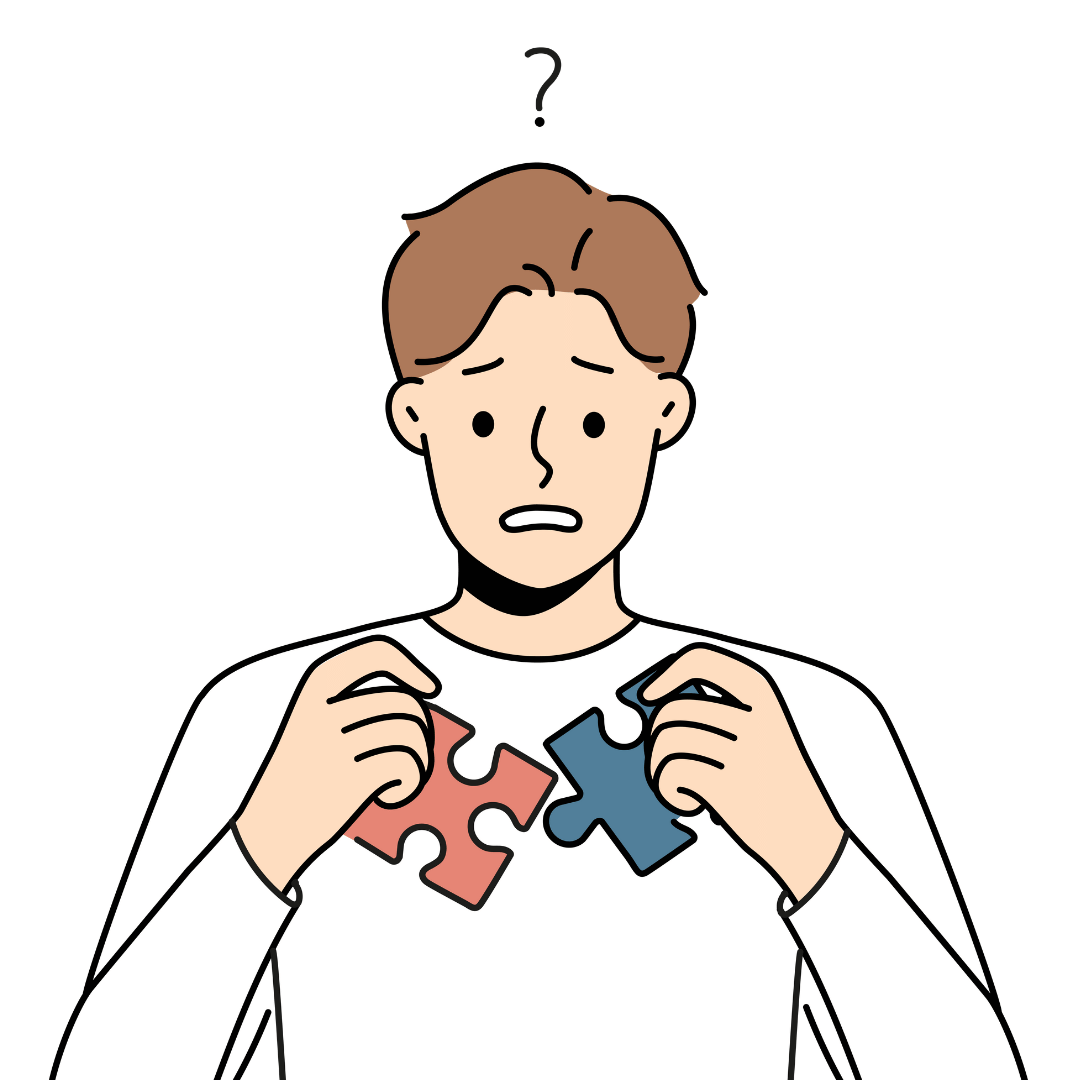
論理的な文章構成が崩れてしまう
特に海外での生活が長く、日本語での論理的な文章作成に不安を持つ帰国生にとって、ここは大きな壁になりがちです。学芸国際の日本語作文は、制限時間30分でテーマ型の課題に臨む形式です。その核心は、自己の経験に基づき、それを客観的・社会的な視点で論理的に説明し、意見を論じる力(意見論述力)にあります。
この記事では、TCK Workshopの指導経験から、学芸国際の日本語作文で高得点を取るための「内省の深さ」と「構成の一貫性」を生み出す具体的な戦略を解説します。
帰国生が日本語作文で点数を落とす2つの致命的なミス

学芸国際の作文指導を通して、多くの帰国生が共通して犯しがちな、採点評価を大きく下げる2つのミスがあります。このミスを回避することが、合格への第一歩です。
1. 経験の「内面的な掘り下げ」が足りない
作文で問われているのは、単なる出来事の報告ではありません。例えば、「海外のサッカークラブに入り、チームメイトと仲良くなった」という事実だけでは、作文のテーマである「学び」や「考え」を掘り下げたことにはなりません。
評価されるのは、その経験を通して「何を感じたか」「何を考えたか」「自分にどんな変化が起きたか」という内面への掘り下げです。海外に行く前は消極的だったけれど、インターナショナルスクールでの経験を通して「積極的に意見を伝えることが怖くなくなった」といった、具体的な学びや価値観の変化を記述する必要があります。
小さな学びや価値観の変化を、自己のビフォー・アフターと関連付けて表現することで、説得力が格段に増します。作文が「経験や知識に基づき、問題に対応した答えになっている」(東京学芸大学附属国際中等教育学校の採点基準A内容)と評価されるためには、この内省が不可欠です。
2. 序論・本論・結論の「論旨の一貫性」が崩壊する
制限時間30分という短時間で、論理的な文章を構築するのは容易ではありません。特に日本語での意見論述に慣れていない帰国生に多いのが、「序論で掲げた主張と結論で着地した主張がズレている」という現象です。
これは、本論でエピソードを書いているうちに、最初の主張を忘れ、単なる物語の紹介になってしまうことで起こります。文章構成にはそれぞれ役割があります。
- 序論: 主張と問題提起(「私は〇〇だと考える」)
- 本論: 主張を支える具体的なエピソードと理由(「なぜなら、××という経験があるからだ」)
- 結論: 主張の再確認と社会への展望(「この経験から、やはり〇〇が重要であり、社会にも応用できる」)
この一連の流れを逆から見ても繋がっているかを確認する意識が必要です。結論の「学び」を見たときに、「その学びを引き出すために、本論のエピソードは適切だったか?」と常に自問自答しましょう。
日本語作文で「論理」と「深さ」を生み出す3ステップ戦略
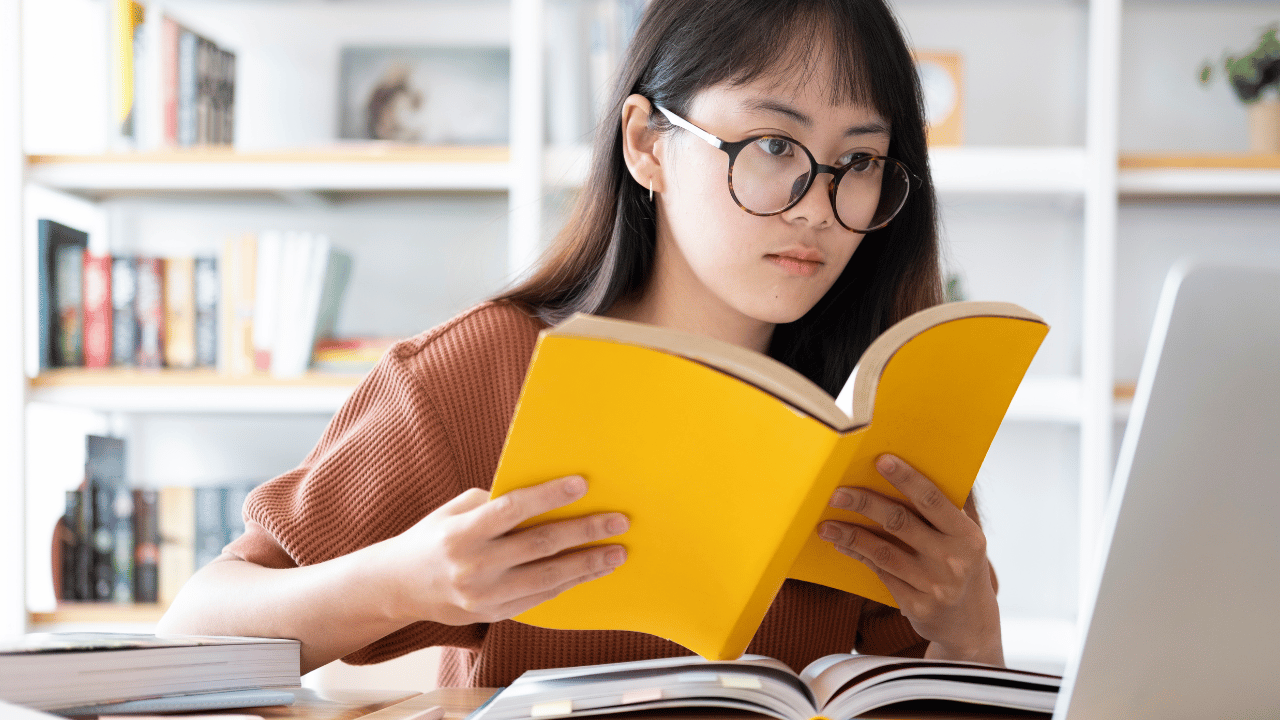
学芸国際の日本語作文で求められる「経験に基づく論理的な意見論述」に対応するために、準備段階から試験本番まで役立つ3つのステップを紹介します。
ステップ1:過去の経験を「カード化」してストックする(経験の棚卸し)
テーマ型作文は、出題テーマを見てからエピソードを探していては間に合いません。あらかじめ、作文で使いやすい自分の経験をストックしておく必要があります。
まずは、過去の経験を振り返り、「ターニングポイントになった出来事」「価値観が大きく変わった出来事」「大変な思いをしたが乗り越えた出来事」といった、自分の内面に大きな変化をもたらしたエピソードをピックアップしましょう。
次に、そのエピソードを、単なる出来事の報告ではなく、「失敗と成功」「自由と責任」「協調性」など、複数のテーマに対応できるような「エピソードカード」としてストックします。例えば、「インターナショナルスクールでの協働学習」のエピソードは、「多様性の中での自分の視点の変化」というテーマにも、「失敗を乗り越えた経験」というテーマにも応用できます。
この「エピソードカード」をいくつか持つことで、本番でどのようなテーマが出題されても、手持ちのカードを使って対応することが可能になります。これは、同時に志望理由書の準備にも繋がるため、一石二鳥の対策です。
日本語作文の土台となる国語力の強化法については、こちらの記事も参考にしてください。
どれほどの国語力が必要?広尾・かえつ・茗渓など日本語作文が必要な学校の対策!
ステップ2:作文の「設計図」を逆算で作成する
制限時間30分を有効活用するために、いきなり書き始めるのではなく、まずは「設計図」(構成メモ)の作成に時間を割きましょう。この設計図は、結論から逆算して作成することが重要です。
| 構成要素 | 役割と意識すべきこと | 想定所要時間 |
| 結論 | 最も伝えたい「学び」と「社会への展望」を決定する。ここで着地点を固めることが一貫性を保つ鍵。 | 3分 |
| 序論 | 結論で決めた「主張」を、テーマに関連付けて力強く宣言する。 | 2分 |
| 本論 | 結論と繋がる「エピソードカード」を選定し、内面の変化を具体的に描写する。 | 5分 |
| 清書/確認 | 原稿用紙のルール、漢字の使用、文体の一致を確認。 逆算して論旨が繋がっているかを最終チェック。 | 20分 |
作文は序論→本論→結論の順番で書きますが、設計図は結論→序論→本論の順番で考えると論理的崩壊を防げます。文章構成の練習は、「文や段落につながりがあり、筋道が読み取れる」(東京学芸大学附属国際中等教育学校の採点基準B構成・言語)という評価基準をクリアするために不可欠です。
📝 さらに詳しい受験準備の進め方を知りたい方はこちらもご覧ください
帰国子女の中学受験スケジュール|いつ何をすべきか?
ステップ3:積極的に「漢字」と「原稿用紙のルール」を使う
海外生活が長いと、日本語の漢字使用に抵抗がある、あるいは原稿用紙の使い方に慣れていない場合があります。しかし、試験の練習段階からこれらの「基本ルール」を徹底することが、本番での安定したパフォーマンスに繋がります。
- 漢字の積極的な使用
練習のときから積極的に漢字を使いましょう。間違えることは悪いことではなく、自分の漢字の「癖」を発見し、克服するチャンスです。漢字を多く使うことは、読み手(採点官)に日本語力への意欲と学力を示すことにも繋がります。 - 原稿用紙ルールの徹底
学芸国際の日本語作文は原稿用紙での記述に移行しています。句読点の打ち方、かぎ括弧や記号の使い方、アルファベットや数字の扱い方など、原稿用紙の基本的なルールは、知っているのと実際に使えるのとは全く違います。インターネットで入手できる原稿用紙を活用し、実際に600字以上の文章を書き、ルールを守れるか確認する訓練を積んでください。これは、試験当日にルールの説明に時間を割かれることなく、作文に集中するための「最低ラインの準備」です。
TCK Workshopの特別講座で徹底対策
TCK Workshopでは、学芸国際A方式入試を突破するための専門的な対策講座をご用意しています。特に、日本語作文は、帰国生特有の課題に合わせて個別指導で集中的に強化します。
実力判定テストで客観的な評価を得る
個別指導では、生徒一人ひとりの「エピソードカード」作成からサポートし、論理構成の強化、内省の深掘りを支援します。さらに、「東京学芸国際 国際生入試 A方式 実力判定テスト」を通じて、客観的な評価を得られます。
- 評価とフィードバック: テストでは、英語エッセイと日本語作文の得点力を客観的に評価し、現在の合格ラインとの差を明確にします。
- 添削指導: 採点を担当した先生による解説オプションもあり、「どこが減点されたのか」「どう直せば良かったのか」といった具体的なアドバイスを受けることで、自己流の対策から脱却し、「書ける」だけでなく「点数が取れる」日本語作文力を身につけます。
この実力判定テストと個別指導の組み合わせが、あなたの学芸国際合格を強力に後押しします。
TCK Workshopの「学芸国際対策講座」で合格を確実にする
TCK Workshopでは、学芸国際の入試を知り尽くした講師陣(中には学芸国際の卒業生もいます)が、帰国生一人ひとりの状況に合わせた個別指導を提供しています。
外国語作文、日本語作文、グループディスカッション対策、そして面接指導までを一貫してオンラインで指導。海外に住んでいて日本の受験情報が手に入りにくい生徒や、帰国後の限られた時間で効率的に対策を進めたい生徒にとって、最適なサポート体制です。
まとめ
学芸国際A方式の日本語作文は、「自分の経験を論理的に、深い内省をもって語れるか」**を試す試験です。合格を勝ち取るために、以下のポイントを徹底してください。
- 作文の核は「内面の変化」: 出来事の羅列ではなく、経験を通じて自分がどう変わったかを具体的に記述し、問題の内容を的確に理解していることを示す。
- 結論から逆算する設計図: 最初に「学び」と「主張」を明確にし、論旨の一貫性を保つ。
- 漢字と原稿用紙に慣れる: 練習の段階から基本ルールを徹底し、適切な語法を使えるよう準備する。
今すぐ、過去の経験の棚卸しを始め、合格へ向けた第一歩を踏み出しましょう!