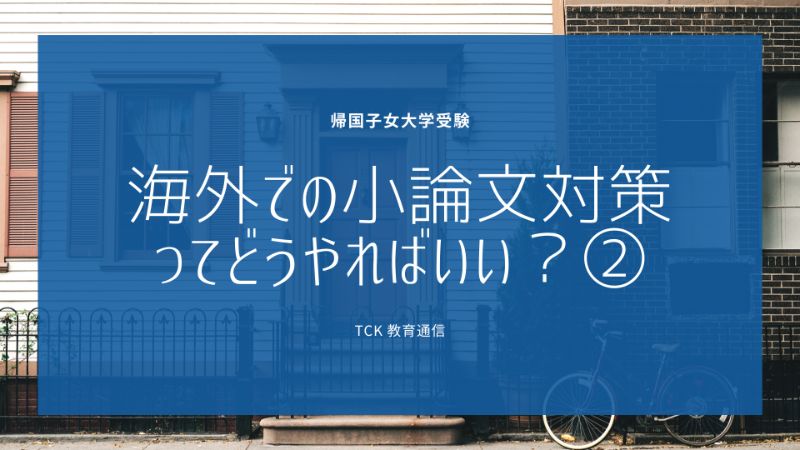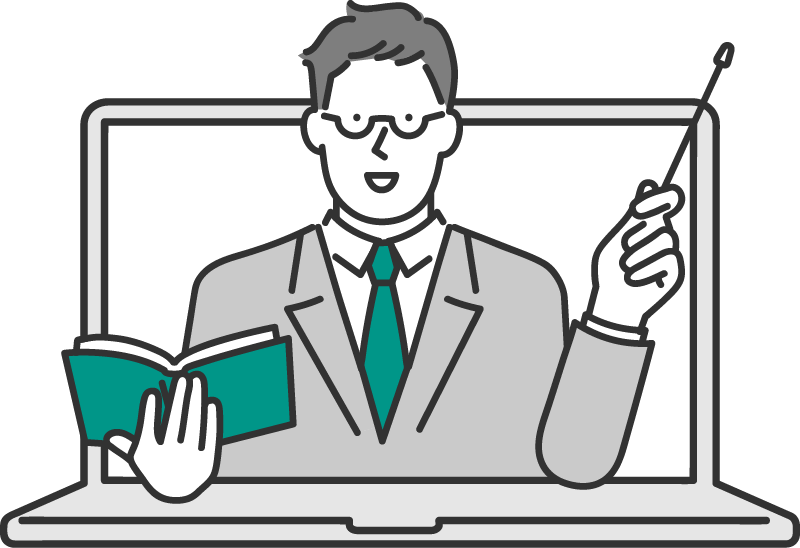多くの大学で、帰国生に課される小論文試験。でも
- 普通の試験とは違って正解がないから、どう勉強していいのか全くわからない!
- 結局小論文試験って、何が必要なの?
という疑問に対して前回は、小論文試験には、「アイデア力」と「構成力」の二つが必要であること、そして「アイデア力」を鍛える具体的な勉強法には、
- 日本の「政治経済」の教科書を二周すべし!
- ネタ帳を普段から持っておくべし!
- 入門書一冊を自分の「バイブル」にすべし!
という方法があることをお伝えしました。
今回は、その後編ということで、小論文に必要なもう一つの力、「構成力」の鍛え方をご紹介したいと思います!
構成力って?
具体的な勉強法をご紹介する前にまず、「構成力」とは何なのかを簡単に見ていきましょう!
前回もお伝えしたように、「構成力」とは、生み出したアイデアを、分かりやすく、筋道立てて構成し、説得力と魅力を兼ね備えた文章にする力のことです。
料理にたとえるとすれば、アイデアが材料なら、構成力は調理の技術そのもの。
どんなに良い食材でも、調理の過程で失敗してしまえば、美味しくはならない。
逆に言えば、苦手な食材でも、調理の工夫次第では「あ、意外と美味しい!」となることもありますよね。
小論文もそれと同じです。
どんなに良いアイデアでも、上手く文章全体の流れに組み込めなければ、その良さは残念ながら伝わりません。
逆に、アイデアがありふれていたとしても、しっかりとした構成でまとめられていれば、魅力的に見えるでしょう。
これで「構成力」がいかに大事か、お分かり頂けたでしょうか?では早速、「構成力」の鍛え方をご紹介したいと思います。
「構成力」の鍛え方
良い構成に大事なもの、それは一にも二にも「一貫性」!
「一貫性」とは簡単に言えば、文章全体で「言いたいこと」がまとまっているか、です。
アイデアが沢山浮かんできて、あれも入れたいこれも入れたい!とついつい欲張ってしまう気持ちはよく分かります。
折角思いついたナイスアイデア、採点者に見て欲しいと思うのは、当然のことです。
けれども、そのせいで「一つ一つのアイデアはとても良いのに全体を見るとイマイチ何が言いたいのか伝わらない」そんな文章になってしまっていませんか?
先ほどの料理の例に戻りましょう。
目の前に、本マグロと最高級チョコレートが置いてあるとします。
どちらも単独で食べれば、とても美味しい食材です。
けれど、この二つを無理に一緒の料理に入れようとするとどうでしょう?
不味くなることは容易に想像できるでしょう。
もちろん、相当の技術力を持ったシェフであれば、この異色の組み合わせから素晴らしい一品を作り出すことも不可能ではないのかもしれません。
けれども、残念ながら私たちはプロではありません。
無理に二つの食材を一つの料理に入れようとすると、悲惨な結果に終わってしまいかねません。
小論文もまた然り。
メインとなるようなアイデアを無理に一つの文章の中に入れようとすると、アイデア同士が文章の中で喧嘩してしまいます。
それを避ける為にも、浮かんできたアイデアを上手く整理・分類して、パズルのように、書く場所を調整しながら、メインとなる一つの考えが引き立つようにしなければいけないのです。
では、具体的にどのようなことを意識して練習をすると良いのでしょうか?
その1:問題を読み解く練習をすべし!
問題を読み解く練習、と聞いて皆さんが思い浮かべるのは恐らく、課題文のある小論文でしょう。
もちろん、課題文があるのなら、それを読み解く練習は不可欠です。
私の志望大学の試験は「課題文のある小論文じゃないからな〜」と思ったそこのあなた!
課題文の有無は関係ないのです。
なぜなら、私がここで言う「問題」とは、課題文のことではなく、
- 「〜について〇〇字以内でまとめなさい」
- 「〜〇〇字以内で、あなたの意見を述べなさい」
というような指示を出している問題文のことだからです。
「え、こんな短い文章、読み解くも何もそのままじゃないの?」
そんな風に思われても仕方がありません。
けれども、課題文のあるなしにかかわらず、この問題文は非常に大事なのです!
問題文は言ってみれば、小論文試験で大学側が学生に与える唯一のヒント。
問題文を分解して、一つ一つの言葉から、大学側は学生に「何を」「どのような立場に立って」書いて欲しいのかを推測してみましょう。
そして、問題文が求めているものに注意しながら、再度自分のアイデアと見比べてみましょう!
どのアイデアを残して、どのアイデアを切り捨てるべきなのかが自ずと見えてくるはずです。
このように、問題文の意図することを推測する練習をしておくと、本番、どんな問題文が出てきたとしても、焦ることなく、アイデアを絞り込むことが出来るようになります。
その2:出だしとエンディングにこだわるべし!
皆さんは、ミステリー小説はよく読みますか?
面白いミステリー小説の多くは、「伏線の回収」がとても上手いですよね。
最後に謎が解けた後に振り返ってみると、こんなところにもあんなところにも伏線が張られていた、と発見した時の爽快感、そして感動といったら!
小論文も同じです。
最初に言っていたことと最後に言っていることが一致しているだけでも、文章全体に一貫性が生まれ、読む側の感動を引き出すことが出来ます。
けれど「伏線回収」というのは案外難しいもの。
人を感心させるような「伏線回収」ならば尚更です。
そこで皆さんに是非やってみてもらいたいのは、出だしの部分に、自分の小論文のメインとなる主張と関わりのある「キーワード」を置くことです。
そして、最後のエンディングのどこかにも、この「キーワード」を登場させて下さい。
「キーワード」を中心に出だしとエンディングを書くことで、自然と内容も対応するものになってくるはずです。
その3:「プロットだけ」の練習を沢山すべし!
結局のところ、構成力をつける上で一番大切なのは、何度も繰り返し練習をすること!
試行錯誤を繰り返す中で、自分のスタイルを確立するのが最も効果的です。
けれど、小論文一本を書くのは、それなりの時間と労力を要します。
「他の科目の勉強もしたいから、小論文の勉強にばかり時間を割いていられない!」そんな受験生もいることでしょう。
そんな人にオススメしたいのが、
問題文を読んで、分析し、プロット、つまり小論文の構成だけを書き出してみる練習を繰り返す勉強法。
実際に全文を書く訳ではないので、表現力の向上や、時間配分の調整には効果的ではないかもしれませんが、段落ごとに何を書くかを書き出してみるだけでも、「構成力」の向上には効果的です。
本当に時間がない時、本番までにとにかく色んな種類の問題に触れておきたい時に、取り入れてみて下さい。
まとめ
さて、今回は小論文に必要な「アイデア力」と「構成力」の内の、「構成力」に重点を置いて
- 問題を読み解く練習をすべし!
- 出だしとエンディングにこだわるべし!
- 「プロットだけ」の練習を沢山すべし!
という三つの勉強法をご紹介しましたが、いかがでしたか?
少しは、小論文の勉強に関する不安を解消できたでしょうか?
冒頭でも触れましたが、帰国生入試の小論文試験には良くも悪くも「正答」がありません。
この「正解のなさ」こそ、受験生の皆さんの不安の原因の一つかと思います。
けれど、「正答」という枠がない小論文試験は、枠を超えて、大学側にあなたをアピールできるチャンスの場でもあります。