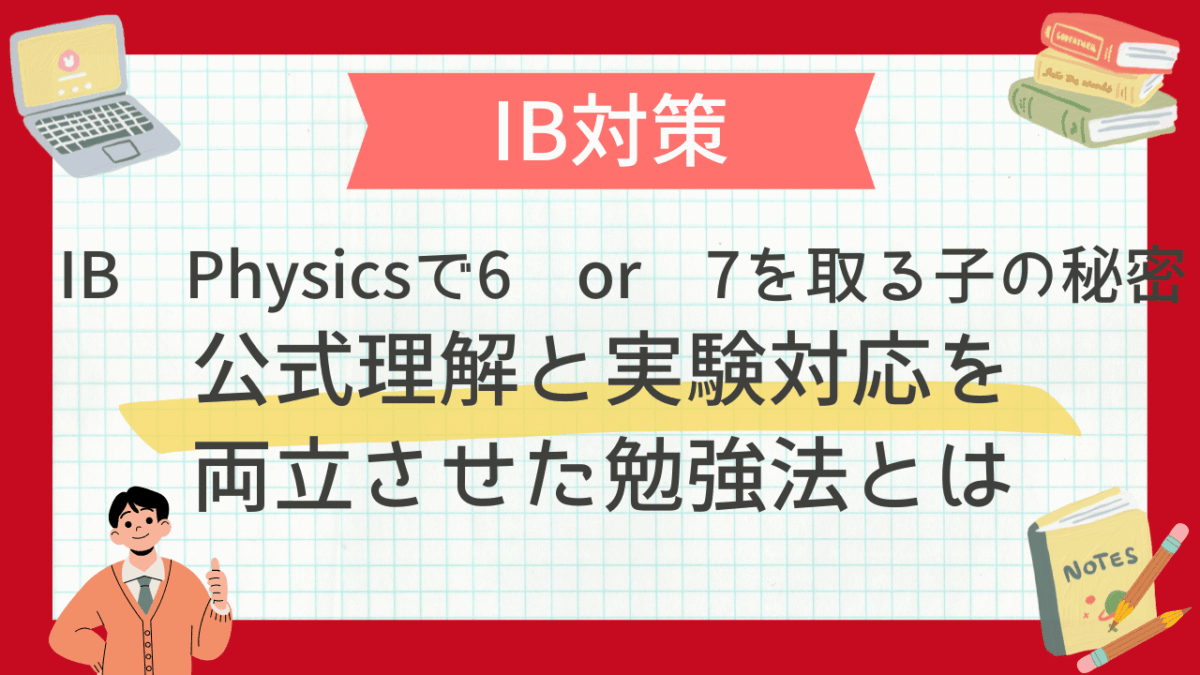「公式は覚えたのに点が取れない…」その理由はここにあります

「学校のテストで点数が取れない…」
そんな声がIB Physicsを履修する生徒から学校が始まり2,3か月経過してからTCK Workshopへと相談が相次ぎます。物理は理科の中でも比較的に勉強がしやすく点数も取りやすい科目です。公式はある程度暗記していても、実際の設問でどう使うかがわからない——それが、多くの高校生が抱える深刻な問題です。
さらに、実験が絡んだ問題では「記述が曖昧で減点される」「なぜこの操作を行ったのか説明できない」といった課題も浮き彫りになります。IB Physicsでは、ただの知識よりも“なぜそうなるか”の理解と論理の組み立てが重視されるため、形式的な暗記では通用しません。
このような壁に直面して、「うちの子、理系なのに物理だけ点が取れない」と感じている生徒も多いのではないでしょうか。中には、「学校の授業では本人も問題なくついて言っているというけど、試験では全然点が取れない」というギャップに悩むケースも少なくありません。
「私たちも同じ悩みを抱えていました」ある母親と娘の葛藤
Eさん(12年生)は、もともと数学が得意な理系タイプ。IAの研究テーマも独自性があり、内部評価では好成績を収めていました。しかし、模試や過去問の試験では得点が伸びず、特にPaper 2の実験問題で苦戦していました。記述があいまいになり、「わかっているはずなのに減点」という状況に。結局、試験の点数が悪いからPredictedは3。志望大学のため何が何でも6を狙いたい…
お母様も「本人は夜遅くまでよく頑張っているんですが、どうもやり方が間違えているのか、毎回テストでは点数が取れず…私も物理のことなんて何もアドバイスができなくて。学生の家庭教師をオンラインでつけていましたが、成果が出ず…正直もう諦めてます。」と不安をこぼしていました。「このままでは志望大学の変更をしなくては…」と、TCK Workshopにご相談いただきました。
そこで行ったのは、徹底的なテスト対策です。シラバスについて知る、テストについて知る、記述方法について知る。こういった知識、技術のインプットは学校では習いません。学校での学びと家庭学習は別物。そういったIBの理解についても指導しました。結果、Eさんは数ヶ月でPhysicsのスコアを3点から6点に上げ、見事に志望大学の理系学部に合格されました。このような変化を支えるのが、今からご紹介する3つのポイントです。
“公式だけ”の学習では通用しない!IB Physicsで差がつく3つの学習戦略
ポイント1:公式を理解で使う「文脈力」の養成
IB Physicsでは、公式を丸暗記しているだけでは得点に結びつきません。大切なのは、「どの公式・理論を、どんな場面で使うのか」を説明できる力です。例えば運動方程式 F=ma ひとつをとっても、それを使うのが直線運動なのか、回転運動なのか、斜面上の物体なのかで適用の仕方が大きく変わります。
この力を養うために有効なのが、「文脈とセットで学ぶ演習」です。重要なことは、過去問を単に解くのではなく、「なぜこの問題でこの式を使うのか」「他の式との違いは何か」を言語化するトレーニングを積み重ねます。これにより、「理解して使う」姿勢が身に付き、初見問題にも対応できる応用力が育ちます。
ポイント2:実験問題の得点力を伸ばす“記述リハーサル”
IB Physicsの中でも多くの受験生が苦手とするのが、実験に関する記述問題です。たとえば、「誤差の原因を考察せよ」「手順の妥当性を評価せよ」といった設問に対し、主観的な表現や曖昧な語句では減点されてしまいます。
TCK Workshopでは、科学的根拠をもとに説明する「記述の型」を指導しています。たとえば「実験の信頼性を高めるにはどうすればよいか」という問いに対して、「変数を1つに絞る理由」「測定回数を増やす目的」などを論理的に記述する練習を行います。これらはマークスキーム、教科書に全て説明がされている内容なのです。これにより、生徒の表現力が格段に向上し、記述式問題で安定して得点できるようになります。
ポイント3:“理解している”と“でも点数が取れない”の“ギャップ”を埋めるアプローチ
授業で扱う内容は理解している。先生が言っていることは理解できている。でも試験では思うように結果が出ない——このギャップも多くの生徒が直面しています。厳しい言い方をしますが、理解できる=できる、ではないということをしっかりと受け止めましょう。英語がわかる(Listening)からといって、話せる(Speaking)はまったく別物ですよね?点数が取れない原因は、大体の場合理解(インプット)が浅い、問題演習(アウトプット)が足りていないです。問題文を読んだだけで、どの理論、どの公式というのがパッパッパっとでてこないようであれば、それはまだまだ準備不足である証拠です。テストで点数を取ることを超短期的な目標とするならば、良きIB Learnerとは違うベクトルで考えましょう。テスト対策をゴリゴリにするしかないんです。
そこで必要なのが「試験対応力」の強化です。具体的には、シラバス(理論)で学んだ内容を過去問題や類似問題で「実践力」を養います。TCK Workshopでは、この理論の学びと実際の試験問題の橋渡しとなる指導により、生徒の本番力を確実に引き上げています。
公式暗記から“使える知識”へ。指導のプロが生徒の力を引き出します
TCK WorkshopのIB Physics対策では、知識の詰め込みではなく、「使える理解」と「説明できる思考力」を重視した個別指導を行っています。TCK Workshopの代表の岡留講師はIB Physicsを20年弱に渡り指導を続けているベテランの講師です。IBだけでなく、AP、IGCSE、A-level、NCEA、さらに日本の大学受験物理も指導を続けています。世界中のカリキュラムを知っている岡留講師は、物理、化学、数学の指導について、アルバイトの学生講師が解らない点などについてもフォローアップをしています。過去問やPredicted評価の傾向をふまえ、各生徒に最適な学習設計を提案します。
たとえば前述のEさんは、講師との1対1の記述演習で「曖昧な表現」を徹底的に改善。Command termそれぞれに対してどのように返答をすべきか、を理解できてからは、解答は解りやすく的を射たものに様変わりしました。模擬問題での実戦演習も繰り返し、「何を書くと点がもらえるか」を体得しました。その結果、模試でも本番でも安定して6点を獲得できるようになったのです。
また、TCK WorkshopではIAのテーマ選定や論文添削もサポートしており、「研究設計→データ解析→論述」まで一貫した指導を提供しています。このように、試験対策とIAサポートを両立させられるのが、当塾の大きな強みです。
「うちの子に合うかも」そんな方こそ一度ご相談ください
今回の記事でご紹介した内容は、特に以下のような方にこそお役立ていただけます。
まず、IB Physicsで「5を超えられない」と悩んでいる生徒。特にPaper 2での減点が多く、「書けばいいのは分かるけど、何を書けばいいかわからない」と感じているケースは、まさに今回の解決策がフィットします。
また、IAの出来には自信があるものの、試験では点数に結びつかないというお子様にも有効です。時間内に考えをまとめ、論理的に説明する力は訓練で伸ばすことが可能です。
さらに、現在11年生やこれからIBを始める10年生も、今のうちから「使える公式理解」と「記述の型」を身につけておくことで、最終試験での得点力が大きく変わります。早期対策の価値は非常に高いといえるでしょう。
まずは気軽に始めてみませんか?無料相談・体験授業のご案内
「うちの子も同じ課題を抱えているかも」と感じた方は、まずは無料の教育相談にお越しください。専門講師が現在の課題を丁寧にヒアリングし、最適な学習プランをご提案いたします。
また、実際の授業の雰囲気を知っていただくための体験授業も随時受付中です。実力派講師によるマンツーマン指導を体感いただけます。
IB Physicsに特化した学習サポートを本格的に始めたい方には、週1回定期的に学校のフォローをしてもらうことがおすすめです。必要に応じて回数を増やすなどをして、テスト前は回数を増やすなどができます。時差や他アクティビティなどの関係上、定期的に時間が取れない場合は、長期休暇中の短期集中キャッチアップが効果的です。夏休み、冬休み、春休みの時間を利用して、ビハインドとなっている部分をしっかりとキャッチアップする時間を作ってみませんか?
このまま苦手を放置するか、今この瞬間から変えるか。その一歩が、将来の進学先の選択肢を大きく広げてくれるかもしれません。
まずは無料相談から、一緒に第一歩を踏み出してみませんか?